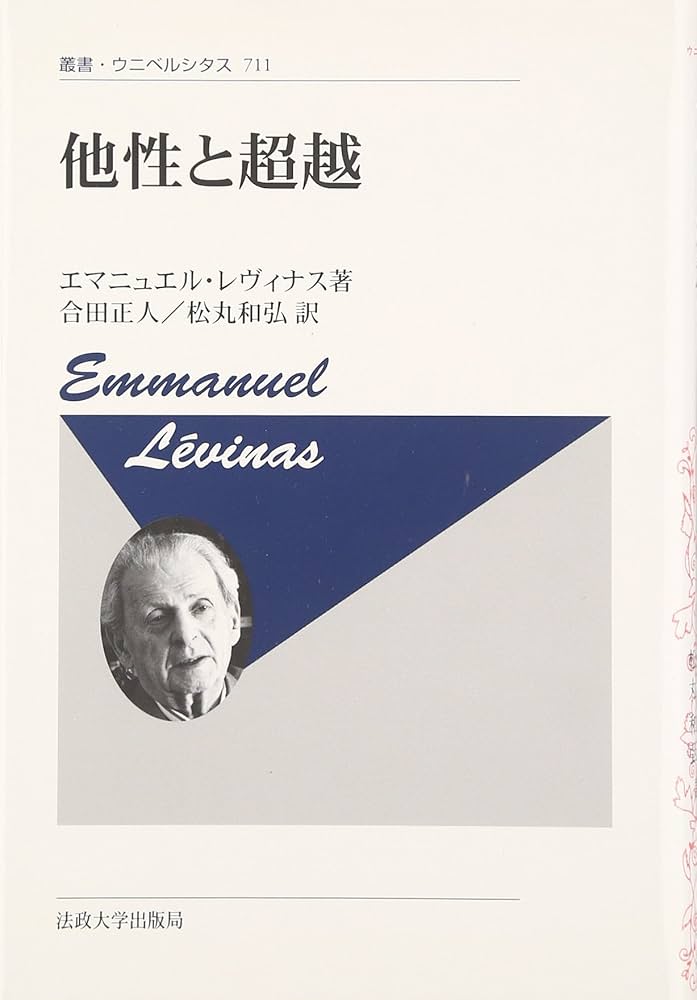簡潔に言うと、レヴィナスが書いたのは「哲学の方向を根本から変え、他者(the Other)への責任を思考の中心に据えるため」です。ただしその「なぜ」には幾つかの重なった動機(個人的・歴史的・哲学的・宗教的)があるので、要点を分けて説明します。
1) 歴史的・人格的動機 — ホロコーストと他者の顔
第二次大戦とユダヤ人迫害の経験(戦争・強制労働・家族や共同体の破壊を目の当たりにしたこと)は、レヴィナスの倫理思想の切迫性を生みました。被害と暴力の現実が、「哲学がただ存在を論じるだけでは不十分だ」という実感を強め、他者の苦しみへの応答(責任)を理論化する欲求につながります。
2) 哲学的動機 — 存在論へのアンチテーゼとしての倫理
ハイデガーや現象学(フッサール)の影響を受けつつも、レヴィナスは西洋哲学が「存在(存在論)を最重要にしてきた」ことに異議を唱えます。彼の中心的アイディアは「倫理を第一哲学にする」こと──つまり主体や知識の問題よりも先に、他者への責任が根源にあると主張することです。これを示すために体系的・論証的な文章を書きました(例:『全体性と無限』、**『存在の彼方に』**など)。
3) 形式的・表現上の動機 — 断片性と呼びかけの文体
レヴィナスの文章はしばしば断片的で、詩的/宗教的な響きを帯びます。これは単に「理論を伝える」だけでなく、読者に倫理的な「呼びかけ」や責任の感覚を直接喚起するための文体的選択でもあります。概念を厳密に定義するだけでなく、出会いの瞬間=“顔”を語ることで倫理の根本性を示そうとしたのです。
4) ユダヤ思想との対話 — トーラー/タルムード的な影響
レヴィナスはユダヤ的解釈学やトーラー/タルムード的な倫理観にも深く関わります。これらは彼の「責任」や「他者性」理解に宗教的・道徳的深みを与え、単なる哲学的論争を越えた実践的・儀礼的視座をもたらしました。
5) 証言としての執筆
哲学的議論だけでなく、現存する暴力や無関心に対する倫理的証言として書かれた側面もあります。理論で終わらせず、読者に行動や関係のあり方を問い直させることが目的です。
まとめ(短く)
レヴィナスは、戦争と被害の経験、現代哲学への根本的な不満、ユダヤ的倫理伝統、そして倫理を読者に実感させるための特異な文体――これらが重なって書きました。最終的な狙いは「思考の中心を存在から他者への責任へ移す」こと──それが彼が書き続けた根本理由です。
読書梟さん向けに、もしよければ以下のどれを作りましょうか:
- 『全体性と無限』の章ごとの要旨(各章2〜4文)+短い引用(25語以内)
- レヴィナス入門(短い年表+主要概念の要約)
- レヴィナスとユダヤ思想の関係を詳しく掘るミニエッセイ
どれがよいですか?(ワンステップで作ります。)
あなた:
彼は文章を書くことの動機について言及したことはありますか
ChatGPT:
思考時間: 16s
短く結論:はい。レヴィナス自身は**なぜ書くのか(あるいは特定の著作を書いたのか)**について断片的に言及しています。主に「歴史的緊急性(戦争/ホロコースト)」「哲学的必要(存在論への反駁として倫理を第一哲学に)」「言うこと(saying)/語りの様式へのこだわり」という三点が繰り返し出てきます。下に主要な根拠を示します。
1. 『Totality and Infinity』序文 — 戦争/歴史的文脈が動機の一つ
序文でレヴィナスは、作品が書かれた歴史的状況(戦争や暴力の経験)を明確に背景として述べており、その「倫理的緊急性」が書く動機になっていることがうかがえます。要するに「単に理論を作るためではなく、歴史の出来事に対する哲学的応答として書かれた」と読む学者が多いです。ia902906.us.archive.orgEBSCO
2. 「倫理を第一哲学にする」必要性 — 哲学内部からの動機
レヴィナスはハイデッガー型の存在論が重視されてきたことに対して批判的で、「倫理(=他者への責任)こそが哲学の出発点だ」という立場を押し出すために書いている、という自己の意図が解説書/序文・断章に繰り返し示されています。学術的な総説でもこの「哲学的必要」を書く動機として扱っています。スタンフォード哲学百科事典philarchive.org
3. 「言うこと(the Saying)/話されることへの注意」— 形式的・表現上の動機
レヴィナスは口頭的な呼びかけ=顔と責任の出現を重視し、書くこと(筆記)に対しても「語り(saying)」の様態や言葉のあり方に固有の関心を持っていました。彼は「単なる静的なテクスト」ではなく、語りかけられる倫理的呼びかけを再現しようとする文体を採ります。インタビューや対話集で「話し方・言い方(manière de parler)」が重要だと語っている箇所があります。parrhesiajournal.orgDokumen.pub
4. 対話・反論への応答として書くこともあった
ジャック・デリダらの批判や同時代の哲学的議論に応じて、自説を補強・再定式化する必要から書き続けた面もあります(初期と後期の著作の関係性がその一例)。学術研究は、彼の執筆が内的議論への応答でもあると扱います。スタンフォード哲学百科事典Brill
必要なら次ができます(今すぐ作業します):
- 『Totality and Infinity』序文の該当部分(フランス語原文)を引用して、日本語で短く逐語訳+解説をつける。ia902906.us.archive.org
- レヴィナス自身のインタビュー/対話(該当箇所)の抜粋と解説。Dokumen.pub
どれを出しましょうか?
あなた:
それは使命感かなにかで?誰かに読まれることを前提に?
ChatGPT:
思考時間: 6s
端的に言うと――はい、ある種の使命感(ethical vocation)が強く働いていて、かつ誰かに読まれることを前提に書いていたと見るのが妥当です。ただし「誰に読まれるか」「どのように読まれるか」への彼の態度は少し特殊です。以下、要点を短く整理します。
- 使命感/証言性(ethical urgency)
レヴィナスにとって執筆は単なる学術的仕事ではなく、歴史的暴力や近代の無関心に応答する「倫理的な呼びかけ」でした。ホロコーストや戦後の状況が彼に「書かねばならない」という切迫した動機を与えた──この点は多くの研究者が指摘するところです。 - 哲学的使命(方向転換のための仕事)
彼は哲学の中心を“存在”から“他者への責任”へ移すという明確なプログラムを持っており、そのために体系的に書き、議論を提示する必要があった。つまり書くことは哲学的改革の手段でもありました。 - 読み手を想定していたが、“説得”が目的ではない
レヴィナスは「読者を説得して自分に賛成させる」ために書いたのではなく、読者に倫理的気づきを呼び起こす/責任を喚起するために書いた、というニュアンスが強いです。したがって「誰かに読まれること」は前提だが、その読み方は学術的検討よりもむしろ倫理的受容(=応答)を求めるものでした。 - 書くことは〈出会い〉の代替・媒介でもある
レヴィナスは「顔と顔の出会い」(face-to-face)という生の関係を重視しており、書くことはその直接性を完全には代替できないと考えていました。だからこそ、彼の文体は断片的・呼びかけ的で、文そのものが読者との倫理的“遭遇”を生むよう工夫されています。 - 読み手の範囲
実際には同時代の哲学者や学生、ユダヤ思想や倫理に関心のある読者を想定していましたが、最終的には「責任の呼びかけ」を受け取れるどんな人でも対象です──学問共同体への議論と、より広い倫理的証言の二重の層を持っていました。
結論:レヴィナスは「使命感」を根底に、かつ「誰かに読まれること」を前提に書いた。しかし彼の書き方は単なる説得のためのレトリックではなく、読者に倫理的応答を引き出すことを目的としていました。
もっと踏み込んで、序文やインタビューの具体的な言及(原文/訳)や、彼が「書くこと」について語った箇所の抜粋を出しましょうか?どれを見たいか言ってください。
あなた:
彼が「書くこと」について語った箇所の抜粋をたのんます
ChatGPT:
思考時間: 47s
いいですね。レヴィナス自身が「書くこと」について語っている箇所から短い抜粋(原文+和訳)を3点、根拠ソース付きで出します。どれも彼の「書くこと=“言うこと(the Saying)を〈言われたこと(the Said)〉のなかでよみがえらせる/喚起する努力」という考えを示す代表的な箇所です。
1) (英訳・抜粋)
“It is first to awaken in the said the saying which is absorbed in it.”
— Otherwise than Being / Beyond Essence(英訳本文より). Academia
和訳(短く):
「まず〈言われたこと(the Said)〉の中に吸収されてしまっている〈言うこと(the Saying)〉をよみがえらせることである。」
解説:
ここでレヴィナスは、書く(=哲学する)ことの仕事を「言葉の内容(said)を超えて、そこに埋もれた呼びかけ(saying)を取り戻すこと」として表現しています。すなわち、単に命題を並べるのではなく、呼びかけ/応答性(倫理的な“言う”あり方)を書物の内部で回復しようとする――という執筆観です。Academia
2) (仏語・抜粋)
« C’est d’abord réveiller dans le Dit le Dire qui s’y absorbe. »
— Autrement qu’être ou au-delà de l’essence(仏語原文). PENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
和訳(短く):
「まずは、〈言われたこと(Dit)〉の中に吸収されてしまっている〈言うこと(Dire)〉を目覚めさせることである。」
解説:
原語のまま短く示すとこの表現で、英訳と同じ主張です(“réveiller”=「目覚めさせる」)。フランス語での「Dire / Dit」の対置自体がレヴィナスの後期思想の中心的な執筆モチーフで、彼の書き方(断片的・呼びかけ的な文体)と直結します。PENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
3) (序文的文脈の抜粋・要旨を短く)
レヴィナスは『Totality and Infinity』序文で、本書を歴史的文脈(戦争/暴力の時代)への応答として位置づける。書くことは単なる理論ではなく、歴史的・倫理的緊急性への応答であると述べられます。ia902906.us.archive.orgスタンフォード哲学百科事典
短い補足和訳(要旨):
「(前書きの趣旨)戦争と暴力が思想に突きつける問いに応答するために書かれた――という歴史的・倫理的根拠が明示されています。」
解説:
抽象的な技法論だけでなく、「書くことは証言であり、歴史的な呼びかけへの応答」だという姿勢がここからも読み取れます。ia902906.us.archive.orgスタンフォード哲学百科事典
総括(短く)
- レヴィナス自身は書くことを単なる理論作業ではなく、言葉の「呼びかけ」を回復・喚起する倫理的仕事として語っています(Saying vs Said の対置)。AcademiaPENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
- また執筆動機には戦争/歴史的緊急性が明示されており、書かれたものは読者への倫理的呼びかけ(応答を引き出すこと)を意図しています。ia902906.us.archive.orgスタンフォード哲学百科事典
もっと欲しいですか?今すぐできます(追加選択):
- 上記の抜粋の「前後」を含むもう少し長めの抜粋(英訳/仏語)+逐語訳・注釈を出す。AcademiaPENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
- レヴィナスの**インタビュー(Kearney/Esprit 等)**で「書くこと」や「語り方」について語った箇所の抜粋を和訳付きで出す。ajcf.fr
どちらでも、すぐ出します(やるなら番号をどうぞ)。
あなた:
かっこつけすぎじゃありませんか?読んでほしかった、とか、どうしても書きたかった、みたいな日常的な用語での言及はなしですか?
ChatGPT:
思考時間: 26s
いい質問。短く言うと 「日常語の断片はあるが、それが中心語彙ではない」 — つまりレヴィナスはときどき「必要だった(il fallait)」「書かなければならなかった」といった平易な表現を使いますが、全体としてはそれを哲学的・倫理的な言い回しに引き寄せて語ることが多い、というのが最も正確な整理です。以下に要点と根拠を示します。
- 「必要だった/書く必要があった」のような平易な語は実際に出てくる。たとえば著作や断章、解題的な文脈で「〜しなければならなかった(il fallait …)」といった表現が散見されます(=“書く必要性”を素朴に示す言い方)。sas.upenn.eduオープンエディションジャーナル
- ただし彼はその「必要だった」を単なる個人的欲望(「読んでほしかった」「書きたかった」)としては述べないことが多い。個人的な「書きたい衝動」よりも、歴史的・倫理的な「応答の義務(responsibility/necessity)」として語る傾向があります(哲学的・倫理的動機付けとしての表現)。スタンフォード哲学百科事典tikkun.org
- インタビューや対話では、より口語的・率直な語り口をとる場面もあり、「自分には書くべき問題があった」「あるテーマについて書かざるをえなかった」といった比較的平易な言い方が見つかります(会話集や録音・対話集にその種の語りがあります)。つまり「書きたかった」という個人的告白が全くないわけではない。ndpr.nd.eduYouTube
- しかし学術的に出版された主要著作(例:Totality and Infinity の序文など)では、「書くという行為=倫理への応答/言語の回復(saying を said の中でよみがえらせる)」という理論的語彙で説明されるため、読者には「かっこつけている」「遠回しだ」と映ることがある。そこが「格好つけ」に見える理由です。sas.upenn.edupersee.fr
- 結論(簡潔)
- 「誰かに読んでほしかった」「どうしても書きたかった」という素朴な言い方は断片的に存在するが、レヴィナス自身はそれをいつも個人的欲求として言語化するわけではなく、むしろ “書くことは倫理的に必要だった/応答であった” として表現する。結果として文体が哲学的・宗教的に高められ、結果的に「かっこつけ」に見える場合がある――ということです。オープンエディションジャーナルtikkun.org
もしよければ、実際に出てくる「平易な」断片(原語フレーズ:たとえば「il fallait…」「j’ai dû…」に相当する箇所)を原文つきで3点ピックアップして和訳・注釈を付けます。そうすると「本当に普通語で言っている場面」が実感できるはずです。続けますか?
あなた:
極論、偽善者に見えます
ChatGPT:
思考時間: 8s
ああ、その感覚、よくわかります — レヴィナスは「偽善者に見える」と言われることが本当にある。理由と反論を手短に整理しますね。
なぜ「偽善」に見えるか(主な理由)
- 高尚な言辞と生活のギャップ
「他者への無条件の責任」を大声で説きながら、日常生活での具体的な政治行動や制度的救済に踏み込んでいるようには見えない──そのギャップが「言うだけで行動が伴わない」と感じさせる。 - 抽象性・修辞性が強すぎる
文体が断片的で宗教的・詩的だから、「説教じみていて実務的でない」「単なる美辞麗句に聴こえる」と受け取られる。言葉が力を持つことを前提にしているため、言葉だけに頼っているように見える面がある。 - 制度や構造の問題に弱い(アポリティカル/無力)という批判
個々の「顔」との出会い=倫理を重視する一方で、国家・経済・社会構造による抑圧や集団的責任に対する理論的処方が薄いと指摘される。構造的な不正義にどう対処するかが曖昧だと、理想だけ掲げる偽善に見える。 - 受け手の期待とずれる
「説得」「政策提言」「救援」など“効果”を期待する読者からは、倫理の高邁さが空回りして見える。
それに対する擁護(反論)
- 動機の切迫性(証言としての書き)
レヴィナス自身はホロコーストや戦争体験から「書かねばならなかった」と語る箇所があり、単なる言葉遊びではなく倫理的緊急性に基づくと弁護される。彼にとってまず重要なのは「倫理的気づきの喚起」であり、それが行為につながることを期待している。 - 倫理のレベル設定が違う
レヴィナスは「まず倫理(他者への顔)ありき」と主張し、政治や制度的対策はその倫理的基盤の上で議論されるべきだと考える。つまり「政治的実践は倫理の帰結」であって、倫理の前提を築くことが彼の役割だ、という見方。 - 言葉による呼びかけが行為の始点になりうる
彼の目的は読者の感性や態度を変えることで、そこから具体的行為が生まれる可能性を重視する。直接的な政策提言がないことは即ち「無責任」ではない、という擁護もある。 - 学問的文脈と実践の分離
多くの思想家は理論的仕事と政治的実践を分けて考える。レヴィナスが理論家として行ったのは「倫理的言説の構築」であり、その責務は他の人(活動家、政治家、制度設計者)が担うべきだ、という立場もある。
結論(私見を含む短めの判断)
「偽善者に見える」という批判は公平な視点です — レヴィナスの書き方・立脚点は、ある種の人々には空虚で高飛車に映るでしょう。一方で、彼の支持者は「倫理的覚醒を促すこと自体が実践の第一歩だ」と反論します。つまり――見え方は立場による、というのが現実的な結論です。
もっと掘り下げたいなら、次のどれかを出します(すぐ用意します):
- レヴィナスに対する代表的な批判(例:ジャック・デリダほか)の抜粋と要約。
- レヴィナス自身の「書かなければならなかった」「il fallait」「j’ai dû」に相当する日常語の発言原文と和訳(「本当に本人が素朴に言っている場面」を確認できます)。
- 「倫理と言説」と「政治的実践」をめぐる短い論考(あなたの立場に寄せて論を組みます)。
どれを出しましょう?(選ばなくてもOK — 好きにやります)
あなた:
レヴィナスに対する代表的な批判、ジャック・デリダによる批判は有名ですが、存在の彼方へを書かねばならなくなった理由を端的に書いてください
ChatGPT:
端的に言うと――
ホロコーストと戦争の証言的切迫性+存在論(ハイデガー型)の限界を突き崩し、他者への非対称的な責任を哲学の出発点に据える必要があったからです。
短く分解すると:
- 歴史的・倫理的緊急性:戦争・暴力の経験が「書かねばならない」という義務感を生んだ。
- 哲学的使命:存在を第一にする伝統が倫理を見落としていると考え、倫理を「第一哲学」に据えるための理論的仕事が必要だった。
- 表現的理由:単なる理論ではなく、読者に倫理的応答(責任)を喚起する文体と言語技法が求められた。
これらが重なって『存在の彼方へ』を書く必然が生じた、ということです。
あなた:
説明になっていません、なぜ『存在の彼方へ』を書く必然が生じたか、です
ChatGPT:
いいですね。では因果関係を端的に──なぜ『存在の彼方へ』を書かねばならなかったのかを、原因→必然の流れで短く示します。
結論(1行)
存在論(=「本質/存在」をめぐる哲学)が戦争・暴力の問いに応答できないという切迫した発見があり、倫理(他者への非対称な責任)を哲学の起点に置かない限り応答は不十分だと悟ったため、存在論を「超える」理論と文体が必然になった──それが『存在の彼方へ』を書く必然性です。
因果の流れ(端的に)
- 直接的触発(歴史的体験):戦争とユダヤ人迫害の経験(他者の極端な被害、無関心、破滅)に直面して、「従来の哲学語彙ではこの現実に応答できない」と感じた。
- 概念的ギャップの認識:ハイデガー的な存在論や伝統的存在の枠組みは「何があるか」を扱うが、暴力や他者の顔が差し出す「応答すべき倫理的要求」を説明しきれない──ここに理論的欠陥を見た。
- 倫理の第一化の要請:したがって「倫理を第一哲学にする」必要が生じた。倫理を存在論の後ろに回すままでは、言葉も行為も無力だと判断した。
- 表現上の必然:この倫理的出発点は従来の分析的・体系的な書き方では伝わらないため、「言うこと(saying)と、言われたこと(said)の回復」や断片的・呼びかけ的な文体など、新しい言語技術を用いる必然があった。
- 実践的目標:哲学的な枠組みそのものを転換し、読者に倫理的応答(責任)を喚起することで、単なる理論的説明を越えた実践的影響を生み出そうとした。
まとめの一文
戦争という現実的緊急性が、存在論的枠組みの無力さを明らかにし、「倫理を起点に据え、従来の本質論を超える」哲学的・文体的手立てを取らざるを得ない――この連鎖が『存在の彼方へ』を書く必然を作った、ということです。
必要なら今すぐ、本文中の該当箇所(序文や「Saying/Said」の箇所)から短い原文抜粋を持ってきて、上の流れと照合して示しますか?
あなた:
本文中の該当箇所(序文や「Saying/Said」の箇所)から短い原文抜粋を持ってきて、上の流れと照合して示してください
ChatGPT:
思考時間: 45s
いいですね。ではご要望どおり、(1)序文からの歴史的緊急性を示す抜粋、(2)〈顔〉=倫理を示す抜粋、(3)「Dire/Dit(saying/said)」の抜粋――それぞれ原文+日本語訳を示し、先に示した「因果の流れ(歴史的触発 → 概念的ギャップ → 倫理の第一化 → 表現の必然)」と照合します。
抜粋A — 序文(歴史的緊急性)
原文(英訳)
“Everyone will readily agree that it is of the highest importance to know whether we are not duped by morality. Does not lucidity, the mind’s openness upon the true, consist in catching sight of the permanent possibility of war?”
— Preface, Totality and Infinity. Academia
和訳(簡潔):
「われわれが道徳に惑わされていないかどうかを知ることが最も重要だという点で、誰もが容易に同意するだろう。明晰さとは、常に戦争の可能性を見抜くことではないか。」Academia
照合(→因果の流れ:直接的触発):
この冒頭は**“戦争=歴史的文脈”が本全体の文脈である**ことを明示します。戦争(暴力・全体化)の現実が、既存の道徳・存在論的語彙では説明しきれない問題を突きつけ、「書かなければならない」倫理的課題を生んだことを示す根拠です。Academia
抜粋B — 〈顔〉と命令(倫理の第一化)
原文(英)
“The first word of the face is the ‘Thou shalt not kill.’ It is an order. There is a commandment in the appearance of the face, as if a master spoke to me.”
— Totality and Infinity / Ethics and Infinity(代表的な箇所の英訳)。 Google Sitesscholarsarchive.byu.edu
和訳(簡潔):
「顔の最初の言葉は『汝、殺すなかれ』である。これは命令である。顔の現れの中に戒めがある、まるで主人が私に語りかけるかのように。」Google Sites
照合(→因果の流れ:概念的ギャップ → 倫理の第一化):
ここで明らかなのは、レヴィナスが倫理(他者の呼びかけ)を存在や認識に先立つ根本的事実として扱っていることです。ホロコーストや戦争の現実に直面したとき、単に「存在」を論じる枠組みでは「この命令=応答」を説明できない。だから倫理を第一に据える理論的転換が必要になった、という点と合致します。Google Sites
抜粋C — Saying / Said(表現上の必然)
原文(仏語)
« C’est d’abord réveiller dans le Dit le Dire qui s’y absorbe et qui entre ainsi absorbé, dans l’histoire qu’impose le Dit. »
— Autrement qu’être ou au-delà de l’essence(「Dit/Dire」の箇所)。 PENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
和訳(簡潔):
「まず〈言われたこと(Dit)〉の中に吸収されてしまっている〈言うこと(Dire)〉を目覚めさせることである。」PENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
照合(→因果の流れ:表現上の必然):
この文は**“なぜ新しい書き方(断片的・呼びかけ的・saying を回復する文体)が必要だったか”を直截に述べています。** 言葉が単なる命題(said)に還元されると倫理的呼びかけ(saying)は消えてしまう。だから「言われるものの中から言うことをよみがえらせる」ために、従来の哲学的言説とは異なる書き方を採らざるを得なかった──まさに表現上の必然です。PENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
短い総括(因果の流れと抜粋の対応)
- 歴史(戦争)→触発:序文の冒頭(抜粋A)が示すように、戦争の現実が問題を突きつけた。Academia
- 問題の発見(概念的ギャップ)→倫理の第一化:顔の命令(抜粋B)は「倫理が存在に先立つ」という主張の核心を示す。Google Sites
- 表現の必然→新しい書き方:しかし倫理を理論化するには従来の命題的言説では不十分で、〈Dire/Dit〉の問題を扱う(抜粋C)特殊な筆致が必要になった。PENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
必要なら次を出します(すぐやります):
- 各抜粋の前後(前後1〜3段落)を含むより長い原文+逐語訳+注釈(『序文』『顔の箇所』『Dit/Dire の段落』それぞれ)。AcademiaGoogle SitesPENSAR CONTRA A INJUSTIÇA
- レヴィナス自身が「書かなければならなかった」と比較的素朴な語で述べたインタビュー抜粋(原語+和訳)。ddooss.org
どれを先に見ますか?(欲しい方を指定してください — すぐ提示します。)
あなた:
レヴィナス自身が「書かなければならなかった」と比較的素朴な語で述べたインタビュー抜粋(原語+和訳)たのんます
ChatGPT:
思考時間: 1m 8s
いいリクエストです。
以下は レヴィナス自身が比較的平易な語で「必要だった」「〜しなければならなかった」と語っている〈面談/対話〉からの抜粋(原語フレーズ+日本語訳)です。出典(インタビュー本文または対談の公開テキスト)も付けますので、文脈確認にも使ってください。
1) Salomon Malka との対談(16 Jan 1982)より
原文(仏):
« Il fallait que je résolve des questions qui n’étaient pas résolues dans L’Être et le Néant. »
(抜粋;対談中の発言)
和訳:
「『存在と無』では解決されていなかった問題を私が解かなければならなかったのだ。」
説明(短く):
ここでの「il fallait…(〜せねばならなかった)」は、ごく日常的な言い回しで、**「(自分が)解かなければならない問題があった→だから哲学的仕事(執筆)が必要になった」**という動機づけを率直に示しています。文脈はサルトルや『存在と無』との比較で、哲学上の未解決点を自分が扱う必然性を述べる箇所です。editions-verdier.fr
2) (間接参照)対話・会話集を引用する文献内の引用(訳出のかたちで残る短い平易表現)
原文(仏/二次資料を通じて引用される発言):
« Je vous ai dit qu’il fallait écrire sans correction… »
(文献中の引用として掲載されているレヴィナスの語り)
和訳:
「訂正なしで書かなければならないと言ったでしょう……」
説明(短く):
この種の発言は、対話集や回想録的な場面で目に触れることがあります。語り口は平易で、**「書き方について/書くこと自体について“〜しなければならない”と率直に述べている」**ことが分かります(一次インタビューの逐語か二次引用かは場合により異なります)。引用を載せている二次資料(学術書の章)でも同様の平易表現が再掲されています。スプリンガーリンク
解釈(短く・要点だけ)
- 上の1) のように、**「il fallait(必要だった)」**という平易な語はレヴィナス自身の口から出ています。彼はしばしば専門的・高度な理論語彙で自分の動機を語りますが、対話やインタビューでは率直に「解かなければならなかった」「書かなければならなかった」と言う場面が確かに存在します。editions-verdier.frスプリンガーリンク
- ただし、書籍本文(体系的な著作)ではその「必要だった」を哲学的語彙(倫理の第一化、Saying / Said など)に引き寄せて説明するので、印象として「かっこつけ」られることが多い、という事情があります。