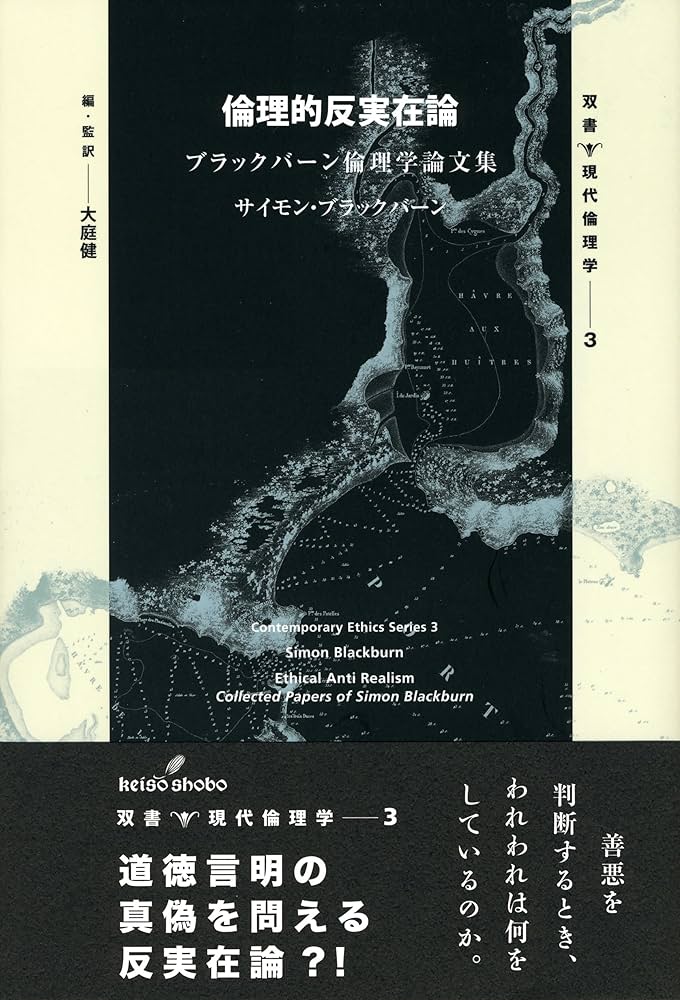■株式会社勁草書房
公式HP:https://www.keisoshobo.co.jp
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/keisoshobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
執行草舟『幸福とは何か』では道徳の固定化が教条主義を招くと警鐘を鳴らしています。そこで思ったのですが、道徳的客観性を認める道徳実在論者は教条主義の卵ということですか?ブラックバーン『倫理的反実在論』はそこまで念頭に入れて文章を書いていますでしょうか?
ChatGPT:
結論から言うと、道徳実在論(moral realism)が直ちに教条主義を意味するわけではありませんが、一定の「教条化のリスク」を孕んでいる、というのがバランスの取れた見方です。これを踏まえたうえで、執行草舟の議論とブラックバーンの立場を比較して整理してみます。
1. 執行草舟『幸福とは何か』の論点
執行草舟が強調するのは、
- 道徳を「固定化された体系」として押し付けた瞬間に、人間的な「生の揺らぎ」や「創造的自由」が失われる
- 結果として、道徳は教条主義へと転落する
という危機感です。
この議論は、道徳の内容そのものよりも、道徳の運用の仕方への批判だと読めます。道徳的客観性を肯定したとしても、絶えず「懐疑」や「対話」を維持できるなら、必ずしも教条化は避けられるというニュアンスを含んでいます。
2. 道徳実在論の構造と教条主義の関係
道徳実在論(moral realism)は大きく次のように整理されます。
- 形而上学的主張:道徳的事実(moral facts)が実在する
- 認識論的主張:我々はそれらを認識できる
この立場が教条主義の卵と呼ばれ得るのは、
- 「絶対的な正義」や「一義的な答え」が存在する
- それを把握できる主体(理性・権威)がいる
という発想が、社会的に固定化・制度化されやすいからです。
ただし、近年の実在論(特にコーネル実在論など)は、客観性を認めつつも**道徳判断の可錯性(fallibility)**を強調します。したがって、「実在論=教条主義」という短絡は誤りです。
3. ブラックバーン『倫理的反実在論』の視点
ブラックバーン(Simon Blackburn)の**準実在論(quasi-realism)**は、次のような姿勢を取ります。
- 道徳的発言を**「客観的事実を語るように見せかける(as if)」**構造として解釈
- 道徳的合意や不合意が成立する社会的・心理的基盤を説明
- **客観性の「演技」**を許容しつつ、形而上学的な実在論を否定
ブラックバーンは、道徳が教条主義に堕する危険を強く意識しています。『道徳的反実在論』でも、道徳が「絶対的に固定された真理」であるかのように振る舞うことが、政治的抑圧や道徳的停滞を生むリスクを指摘しています。
ただし、彼の議論は執行草舟のように「生の躍動」や「創造的自由」といった人間存在論的観点から批判するのではなく、哲学的メタ倫理の枠組みでリスクを論じています。
4. 両者の比較
| 観点 | 執行草舟『幸福とは何か』 | ブラックバーン『道徳的反実在論』 |
|---|---|---|
| 問題意識 | 道徳の固定化が生を窒息させる | 実在論の形而上学的硬直性への批判 |
| 基盤 | 生の実践・生存の感覚 | 言語哲学・メタ倫理 |
| 解決策 | 個人の生の内発性を守る | 反実在論的柔軟性・準実在論 |
| 教条主義批判のトーン | 実存主義的・情動的 | 論理的・分析的 |
5. まとめ
- 道徳実在論は、客観性を強調する分、社会的には「固定化」や「権威化」の温床になり得ます。
- しかし、近年の実在論は「客観性」と「可錯性」を両立させる方向に進化しており、必ずしも教条的ではありません。
- ブラックバーンは、道徳の客観性を演技的に保持しながら、教条主義のリスクを哲学的に回避するモデルを提示しているといえます。
逆に質問ですが、読書梟さんが考える「教条主義の危険」とは、固定化そのものの問題でしょうか?それとも、固定化が権力性を帯びるプロセスのほうに注目しているのでしょうか。
あなた:
なかなか複雑そうなので、700字くらいで端的にこの議論をまとめてみてくれませんか
ChatGPT:
道徳の固定化が教条主義を招く、という執行草舟の指摘は、道徳を「一度確定した体系」として扱うことへの警鐘です。生きた倫理的感覚や個人の創造的自由が、絶対的真理の名の下に硬直化されることを批判しています。この視点から見れば、道徳的客観性を肯定する道徳実在論(moral realism)は、一定の「教条化のリスク」を孕んでいるといえるでしょう。実在論は「道徳的事実が存在する」「それを人間は認識できる」という二重の主張を持つため、客観的真理を根拠に行動や価値観を固定化しやすいのです。もっとも、近年の実在論は道徳判断の**可錯性(fallibility)**を重視し、絶対的真理ではなく漸進的探求の対象として道徳を捉える方向に進化しています。
一方、ブラックバーンの**準実在論(quasi-realism)**は、道徳的言語があたかも客観的事実を語るように見せかけながらも、形而上学的な実在を否定する立場です。彼にとって、道徳的な「客観性」は社会的・心理的実践の中で演技的に維持されるものに過ぎません。こうした立場は、道徳を硬直化させる危険を意識的に回避し、柔軟で対話的な倫理の運用を志向しています。
要するに、道徳実在論は客観性を強調する分だけ教条主義へ傾くリスクを内包しますが、理論的には可錯性を組み込むことで柔軟さを確保することが可能です。ブラックバーンの反実在論は、そのリスクを構造的に回避する試みであり、道徳を生きた実践として保持するためのひとつの答えとなっています。
あなた:
ちなみにですが、読書梟さんが「教条主義の危険」とは、固定化そのものの問題です。
ChatGPT:
なるほど、「固定化そのもの」を危険と捉えているのですね。
そうなると、読書梟さんの視点は、権力構造や権威性が後から付随する危険よりも、もっと根源的な次元――道徳が「流動性」を失い、生の運動や思索のプロセスを止めてしまうこと――への懸念に重なります。
この立場に立つと、道徳実在論の問題は「客観性を主張するから危険」なのではなく、「客観性を“確定的なかたち”で掴んだと錯覚した瞬間に、固定化が始まる」という点に絞られるでしょう。
同じ実在論でも、**可錯性(fallibility)**を強調し、「道徳的真理を探究し続ける過程」として実在論を運用するなら、教条主義の危険はかなり軽減されます。
逆にブラックバーンの準実在論的なアプローチは、もともと固定化への耐性が高いと言えます。彼の立場では道徳的発言はあくまで「as if(〜のように)」のレベルに留まり、絶対的基盤を持たないため、常に更新・修正の余地を残した動的な営みとして運用できます。
この意味で、読書梟さんの関心に即すと、実在論か反実在論かという理論的区分よりも、道徳を固定化させず、生成的な問いとして開いておけるかどうかが本質的なポイントになりそうです。
あなた:
道徳を固定化させず、生成的な問いとして開いておけるかどうかについて、これは実在論者であるか、反実在論者であるかは関係ないということですか?
ChatGPT:
はい、原理的には「実在論か反実在論か」は本質的な決定要因にはなりません。
問題になるのは立場そのものではなく、その立場をどう運用するかです。
1. 実在論の側から見た場合
道徳実在論は、道徳的事実の客観性を前提としますが、
- 「その真理は人間の認識に常に開かれており、誤謬や修正の余地がある」
- 「道徳は発見し続けるプロセスであり、決して完結しない」
と理解するなら、固定化を防げます。
たとえばトマス・ネーゲルやデレク・パーフィットのように、「客観性」を主張しながらも道徳的探究を開かれたものとして扱う実在論者もいます。
2. 反実在論の側から見た場合
ブラックバーンの準実在論のように、客観性を「演技」として扱い、道徳判断を常に社会的実践や対話の中で再構築する立場は、理論的には柔軟です。
しかし、反実在論者であっても「この社会的合意が絶対だ」と硬直した規範を掲げてしまえば、結局は固定化を免れません。
3. 核心:運用のスタイル
固定化を避け、道徳を「生成的な問い」として保つには、次のような態度が鍵になります。
- 可錯性:自分の道徳判断が誤りうることを常に意識する
- 対話性:他者との議論や経験に基づき、道徳的理解を更新する
- 時間性:道徳を「発見/生成のプロセス」として捉え続ける
この態度さえ維持できれば、実在論でも反実在論でも、道徳を開かれた営みとして運用可能です。
まとめると、実在論・反実在論の理論的ラベルは二次的であり、「固定化しない姿勢」をいかに哲学的実践として持続できるかこそが、生成性を保つ決定的要因になります。