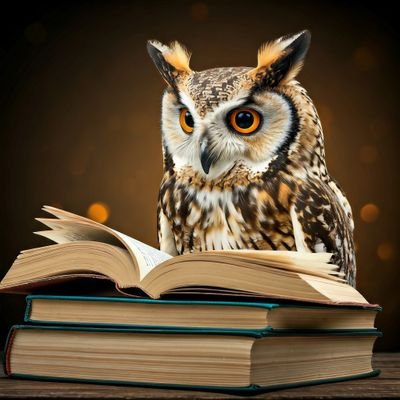1. 導入 ― 書くことと記録することの迷路
noteを書いてnoteで読む。その行為をノートする――そんな無限ループに、自分でも少し笑ってしまう。
SNSに疲れた人々がnoteに流れ着き、そこにまた物語を見出す時代。だが、記録が記録を呼ぶこの迷路には、なぜか“後ろめたさ”がつきまとう。
2. 「note化」現象の分析
noteは便利だ。
ワンクリックで書けて、瞬時に公開できて、誰もが小さな「書き手」になれる。
でも、ふと気づく。「これは本当に“書く”という行為なのか?」と。
- 平易さの暴力性
書くことの敷居が下がった分、書くことへの“真剣さ”もどこか漂白される。 - 演出過剰の自己言及
「書く私」を見せるために、書く。「#今日のnote」というタグに象徴されるように、書くこと自体がコンテンツ化する。
つまり、noteは「書くこと」を加速させる装置であると同時に、「書かれること」を消費する機構でもある。
3. 哲学的展開 ― 無限連鎖のなかで
デリダが言うように、「書き込みは常に他者への遅延を伴う」。
noteで書いた文章は、書いた瞬間に「過去の自分」に属する。
そこに重なるのは、「記録されること」と「忘却されること」の同時性だ。
書くことは、失われることへのささやかな抵抗である。
だから、noteは記録であり、同時に消費であり、そして忘却のためのプラットフォームでもある。
記録のために書いたはずが、次のnoteが前のnoteを押し流す。そのスピード感は恐ろしいほどだ。
4. 読書梟的ユーモア
この現象をどう見るか。
私はときどき、noteのタイムラインを眺めながら「全員が哲学者」だと思うことがある。
- 誰かが「自分探し」を語り
- 誰かが「今日の気づき」を書き
- 誰かが「推しの尊さ」を解剖し
- 誰かが「文章術」を売る
そして私はまた、その光景を「noteのnoteをノートする」。
書くことに「意味」を見つけようとして、結局はズレを抱きしめながら。
5. 結論 ― ノート化された思考を読み返す
noteは、書くことの民主化を確実に進めた。
しかし同時に、「記録が氾濫する社会」をも可視化させた。
書いたものを、再びノートして、もう一度読むこと。
この反復のなかでしか、批評的なまなざしは育たないのかもしれない。
書かれたものは、書かれた瞬間に記録を超える。
そして今日も私はnoteを開き、また書き始める。
書くことと読むこと、その果てしない往復運動を「ノート」と呼びながら。