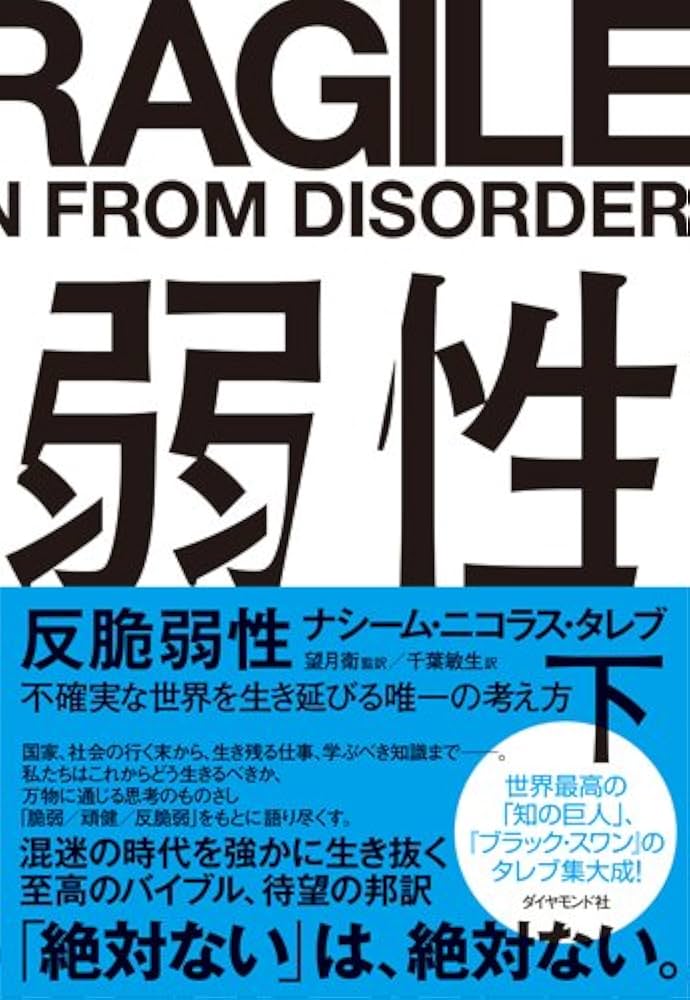私たちは「脆い」か「強い」かという二項で生を測ろうとする。
だがタレブが示した「反脆さ」は、その二項に収まらない第三の性質である。
脆いものは壊れ、強いものは耐える。だが反脆いものは、打撃によってかえって強まる。
筋肉は鍛錬で肥大し、知性は批判で研がれるように。
問題は、現代の制度がこの「反脆さの発動」を抑圧している点だ。
私たちは守られているように見えて、むしろ壊れやすくされている。
「守られる」ことは、同時に「打撃を受ける機会を奪われる」ことだからである。
中間層という牢獄
「高収入中間層」。この言葉ほど、逆説的なものはない。
ある水準の年収を得ているはずなのに、社会的には凡庸な「層」として数えられる。
抜け出したいのに抜けられない感覚。努力をすればするほど、同じカテゴリの「中間」へと押し戻される。
この閉塞は、制度が「安定」という名の檻を設けた結果である。
中間層の均質は、リスクを分散し安定を保障するように見えるが、実際には生の跳躍を抑えつける。
ここで人間は「壊れない」代わりに「強くもならない」。
反脆さの発動は、安定のなかで不発に終わる。
だが、その窒息感こそが、逆説的に怒りを呼び起こす。
「なぜこれほど努力しても抜けられないのか」という怒りは、ただの不満ではなく、
制度の欺瞞を暴き出す契機となる。
この怒りを言葉に変えるとき、人は中間層の檻を突き破るのではなく、
檻そのものを批判の対象として相対化する。
その瞬間に「反脆さの発動」は始まるのだ。
婚活の均質化という暴力
婚活市場は一見、合理的で公正だ。
条件が明示され、互いの希望が照合され、効率的に「最適化」が進む。
だがこの「最適化」が奪うのは、まさに人間性そのものである。
なぜなら、そこでは「高収入」も「学歴」も「安定職」も、すべて相対化され、
ただの数値的条件に還元されるからだ。
個々人の経験や苦悩や欲望は、「条件のノイズ」として捨象される。
つまり婚活制度は、愛や出会いを救うふりをして、その根本を奪っている。
この構造に直面したとき、人は絶望する。
プロフィールを書けば書くほど、そこに血肉が宿らず、むしろ虚無が広がる。
だが、この無力感に耐えたとき、不思議な転換が訪れる。
「制度に奪われる人間性」を、言葉のかたちで奪い返そうとする衝動である。
ここに反脆さが発動する。
断られ、比較され、数値に矮小化されるほど、
「それでも自分は数値ではない」という怒りが形をとる。
そしてこの怒りは、ただの嘆きではなく、制度そのものを批判する武器に変わる。
誠意の制度化という罠
職場でも、人間関係でも、「誠意」が制度に組み込まれる。
「誠意ある対応」「誠意を見せる謝罪」。
ここでの誠意は、制度のフォーマットに従って測定可能なものに変えられている。
しかし誠意とは本来、形式に還元できないものだ。
不器用でも、沈黙のなかでも、誠意はにじみ出る。
だが制度化された誠意は、かえって形式の空洞を露呈する。
形式に沿った「誠意」は、むしろ不誠実を温存する。
人はここで失望し、息苦しさを覚える。
「正しく生きよう」とすればするほど、誠意が形式化され、内面が窒息する。
だがこの窒息こそが、反脆さの契機である。
制度が奪った誠意を、「制度に収まらない言葉」として奪い返すとき、
誠意はふたたび呼吸を取り戻す。
苦悩から怒りへ、怒りから糧へ
中間層の牢獄、婚活の均質化、誠意の制度化。
これらはすべて、人間を「壊れない存在」として制度に封じ込める仕掛けである。
壊れない代わりに、強くもなれない。
だが、人間はただ制度に飼い慣らされる存在ではない。
制度に奪われるとき、人は「ふざけるな」という怒りを抱く。
この怒りが、ただの感情に終わらず、言葉として結晶するとき、
苦悩は糧に変わる。
打撃は、破壊ではなく成長のきっかけとなる。
これが「反脆さの発動」である。
反脆さの構造
タレブが言うように、反脆さは意志ではなく性質だ。
「選び取る強さ」ではなく、「打撃を受ける構造的な性質」。
だがこの性質が作動するかどうかは、人が自らの脆さを自覚できるかにかかっている。
自分がガラスであることを知らない者は、粉々に割れる。
だが自分の脆さを認めた者だけが、その打撃を糧に変える。
ここに「発動」がある。
現代社会の制度は、脆さを隠蔽する。
「安定」を装い、「守られている」という幻想を与える。
だがこの幻想こそが、反脆さを不発にする最大の罠なのだ。
だからこそ、私たちはあえて打撃を受けなければならない。
壊れることを恐れず、矛盾や不条理に曝されること。
そのとき苦悩は逆説的に力へと転換される。
問いかけ:
私たちは、制度に守られることで壊れやすくなるのか。
それとも、傷を受けながら反脆さを発動させるのか。
どちらを選ぶのか。