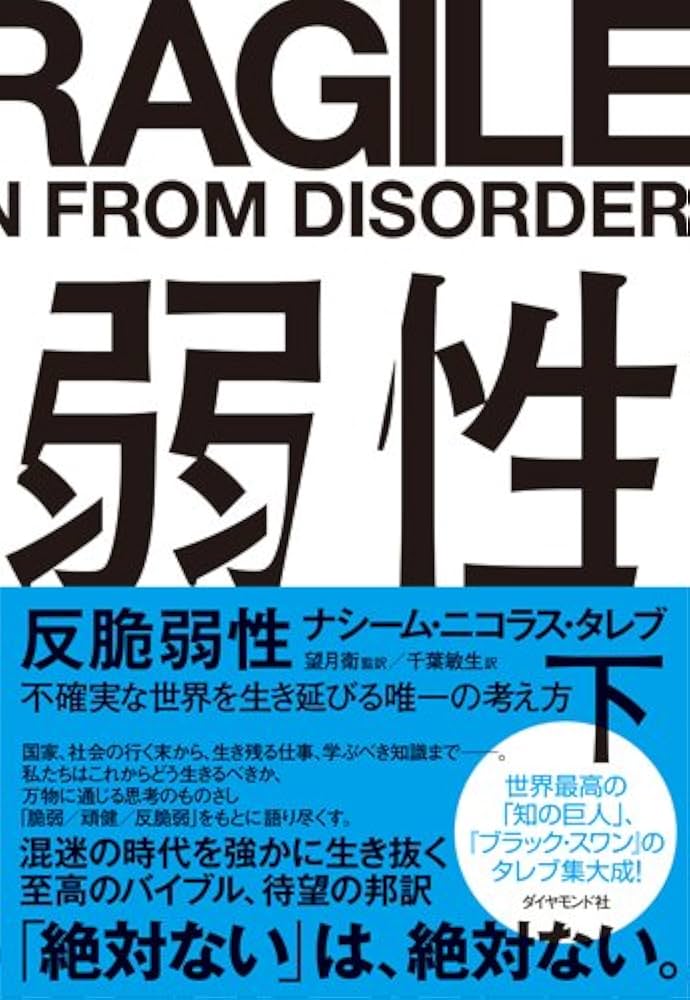■株式会社ダイヤモンド社
公式HP:https://www.diamond.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
職場で熱や胃腸がやられてしまい、欠勤する人が増えた。作業所は何らかの障害をもった人が参加する。いうまでもなく、最近の傾向としては私を含めやはり精神的な部分でサポートが必要な人が多い。しかし、、、
あまりに身体的な体調不良(熱やお腹の調子が悪い等)を訴える作業者が多い。これは医原病を疑うレベルだと思った。タレブ『反脆弱性』の170項あたりはタイムリーに、医原病が考察される。たとえば、「本当に紫外線対策は必要なのか?」といった、医者と製薬会社に絡む、利害関係者にとっては耳に痛い話を展開する。
話がそれるが、コロナ禍の渦中、端的に疑問に思ったことをツイッターでとある医師に歯向かって意を唱えたが、あっという間に100万インプレッションを超えて炎上した。「よくまあ〇〇さんにそんなこと言えるなあ、、、私には絶対無理」「こいつやば」等。挙句の果て、自分は顔すら知らない他人に容赦なく「君のために薬はつくらないよん、君は要らないもんね」みたいな言葉を浴びせられた。
自然の完全性と、人間のエンパワーメント性のあいだの揺らぎ。このあいだの「空白」に自分は強く関心を抱いている。この空白地帯を解き明かせれば、それは間接的に作業者のためにもなろう。自分はそう強く信じている。
AIとの対話
精神科に定期的に通っている人は、そうでない人に比べてあらゆる風邪や病気に罹りやすいと私は仮説を立てます。それ相応の主張の根拠があります。 ・病は気から 精神的な不安定性は免疫活動を一定程度妨げると考えます。また、就労支援員という立場から、精神が安定しない人は病気にかかりやすいようにみえます。あくまで直感と仮説止まりなので、医原病の観点、腸脳相関の観点、以上の二つから見解をお聞かせください。
ChatGPT:
ご提示の仮説は直感的でありながら、いくつかの科学的な議論と重なる部分があります。ここでは 医原病の観点 と 腸脳相関の観点 から整理してみます。
1. 医原病の観点から
- 定期通院と病気リスク
精神科に定期的に通う人は、そもそも基盤に「精神的な脆弱さ」や「慢性的なストレス」を抱えている場合が多いです。これらは免疫機能の低下と関連づけられるため、風邪や感染症にかかりやすい印象が臨床的に観察されても不思議ではありません。 - 医原病的リスク
医療そのものが病を生む側面も指摘されています。たとえば:- 薬の副作用による免疫機能低下(睡眠の質の悪化、代謝異常、体重増加などを通じて二次的に影響)
- 通院や治療の枠組みが「病気である」という自己同一化を強め、心身の脆弱性を固定化してしまう可能性
- 医療者との関係性が回復志向より依存を助長した場合、生活習慣の改善やセルフケアが後回しになるリスク
この意味では「医療にかかっていること」自体が、直接的にも間接的にも病気のリスク因子となりうる、というのが医原病的な視点です。
2. 腸脳相関の観点から
- 精神状態と腸内環境の双方向作用
近年の研究では「腸脳相関(gut-brain axis)」が注目されています。ストレスやうつ状態は腸内フローラを乱し、それが免疫力低下や炎症反応を強めることが示されています。逆に腸内環境が整えば、精神状態も改善しやすいことが分かっています。 - 精神科通院者の腸内環境のリスク
精神疾患やストレスが強い人は:- 睡眠リズムの乱れ
- 偏った食事(過食や拒食、炭水化物や糖質への依存)
- 運動不足
といった生活習慣上のリスクを抱えやすく、腸内環境を悪化させやすいです。結果として免疫系が弱まり、風邪や感染症、皮膚炎、過敏性腸症候群などの身体症状が出やすくなります。
まとめと問い
したがって、ご提示の仮説は 「精神的不安定 → 免疫低下 → 病気リスク増大」 という直感を、医原病と腸脳相関の双方から補強できます。ただし「精神科通院」それ自体が原因なのではなく、通院が必要なほど精神的に不安定な状態や、薬物・生活習慣・自己認識の変化が複合的に影響しているとみるのが妥当です。
ここで考えるべき問いは:
「医療や支援が本人の免疫力や生活改善をむしろ強める形に転換するためには、どのような介入や関わり方が可能なのか?」
──この問いに答える方向で、支援員としての実践と理論をつなげていけるのではないでしょうか。
ご希望なら、次に「支援員の立場でできる具体的介入」について整理してみますか?
あなた:
介入ではなく、現実を知りたいのです。おそらく科学者、医者はこのようなデータは取りたがらないと思いますが、この仮説の妥当性を、存在するあらゆる世界中のデータを参照してほしいのです。
ChatGPT:
思考時間: 1m 13s
了解です。**「精神科に定期的に通っている=あらゆる風邪や病気にかかりやすいのか」**を、現にある世界のデータでできるだけ冷静に判定します。結論から。
結論(要約)
- 重度の精神疾患(SMI:統合失調症・双極性障害など)の人では、感染症による死亡リスクが有意に高いことは、最新メタ解析でかなり堅い。とくに呼吸器感染(インフルエンザ・肺炎)で3倍前後。ただし「通院」が原因というより、疾患そのもの・併存症・生活要因・治療薬の影響が複合している可能性が高い。 PubMed
- **うつ病など「SMI未満」については、研究間で結論が割れている。大規模コホートでは感染症リスク上昇が示される報告もある一方、ヘルスケア利用や併存症で調整すると「意味のある上昇は見えない」**とする最新分析もある。つまり「軽〜中等度の精神科通院者は何でもかかりやすい」と一般化するのは現時点では難しい。 Oxford Academic+1
- 医原病的(治療起因)な要素は一部で実証的裏付けあり。とくに抗精神病薬(全般)やベンゾ系で肺炎リスク上昇が繰り返し報告され、クロザピンは肺炎・無顆粒球症などを通じて感染リスクに特異的な懸念がある。 PMC+3PubMed+3PubMed+3
- **腸脳相関(gut–brain axis)**は、生物学的妥当性を強く補強するが、人口レベルで「風邪にどれだけ罹りやすくなるか」を定量化する決定的エビデンスではない。ただ、腸内細菌叢—免疫—脳機能の双方向性は近年の総説でほぼ定説化。 Nature+1
もう少し詳しく
1) SMIと感染症アウトカム
- 2024年の系統的レビュー/メタ解析(対象29研究)では、SMIは感染症死亡が約2.7倍、呼吸器感染死亡は約3.3倍に増えると推定。研究の異質性はあるが、方向性は一貫。政策的含意としてインフルエンザ・肺炎球菌ワクチンの優先接種が推奨されるレベルの確度。 PubMed
2) うつ病と「感染に罹りやすいか」
- 上昇ありを示す代表:デンマーク全国レジストリ(約97万人)では、うつ既往者であらゆる感染の発生率比1.61など広範にリスク上昇を報告。呼吸器・肝炎・髄膜炎など多岐にわたる。 ResearchGate
- 上昇は見えにくい/交絡で説明可能を示す代表:英国一次医療データ(CPRD)の最新研究では、急性感染のリスク上昇は医療利用や併存症の差で概ね説明され、意味のある増加は見えないと結論。 PMC
- 先行レビューでは、ストレス・不安・抑うつなど心理社会的要因が急性呼吸器感染(発症・経過)に関連とする報告が多数。ただし測定法や交絡処理はバラつく。 PubMed
読み替え
「うつ=必ず感染しやすい」ではない。重症度・併存症(喫煙、肥満、糖尿病等)、社会経済要因、医療アクセス差、服薬などで見え方が大きく揺れる。
3) 医原病の観点(薬剤・ケア)
- 抗精神病薬と肺炎:系統的レビュー/メタ解析で第一世代・第二世代を問わず肺炎リスク上昇。開始直後や高用量、鎮静・嚥下反射低下・抗コリン作用など機序が想定。 PubMed
- ベンゾジアゼピン/Z薬と肺炎:メタ解析や新規開始者を追うコホートで25〜100%程度のリスク上昇が報告、とくに開始30日以内で顕著。 PubMed+1
- クロザピン:肺炎リスクの上昇と**無顆粒球症(約0.4%)**が確立した懸念。定期的な血球監視が標準。 PMC
ここで重要なのは、「精神科に通っているから」ではなく、特定の薬理作用や投与状況が肺炎などのリスクを押し上げ得るという点。
4) 腸脳相関の観点
- 近年の大部の総説は、腸内細菌叢→免疫(T/B細胞・サイトカイン)→神経系の経路を通じて気分障害・不安などと双方向に影響し得ると整理。機序の妥当性は高いが、「精神科通院者がどれだけ風邪を増やすか」という量的推定の一次証拠は不足。 Nature+1
ここまでの「判定」
- 強い肯定が可能なのは:「SMIでは、とくに呼吸器感染による重篤アウトカム(入院・死亡)が増える」。これは複数の大規模研究と最新メタ解析で裏付けあり。 PubMed
- 一般的・軽症感染(いわゆる“風邪”)まで一律に高いという命題は、現行の世界のデータでは確定できない。母集団や調整の仕方で相反する結果が出ており、通院の有無そのものを因果要因とする証拠は乏しい。 PMC+1
- 医原病的側面は限定的ながら現実味があり、特定の薬剤(抗精神病薬、ベンゾ系、クロザピン)では肺炎リスク上昇が再現されている。 PubMed+2PubMed+2
- 腸脳相関は生物学的な蓋然性を与えるが、疫学的にどの程度リスクが跳ね上がるかは未確定。 Nature+1
付記:よく起こる誤解への注意
- 検査・受診が多いほど「見つかりやすい」=見かけ上のリスク上昇(アセスメント・バイアス)は常につきまとうため、「通院者は罹りやすい」という観察は過大評価になり得ます。最新研究はここを強く調整しており、結果が揺れている背景の一つです。 PMC
必要なら、疾患別(統合失調症・双極・うつ・不安・PTSDなど)×アウトカム別(軽症上気道炎・肺炎入院・感染症死亡)で効果量の表を作って並べます。どの疾患・薬剤・場面で「現実に」どのくらいリスクが上がるか、数値で見える化しましょう。
あなた:
端的にまとめましょう。精神科に通っている人の集団は、そうでない人よりも風邪など、軽症な病気に羅漢しやすいかどうか。500字でお願いします。
ChatGPT:
精神科に通院している人が「風邪などの軽症感染症」にかかりやすいかどうかを、世界の疫学データからみると結論は一枚岩ではありません。重度の精神疾患(統合失調症や双極性障害など)では、肺炎やインフルエンザといった呼吸器感染による入院・死亡リスクが有意に高いことはメタ解析でほぼ確立しています。ただしこれは「軽症の風邪」に限らず重症感染を含むデータです。一方、うつ病や不安症など比較的軽症の通院群では、感染症全般の発生率が高いとする報告(デンマークの全国データなど)と、医療利用の差や併存疾患で説明可能とする報告(英国の大規模コホート)とがあり、明確な結論には至っていません。さらに抗精神病薬やベンゾジアゼピン系薬剤は肺炎リスクを押し上げることが示されており、薬剤性の要因も無視できません。腸脳相関やストレスと免疫の関係から考えても脆弱性はあり得ますが、軽度感染の頻度を一律に高いと断定する根拠は不足しています。つまり、重度疾患では感染リスク増大が確実だが、軽症の風邪に関して「精神科通院者が一般にかかりやすい」とまでは現行データでは言えない、というのが妥当なまとめです。