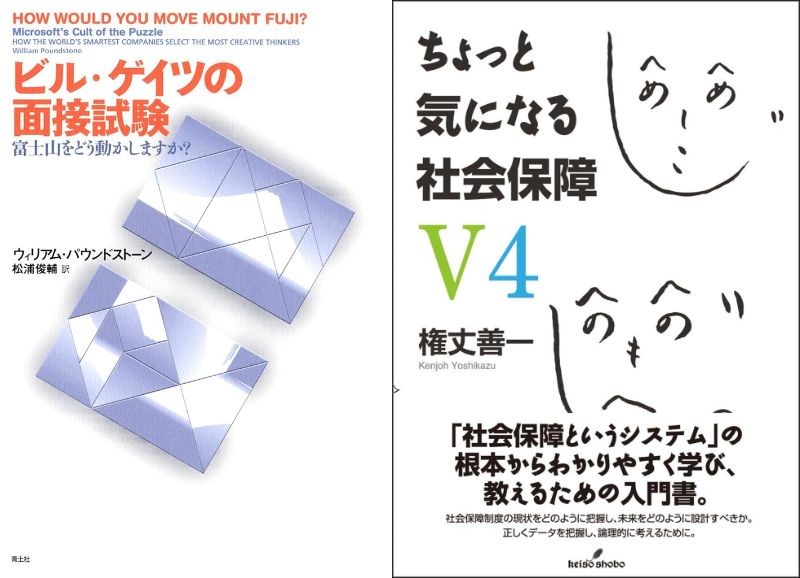■株式会社青土社
公式HP:http://www.seidosha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/seidosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社勁草書房
公式HP:https://www.keisoshobo.co.jp
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/keisoshobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『ちょっと気になる社会保障 V4』
核家族という形態は、果たして私たちにとって本当に自然で安定的なものなのだろうか。投資の世界では「リスクは分散せよ」という鉄則が繰り返し語られる。株式、債券、不動産、現金などを組み合わせ、一つの資産が暴落しても全体が維持できるように設計するのが合理的であるとされる。ところが、私たちの生活の基盤である「家族」についてはどうだろう。独身か、せいぜい核家族か。つまり、非常に局所的で集中したリスクを抱え込む形を「普通」として生きている。稼ぎ手が一人倒れれば共倒れ、介護が必要になれば家族全体が疲弊する。それなのに、投資では分散を解としながら、家族形態では非分散を前提にするという、この奇妙な矛盾はどこから生じているのだろうか。
歴史的に見れば、核家族は人類史の中でごく短い期間にしか存在していない。長らく人間は拡張家族、親族ネットワーク、地域共同体のなかでリスクを分散してきた。子育てや介護、稼ぎ手の不在といった不確実性を、多人数のネットワークで吸収する仕組みがあったのだ。では、なぜ近代以降の社会では核家族化が急速に進んだのか。その原因を探ると、いくつかの層が見えてくる。
まず最大の要因は、産業化と都市化である。都市に人口が集中し、農村からの労働力が流入し、狭い土地に多数の住居を建設する必要が生じた。効率よく収容するためには「夫婦+子ども二人」という小さな単位が最も機動性が高かった。高度経済成長期の日本で典型的なのは、団地やマンションに乱立した「3LDK」という間取りである。これは核家族を前提とした設計であり、大家族や多世代同居はそもそも制度の想定外に置かれていた。住居という物理的制約が、核家族を「標準家庭」として固定化したといえる。短期的には供給の合理性があったのだろうが、長期的に見れば「制度設計のミス」と言わざるを得ない。なぜなら、この住宅モデルが世代間扶養を困難にし、孤独死や子育て孤立といった社会問題を拡大してきたからだ。
次に重要なのは、社会保障制度の存在である。伝統的には、扶養や介護、失業といったリスクを吸収していたのは大家族や地域共同体であった。しかし近代国家は、年金、医療、失業保険といった制度を整備し、その役割を肩代わりした。国家が分散を担うなら、家族は小さくてもよい、という構造が成立したわけだ。核家族の脆弱性は、社会保障という「見えないポートフォリオ」によって補われていた。つまり私たちは、分散を家族の内部ではなく国家に外部化することで、非分散的な家族形態を自然と感じるようになったのである。しかし近年はその社会保障が財政的に揺らぎ、また孤立や孤独死といった問題が浮かび上がっている。そう考えると、核家族の安定性は一時的な錯覚にすぎなかったのではないか。
さらに文化的なバイアスも無視できない。近代化の過程で「大家族=旧弊」「核家族=進歩的」という進歩信仰が広がった。自立した個人が自分の家庭を切り盛りすることが理想とされ、親族や近隣に依存することは後進的だとみなされた。そこには「自由」「プライバシー」「快適さ」を重んじる価値観が強く働いている。確かに大家族には干渉や不自由さがあり、核家族は気楽で便利に見える。しかしその自由は、実のところ外部化された依存に支えられている。保育園、介護施設、社会保障、さらには匿名の労働者によるサービスが不可欠であるにもかかわらず、あたかも「自立している」と錯覚してしまう。この自立幻想こそ、核家族バイアスの中核にあるものだろう。
政策面の影響も見逃せない。戦後の持ち家政策や住宅金融公庫の仕組みは、核家族を前提とした一戸建てや分譲マンションを大量に供給した。都市空間そのものが「小さな家族」を標準とするよう設計されてしまったのだ。さらにメディアは「標準家庭」を繰り返し描き、核家族像を規範として刷り込んできた。『サザエさん』のような大家族は例外的に扱われ、むしろコミカルに提示された。こうして私たちは、多数派の錯覚の中で「核家族こそ自然」と信じるようになった。
このように整理すると、投資におけるリスク分散と家族形態における非分散の矛盾は、主に五つの要因によって生じている。最も強いのは産業化・都市化による物理的圧力であり、次に社会保障制度によるリスク分散の外部化が続く。その後に文化的な個人主義バイアス、住宅・都市政策、そしてメディアによる規範の固定化が位置するだろう。つまり矛盾の正体は、国家や都市が設計した制度的・物理的な環境が、私たちの生き方を局所化させてしまったことにある。
しかしここで問うべきは、未来においてもこの構造が持続可能かどうかである。社会保障が弱体化し、都市もリモートワークや地方分散が進む時代に入れば、従来の力関係は逆転するかもしれない。都市の物理的制約が緩和されれば、文化的なバイアスや住宅設計の方がむしろ強い要因になっていく可能性がある。そうなれば、私たちは改めて「核家族バイアス」を意識的に問い直さなければならないだろう。
本当に安定を望むのであれば、サザエさん的な大家族や、あるいは新しいネットワーク型共同体の方が合理的なのかもしれない。血縁に限らず、友人や隣人と協力し合うコレクティブな生活形態が再び注目されているのも、その必然の表れである。にもかかわらず、私たちはいまだに「核家族こそ普通」という幻想を手放せないでいる。それは進歩への信仰であり、自立の幻想であり、快適さを優先する短期的な合理性の罠にすぎないのではないか。
投資の世界であれば、誰もが「一点集中は危険」と言う。しかし家族の世界では、「一点集中こそ自然」と思い込まされている。このねじれこそが、現代社会の最も深い矛盾ではないだろうか。もし本当にリスクを分散させたいのなら、私たちはどこから手をつけるべきだろう。都市の制度設計を改めるのか、社会保障を再構築するのか、それとも文化的なバイアスを相対化して新しい共同体を構想するのか。あるいはそのすべてが必要なのか。
投資では分散が合理的とされるのに、家族では非分散が「自然」とされる。この矛盾を解きほぐすことは、実は現代社会の根本的な問いなのかもしれない。では、私たちはいま、どちらの方向に舵を切るべきなのだろうか。
・・・・・・
『ビル・ゲイツの面接試験』
200円だったので読んでみることにした。70ページくらいは読んだと思う。どんな本なのか、わくわくしたが、蓋を開けてみるとIQテストの妥当性を科学的に検証するような本だった。ビル・ゲイツは「IQの高い人を雇う」とし、パズルや論理的な力が試される面接試験を導入。結果的にインテル社の創業者などをマイクロソフトは排出したが、果たしてIQテストベースの採用試験は本当に妥当性があるのか?という内容だった。SPIは今でも行われているのだろうか。たしかに膨大な履歴書を抱える人事にとっては、SPIはいい感じのフィルターになるのかもしれない。ただ、相関性はあるにせよ、SPIが高得点だからといって本当にアウトプット(実績)が出るのかというと、微妙なところではないか、と書きたいところなのだけれども、自分のまわりを見ると、やはり論理的な力がある人、推論能力にたけている人はわりといい会社に入って人生がうまくいっているように見えなくもない。
つづく