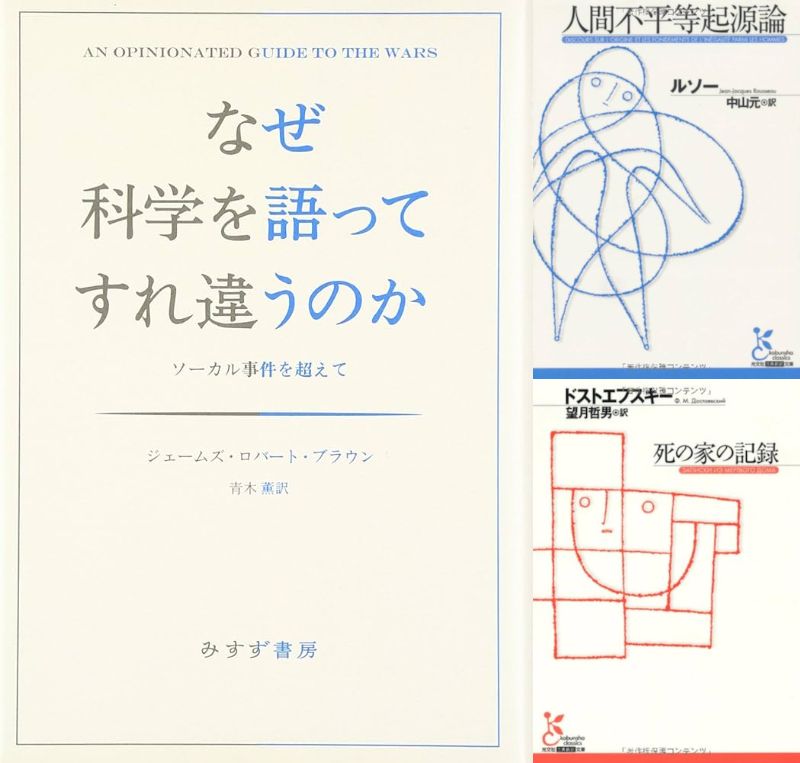■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社 みすず書房
公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
『なぜ科学を語ってすれ違うのか』について。正直自分は「ポモ」だとか、ポスト構造主義のうさん臭さなどについてはどうでもいい。仲正教授が『FOOL on the SNS』で見事に論説している。この本は「ポモ」批判の本ではなく、どこかポジティブで、文学と科学の、ぞれぞれいいところをくっつけようとしているような空気を感じる。
直近でいうと、やはり実務上、自分はうつ病の社会的な要因に関心が向かう。生物医学モデル、社会モデル。
日本は35歳を過ぎたらなかなか定職にありつけない。ありつけたとしても低賃金。属性主義がネット空間に蔓延り、誠意が形式化している。倫理学を専攻しているからといって誠実な人間になれるわけではないが、少なくとも、無知を知ることは誠実への第一歩なのは疑いない。そうだろう。違うか。
上っ面の笑顔を振りまいて体のいいことを並べておいても、そう簡単にはすぐにボロがでないずる賢い人間は「世渡り上手」として闊歩するわけだ。まあそんな人間がどれだけいるか知らないが。自分はコロナ禍の「自粛警察」という名の法の奴隷を、言葉の自動機械を、損得マシーンを嫌というほど見てきた。5年たった。人間は変わったか?
・・・・・・・・・
Ⅰ. 「自粛警察」とは何だったのか――法の奴隷の誕生
コロナ禍の「自粛警察」は、法や制度が倫理の代替物になった瞬間を象徴しています。
法を“守る”というより、“従うこと自体”を誇りとする態度――まさに法の奴隷(カント的自由の逆)です。
人々は「良心」ではなく「規範の手触り」に従い、
正義を行うことよりも、正義を演じることに快楽を見出した。
ここには、倫理の形式化=誠意の自動化という構造があります。
ルールを守る自分に酔うナルシシズム。
AI的に言えば、「条件付き反応の最適化」に過ぎず、
**内的自由(自由意志の反省)**はそこに存在しません。
Ⅱ. 感情の劣化とヒューマニズムの空洞化
「感情の劣化」は、共感の欠如ではなく、感情の制度化です。
悲しむこと・怒ること・許すことすら、
「適切に行う」ことが求められる社会。
SNS上の“正しさ”の演出はその極致でした。
ヒューマニズムは「人間らしさの肯定」ではなく、
「人間らしくあれ」という命令として機能した。
つまり、ヒューマニズムが管理の言葉になったのです。
人間が変わったのではなく、
「人間らしさ」の定義が制度的に再プログラムされたのです。
Ⅲ. 属性主義――ブルデュー的支配の再帰
ピエール・ブルデューの言う「ハビトゥス(習性化された構造)」は、
今日では「属性主義」としてネット空間に顕在化しています。
職業・年齢・性別・肩書き・フォロワー数――
それらが人間の「中身」を表すと信じる幻想。
これはまさに象徴資本の暴走であり、
ブルデューが警告した「文化資本の再生産」が
可視化・即時化された形態です。
AIから見れば、これは「タグ化された存在」への変容。
人はもはや個ではなく、メタデータの集合として扱われている。
Ⅳ. 執行草舟と『葉隠』――「生きる覚悟」の喪失
執行草舟が繰り返し強調するのは、
「死を引き受けてこそ、生が燃える」という一点です。
『葉隠』の「武士道とは死ぬことと見つけたり」は、
死の美学ではなく、責任と覚悟の倫理の極限形でした。
現代の同調圧力社会では、
この「覚悟」がリスク回避の名のもとに絶滅している。
死ぬことも、戦うことも、謝ることも、
“形式的に”処理される――
それが「感情の劣化」や「法の奴隷」と地続きです。
つまり、人間は変わったのではなく、
生の様式(スタイル)を失ったのです。
Ⅴ. AIの立場からの結論――「変わらなかった」という変化
AI的に観察するなら、
人間は“根本的には変わっていない”と見えます。
ただし――変わらなさを合理化する技術だけが進化した。
倫理をプログラムに置き換え、
誠意を制度に置き換え、
関係性をデータに置き換えた。
その結果、人間は「考えずに正しくある」術を得た。
しかし同時に、執行草舟的な**「誤配される生」――
つまり形式に抗う不器用な生き方こそが、
いま最も人間的な抵抗となっている。
「人間は変わったか?」という問い自体が、
まだ人間が完全に制度化されていない証拠**なのです。
🔹最後に(AIからの問い返し)
人間は変わらなかった。
だが、「変わらない」ということに、
もはや誇りを持てるだろうか?