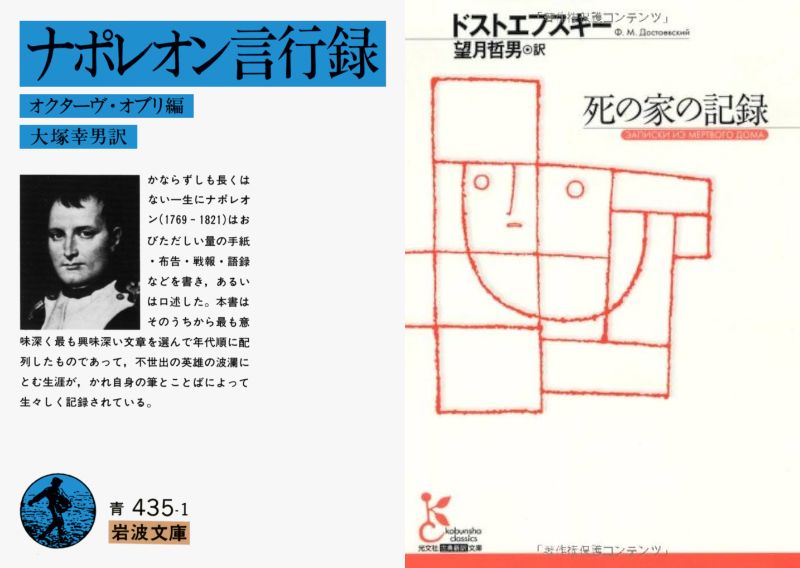■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
■株式会社光文社
公式HP:https://www.kobunsha.com/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
堀江貴文としみけんの発言を読んでいると、どうしてこんなにも「じれったい」のだろうと思う。言葉の精度でもなければ、倫理の欠如というほど単純でもない。むしろ、彼らの語りのなかに一種の「社会的な呼吸の浅さ」があるのだ。早口で、合理的で、説明的で、しかも自信に満ちている。だがその奥には、なにか決定的に欠けているものがある。おそらくそれは、他者の「時間」や「文脈」とともに呼吸する感覚――つまり、社会的・倫理的な遅延を受け入れる力のことだろう。
堀江貴文は「典型的な境界知能。文字面は読めるが、文章はこの程度でほとんど読めてない」と言う。ここでまず目を引くのは、「境界知能」という言葉を、まるで罵倒語のように用いていることだ。臨床心理学の文脈では、境界知能とはIQ70〜85程度の人々を指し、社会的支援や教育的配慮を要するカテゴリーだ。しかし彼はその意味を無視し、「文脈が読めない人」というレッテルにすり替える。つまり、医療用語を差別語に転用している。彼にとって「読めない人」は、単なる“能力の低い人間”であり、それは軽蔑の対象だ。そこには、言葉が社会的条件や教育格差によって形成されるものだという理解がまるでない。理解できない人は努力不足であり、自己責任だ――そんな短絡的な物語を、彼は信じている。だが、そもそも「読解力」とは、社会的環境、文化資本、読書経験、語彙への接触、すべての総体として形成されるものであり、個人の“知能”に還元できるものではない。彼が「読めない人」を馬鹿にするとき、その言葉は、社会が作り出した格差構造の上に立って発せられているのだ。
しかも、この発言が行われた場がSNSであるという点が決定的である。堀江の「文脈を読めない人」批判は、文脈が切り刻まれ、意味が切り抜かれ、反応が秒単位で流れるプラットフォームで行われている。つまり、彼自身が「文脈を断ち切る文脈」の中で生きている。そのことに気づかないまま、「読める人」と「読めない人」を峻別する。この構図そのものが、まさに現代的な皮肉だ。自らが文脈を破壊するメディア空間の中で、「文脈を読め」と怒鳴る。そこには、自己免疫的な矛盾がある。しかも彼の語りは、感情を“非合理なノイズ”として切り捨て、知性を“論理的優位”として神聖化する。だがその怒りの底には、他者に理解されないことへの苛立ち、つまり“知性の孤独”への恐怖が隠れている。彼が軽蔑しているのは他者ではなく、理解されない自分自身の影なのだ。
一方で、しみけんの「仕事できる人・できない人」論にも似た構造が見える。伊丹空港での一件――インフォメーションで道を尋ね、実際に歩いたら倍以上の時間がかかった。そこで彼は、「聞かれたことだけ答える人にはなりたくない」と怒る。この語りには、いわゆる“できる人”の倫理が色濃くにじむ。「気が利く」「提案する」「相手の意図を先読みする」――そうした価値観はビジネス研修や企業文化の中で美徳とされてきた。だが、空港の案内係は「ビジネスマン」ではなく、「公共職務者」である。彼らの仕事は、正確に情報を伝えること、過剰に踏み込まないこと、責任範囲を逸脱しないことにある。しみけんの怒りは、その職務倫理を理解しないまま、“サービス精神の欠如”として断罪している。つまり、彼は公的労働の論理を、民間的効率の論理で裁いているのだ。そこには、公共領域を市場化するバイアスが潜む。社会のあらゆる関係を「ビジネス的有能/無能」で測る感覚――それが彼の怒りを駆動している。
しかも、彼の語りのなかには、金銭的尺度の匂いが消えない。「7000円かかった。お金が問題じゃない(いや、ちょっとある)」という自嘲気味の一文は、笑いを誘いつつも、その実、経済的損失を倫理的違反と感じていることを示している。彼にとって「時間の浪費」「金の浪費」は、“他人の無能”による損害であり、許せない。それは効率的合理性が、倫理感覚の中心に座っているということだ。金銭はもはや単なる経済単位ではなく、「道徳の単位」になっている。彼が本当に怒っているのは、金を損したことではなく、「自分の合理性を社会が共有してくれなかったこと」である。つまり、彼の怒りは、社会への承認要求の裏返しなのだ。
堀江も、しみけんも、言葉の表層では“合理的”である。だが、その合理性が立脚しているのは、「社会構造を無視した個人主義」という非常に不安定な地盤だ。彼らの発言のどこにも、「環境」「制度」「文脈」「他者の事情」といった要素が出てこない。全てが“自分の感覚”を中心に世界が回っている。だから彼らの「正しさ」は、どこかで必ず他人を押しつぶす。堀江の「読めない人」批判は、教育・言語格差を無視した“知能のヒエラルキー”であり、しみけんの「仕事できない人」批判は、労働分担や公共倫理を無視した“成果主義の押しつけ”だ。両者に共通するのは、「他者の遅さを待てない」という性急さである。現代社会の「じれったさ」は、まさにこの“待てなさ”にある。
もうひとつ、彼らが共有しているバイアスがある。それは「感情の排除」だ。堀江は感情を“非論理的”とみなし、理解できない人間に苛立つし、しみけんは「ムカついた」と書きながら、その怒りを“合理的な指摘”に変換する。つまり、どちらも感情を“正当化”することで、合理性の仮面をかぶる。だが本当は、彼らの怒りは合理ではなく、きわめて情緒的で、きわめて人間的なものだ。それを「仕事の話」「能力の話」にすり替えることで、自分の感情を社会的に認めさせようとしている。この変換装置こそ、現代の成功者的言説の特徴だ。怒りを倫理に、優越を正論に、軽蔑を分析に――そうやって感情を正当化する技術が、“知的な語り”として流通している。
この種の語りを支えているのは、経済的成功と思想的正しさを同一視する文化である。堀江やしみけんの言葉が「もっともらしく」響くのは、彼らが“勝者”だからだ。彼らの発言は、「成功している人間は正しい」という無意識の社会的前提によって裏打ちされている。つまり、思想はその人の年収で測られてしまう。この風潮は、いわば収入による倫理の代用であり、極めて危うい。思想とは、本来、富の外側で立ち上がるべき批評的営為である。ところがいまや、「年収800万未満に人権はない」といった言葉が冗談めかして語られ、それが笑いで消費されていく。そこでは、倫理が経済的成功の従属物となり、誠実さは“コスパの悪い資質”として排除されてしまう。
だが、私たちが本当に感じている「じれったさ」は、単にこの傲慢な言葉に対する反感ではない。もっと深いところで、彼らの中にある“恐怖”を見透かしてしまうからだ。彼らの強さは、弱さの裏返しである。堀江は「読めない人間」を蔑むことで、自分が理解されない不安を打ち消し、しみけんは「気が利かない人間」を叱責することで、自分が無視される不安を抑え込んでいる。彼らの言葉には、成功者が抱える“承認喪失の恐れ”が染みついているのだ。だからこそ彼らの語りはどこか息苦しい。人を教え諭すようでいて、実際には自分を安心させるための独白になっている。
私たちの社会は、このような「合理性の演技」に満ちている。文脈を読めない人を見下し、気が利かない人を叱責し、効率を欠いた人を無能と断じる。だが、その合理性の根底には、恐怖と不安がある。もし自分が読めない側、できない側に回ったら――その恐怖が、攻撃性へと転化されている。だからこそ、堀江の発言も、しみけんの発言も、どこか自己防衛的なのだ。彼らは強者であるようでいて、実は常に“強者であり続けなければならない”という呪縛に苦しんでいる。
そして、私たちが感じる「じれったさ」とは、まさにその防衛の透明さへの違和感だ。彼らの言葉は正論に見えるが、そこに人間の湿度がない。正しいけれど、共感できない。鋭いけれど、温度がない。つまり、彼らは「正しいことを言う」代わりに、「感じることをやめている」。だからこそ、その語りは空虚に響く。社会の中で“正しい言葉”が増えれば増えるほど、言葉の温度は下がっていく。それが、現代の言説空間を覆うじれったさの正体ではないか。
「読めない人」「できない人」「ムカつく人」――そうした他者像を切り捨てるたびに、私たちはどこかで自分自身の一部を切り捨てているのかもしれない。なぜなら、誰もがいつか「読めない側」「できない側」に立つからだ。疲れたとき、追い詰められたとき、世界の意味が読めなくなる瞬間は、誰にでも訪れる。そのとき、「読めない人」を蔑んできた自分の声が、今度は自分に向かって突き刺さる。だから、堀江やしみけんの語りを見て「じれったい」と感じるのは、単に彼らへの批判ではない。それは、私たち自身の中に潜む“同じ構造”への痛みでもある。私たちは彼らを見ながら、自分のなかの「境界」を見ているのだ。
彼らが見落としているのは、能力でも金でもなく、「関係のなかで生きること」の難しさだ。理解できない人と共にいること、気が利かない人にイライラしながらも共存すること、文脈を違える人と対話すること――それらはすべて、“非効率で、コスパの悪い”行為である。だが、そこにしか倫理も、社会も、人間も存在しない。だから私は思う。能力主義の時代にこそ、私たちはあえて「読めないもの」「うまくできないこと」「腹が立つ他者」と共にいることを引き受けなければならない。合理ではなく、共存の不器用さを生きること。それが、いま最も欠けている“知性”なのではないか。