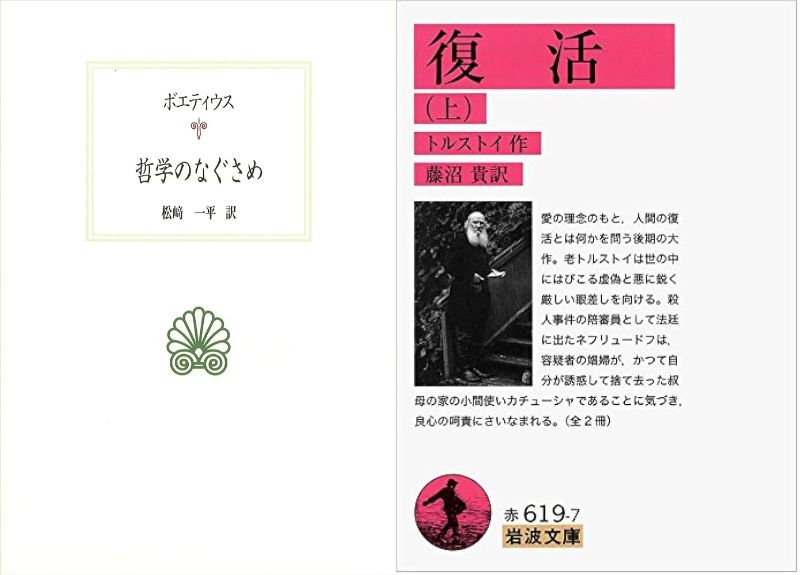■一般社団法人京都大学学術出版会
公式HP:https://www.kyoto-up.or.jp/
公式X(旧 Twitter ):https://x.com/KyotoUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
私たちは、契約書を「安心の装置」として信じすぎてきた。署名と押印が、将来の不幸に対する保険であり、対立の回避装置であり、社会的信頼のしるしであると。だが、私が身をもって学んだのは、契約書こそが不幸の入口になり得るという事実だ。そこに「役務提供」という、誰にとっても都合よく読める言葉が置かれるだけで、現実は条文に吸い込まれ、生活は不可逆に縛られる。契約は制度であり、制度は人を守るふりをして、人の時間と尊厳を徴収する。だからこそ私は問いたい――制度上、可逆性をどう確保するか、と。
可逆性功利主義とは、社会の厚生を「やり直せる力」によって測り直す立場である。効率や迅速さを称揚する前に、間違いが起きたときの撤回・修復・救済の容易さを主要な指標とする。これは気分や倫理の美談ではない。実務と設計の問題だ。なぜなら、現代の被害の多くは、悪意よりも「不可逆の形」の中に埋め込まれているからだ。前払一括、包括的委任、抽象的成果、恣意的検収――どれも、その瞬間は合理的に見える。しかし、失敗のコストが一方に濃縮される設計は、やがて弱者に沈む。粘り強く戦える者は少数であり、たいていは「払って終わらせる」ほうが精神衛生に良い。だから統計上は静かに被害が続く。これは個々の取引の問題を超えて、公共の厚生をむしばむ。
では、契約という制度に、どう可逆性を注ぎ込むか。第一に、言葉のレベルで抽象を制限する。抽象は専門家の能力を示す飾りではない。抽象は、責任の逃げ道になる。契約文は詩ではなく、検査可能な命令であるべきだ。目的、成果、検収、返金、紛争処理――この五つが一ページで読め、外部の第三者が同じ結論に到達できる程度に具体化されていなければならない。「役務提供」は、具体的行為と測定可能な出力に分解されるべきだ。抽象を削ることは、自由の削減ではない。むしろ、後日の自由――すなわち是正の自由――を増やす。
第二に、時間の構造を再設計する。不可逆はしばしば時間配列の問題だ。前払一括や一気呵成の納品は、最初にすべてのリスクを買わせる。可逆性功利主義は時間を細かく刻む。短い試行期間、段階的検収、留保金のエスクロー、比例返金の数式。これらは弱者のための特権ではない。誠実な事業者にとっても、期待値のばらつきを抑える保険である。もし結果が伴えば、段階を進め、留保を解放すればよい。失敗が起きれば、小さく訂正する。経済とは試行の連鎖であり、試行には巻き戻しが必要だ。
第三に、記録の公共性を導入する。取引は当事者の私事であっても、是正の条件は公共に属する。要件定義、変更合意、検収の根拠は、後から第三者が追跡できる形で残されるべきだ。これは監視ではない。可視性こそ可逆性の土台である。記録がなければ、救済は常に「言った/言わない」の戦いになり、強者の弁舌が勝つ。記録は弱者の武器であり、誠実な事業者の盾でもある。
第四に、行政の位置づけを「最後の救済」から「最初の既定」に変更する。行政介入がようやく和解を導いたという経験は、多くの当事者に共通している。しかし、その到来は遅すぎる。契約の紛争条項には、中立機関の早期調停をデフォルトとして埋め込み、費用配分と期限を先に固定する。可逆性の制度設計は、紛争が「起きてから」ではなく、「起きる前」から始める。行政の役割は、個別事案の裁定者だけでなく、可逆設計の標準化者であるべきだ。
第五に、不可逆性に価格をつける。高額の前受けや包括的な免責、過度な解約違約金といった不可逆の要素には、相応のコスト負担(供託、保険、割引、説明責任)が伴うべきだ。市場は価格に敏感であり、不可逆を高くつくようにすれば、可逆が競争力を持つ。ここでいう「課税」は道徳的罰ではない。外部不経済の内部化である。不可逆の危険は社会に波及するから、その分の保全コストを制度的に前取りする。
第六に、可逆性を測る。測れないものは、やがて軽んじられる。紛争の回避率、是正までの平均日数、返金の比例性、当事者の心理的負担の代理指標――これらを束ねて可逆性指数(Reversibility Index)をつくり、契約形態や業界ごとに公開する。数値は万能ではないが、沈黙よりはましだ。数字は議論の入口を開く。入口があれば、人は戻って来られる。
この宣言は、契約を否定するものではない。むしろ、契約を生かすための告発である。契約は約束の形式だが、約束は未来の不確実性の上に立つ。形式が未来を固定しすぎるとき、約束は人間から自由を奪う。自由とは、軌道修正の可能性である。つまり、契約は可逆であるほど、人間に似る。可逆な制度は、失敗を学習へ変える。不可逆な制度は、失敗を沈黙へ変える。どちらが豊かな社会を育てるかは、明らかだ。
私は自分の不始末を免罪するつもりはない。いたらなさが招いた失敗だった。それでもなお、個人の成熟の遅れが、制度的な不可逆性によって過剰に罰せられる世界は、正義から遠い。成熟の差を吸収するために、制度がある。制度が「粘れる人」だけを救うのなら、それは制度ではなく賭場だ。私たちは賭場ではなく、学びの場を必要としている。
可逆性功利主義は、最終的に一つの問いに帰る。私たちは、いつでも説明でき、いつでも戻せる社会を、面倒くさいと切り捨てるのか、それとも文明のコストとして引き受けるのか。面倒は確かに増える。だが、面倒を先に払うほど、後の悲劇は小さくなる。私は、悲劇を避けるための面倒に賛成する。契約書は、やり直し可能性の設計図であるべきだ。抽象の優雅さより、撤回の優雅さを。スピードの快感より、修復の穏やかさを。不可逆の効率は、短期の勝利にすぎない。長期にわたる共同の厚生は、可逆の軌道修正によってしか育たない。
この宣言に賛同する者は、まず自分の契約から始めよう。五つの要件(目的・成果・検収・返金・紛争)が一ページで読めるか。時間は刻まれているか。記録は第三者に読めるか。行政の早期介入のレールは敷かれているか。不可逆の価格は支払っているか。もし一つでも「いいえ」があるなら、私たちはまだ学びの途中だ。学びの途中でいられること――それこそが、可逆であることの幸福なのだ。