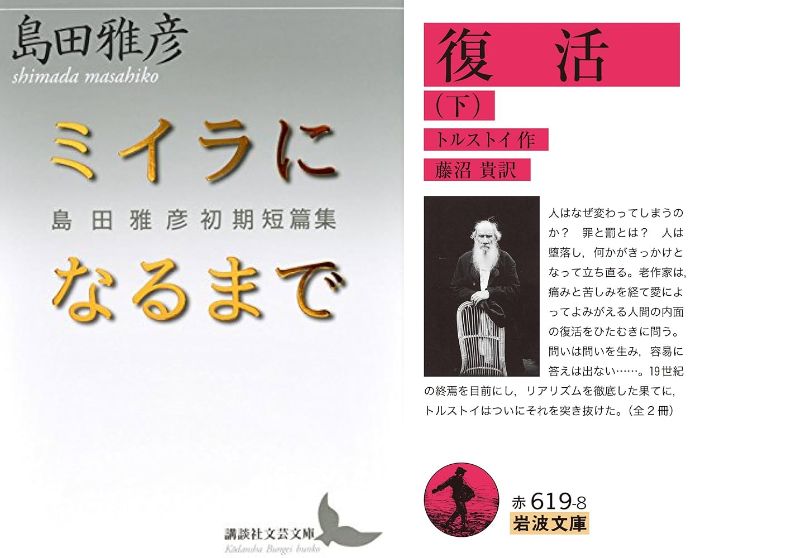■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
■株式会社講談社
公式HP:https://www.kodansha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
今日は、トルストイ『復活 下』のつづきを読み進めつつ、島田雅彦『ミイラになるまで』を開いた一日だったのだけれど、読後に残ったのは感動よりも、むしろ「響かなかった」という感触の方だった。なかでも「断食少年」は最後まできちんと読み切ったにもかかわらず、ページを閉じて最初に出てきた言葉が、どう取り繕っても「……いや、やっぱり響きませんでした」だった。これは作品に対する批評というより、自分の身体と心の側の反応の問題として書き留めておきたい。「ああ、こういう発想か」と部分的に「なるほど」と思った箇所もあったのに、全体としては、どうにも、ほんとうに、響きませんでした。
「断食少年」のアイデアそのものは、なるほど面白い。ハンストという行為、本来は政治的な圧力であり、誰かに「責任」を取らせようとするための究極の手段としての「食べないこと」。それと、「本当に食べ物が嫌いで仕方がない人」という、身体の嗜好や感覚のレベルで「食べない」方に傾いてしまっている人間が組み合わさると、そこにはどんな化学反応が起きるのか。その設定のねじれ方は、たしかに「おお、そう来るか」と思わせるところがあった。ハンストという行為がもつ「他者への訴え」と、食べ物嫌いがもつ「自分の身体への嫌悪」が、一本の線上にまとめられるとき、そこには倫理の座標軸が少しずれるような不気味さがある。
なのに、だ。それでもなお、読んでいるあいだの私は、どこか遠くから眺めている感じを拭えなかった。観念としてはわかる。発想としては納得もする。だが、その「わかった」「納得した」が、胸の奥の柔らかいところに落ちてこない。物語の中で、登場人物たちが何かを賭けている気配が、私の身体のほうに伝わってこない。読み終わってみても、心拍数はほとんど上がらず、汗もかかない。ページを閉じる手つきも、妙に乾いている。そういう意味で、これは本当に、見事なまでに響きませんでした。
ここまで響かないと、もはや「自分の感受性の側に問題があるのでは」という気分になってくる。作品の質がどうこうというより、「私はいま、何をもってして作品と『共鳴した』と感じるのか」が、うまくつかめなくなってくるのだ。たとえば、同じ「身体」と「罪」や「負い目」を扱っているという点では、今日少し読み進めたトルストイ『復活 下』の世界のほうが、よほど生々しく迫ってくる。そこに描かれるのは、禁欲でも断食でもなく、食べること・欲すること・恥じること・それでも生きてしまうことの、どうしようもない混沌だ。聖人のように一気に高みに飛び上がるのではなく、泥を踏みしめながら、しかしどこかへ向かわずにはいられない魂の動きがある。そういうものは、読みながら自然に、じわじわと身体の奥のほうに沈んでくる。
それに比べると、「断食少年」の世界は、どこか私には整いすぎて見えたのかもしれない。設定のねじれはある。象徴的な構図もある。だが、そのねじれを感情のレベルで受け止めるための「余白」や「ガタつき」のようなものが、私にはあまり感じられなかった。ピシッと計算された比喩のように、きれいにまとまりすぎている印象さえあった。私の側の嗜好として、多少いびつで、収まりの悪い人物や場面のほうに惹かれてしまうところがあるのだろう。倫理的にも感情的にも「これでいいのだ」と言い切れない、その中途半端さにこそ、どうしようもなく共感してしまうところがある。
「響く/響かない」という言い方は、よく考えるとずいぶん乱暴でもある。では何が響くのかと問われると、きちんと言語化できているわけではないからだ。たとえば、トルストイの人物たちだって、現代の感覚からすると「いやいや、そこまで極端に振れる?」と思う場面がいくつもある。それでも彼らの言動や心の揺れは、どこかで私の日常と地続きだと感じてしまう。たとえ極端に誇張されていても、「ああ、人間って、こういうふうに自分を正当化したくなったり、急に全部を捨てたくなったりするよね」という、恥ずかしい共通分母が透けて見える。一方で、「断食少年」を読んでいるあいだの私は、そこに自分を重ね合わせる足場をうまく見つけられなかった。
ただ、だからといって「響かなかった」作品を切り捨ててしまうのも、なんだかもったいない気がしている。響かなかった、だからこそ、いまの自分の輪郭が少しだけ浮かび上がることもあるからだ。ハンストと食べ物嫌いの組み合わせに「なるほど」とだけ思って終わってしまった自分は、きっと「食べないこと」に人生を賭けたことのない人間なのだろう。食べること、食べないことが、生の根源的な選択として迫ってきた経験を持たない。だから、そこに物語としての切実さを感じることができなかった。これは作品への批判というより、自分の生き方の貧しさの一端なのかもしれない。
一方で、『復活』を読み進めていると、今度は逆に「そんなに自分を責め続けなくてもいいのでは」と言いたくなる瞬間がある。主人公が、自分の過去の罪や怠慢を思い出しては、何度も何度も心の中で糾弾し続けるあの反復。そこには、自己懺悔がある種の快楽と結びついてしまう危うさも見える。だが、その過剰さ込みで、私は彼のぐるぐる回る思考に、つい付き合ってしまう。あまりに行き過ぎた反省は、たしかに滑稽で、時に鬱陶しい。それでも、その鬱陶しさの中に、「ああ、やっぱり私もこうやって堂々巡りをしているな」と思わされるリアリティがある。
今日の読書をふりかえってみると、一冊(というか一編)は明らかに「刺さらなかった」のに、もう一方はじわじわと効いてくる。その差は作品の出来不出来だけでは説明できない。むしろ、その日の自分の体調や気分、抱えている悩みや関心との相性のほうが、大きく影響しているように思う。もし私が、食べることや食べないことをめぐる切実な葛藤のさなかにいたなら、「断食少年」は全く別の読み方を迫ってきただろう。逆に、もし「罪」とか「救済」とかいうテーマから距離を置きたい時期だったなら、『復活』の説教くささには耐えられなかったかもしれない。そう考えると、「響きませんでした」という一言の裏には、その日の自分のコンディションと、作品側の波長のすれ違いが折り重なっているのだろう。
それでも、あえて今日は「響きませんでした」を強調して書き残しておきたい。なぜなら、読書日記というのは、本来「よかった本」だけの栄誉の殿堂ではなく、「よくわからなかった本」「別にピンとこなかった本」も含めて、その日の自分の感受性の記録であるはずだからだ。私が今日、島田雅彦の短編に対して覚えたのは、「つまらない」という即物的な評価よりもむしろ、「自分はこの種類のねじれ方には共鳴しないらしい」という、少し冷静な自己観察に近い感触だった。観念のレベルではなるほどと思いながら、心が一ミリも動かない感じ。そこにこそ、「読書日記アプローチ」で拾い上げたい微妙なズレがある。
読書には「人生を変えた一冊」のようなドラマチックな出会いもたしかにあるけれど、実際の読書生活の大部分は、「別に人生は変わらなかった一冊たち」によって埋め尽くされている。今日の「響きませんでした」も、その大多数の側に属しているのだと思う。しかし、そうした無数の「響かなかった読書」の堆積が、結果として自分の好みや思考の癖、感情の傾き方をじわじわと形づくっていくのだとしたらどうだろうか。あの日読んでピクリともしなかった一行が、数年後、別の文脈で突然思い出され、そのとき初めて遅れて響く、ということもあるかもしれない。
そう考えると、「響きませんでした」と書くこと自体も、決して作品を切り捨てる宣告ではなく、むしろ「今の私はここまでです」と自分の現在地を告げる、小さなメモのようなものなのかもしれない。今日の私は、「断食少年」の化学反応に立ち会いながらも、その熱をほとんど感じ取ることができなかった。代わりに、『復活』の泥くさい懺悔と迷走に、妙な親近感を覚えていた。では、この偏った共鳴のあり方そのものを、これから先の読書の中で、どのように引き受けていくことになるのだろうか。