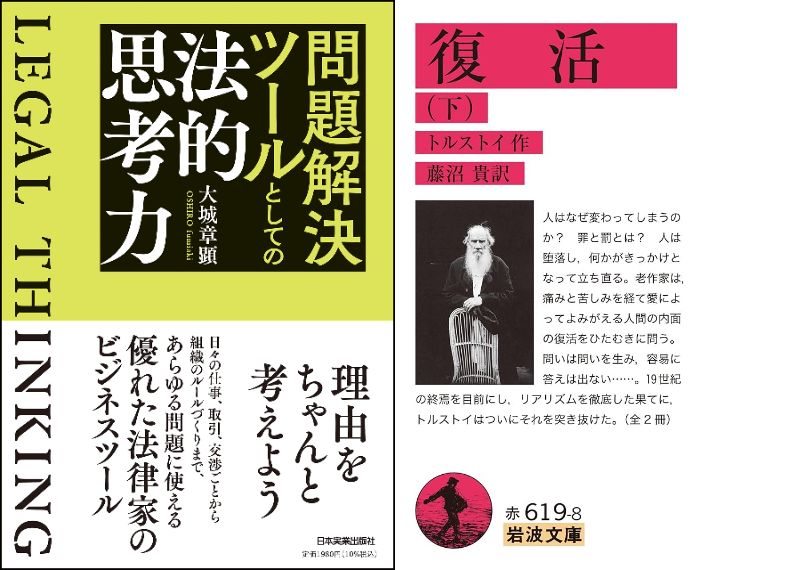■株式会社日本実業出版社
公式HP:https://www.njg.co.jp/company/
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
感想・日記
『問題解決ツールとしての法的思考力』を読み終えた。ページを閉じたあと、いちばん最初に浮かんだ感想は、「ああ、自分はようやく『知識』と『知恵』の違いを、法という入り口から教わったのだな」というものだった。
法律の本を読んでいるとき、人はつい「どれだけ条文を暗記したか」「判例の名前をいくつ言えるか」という方向に意識を引っ張られがちだ。試験勉強をくぐってきた人間ほど、その誘惑は強い。だが本書は、その方向に安住してしまった瞬間に、法はただの「情報の山」に堕してしまうのだと、何度も釘を刺してくる。どれだけ六法を積み上げても、それが「問題に向き合うための道具」になっていなければ、知性のかけらもない、と。
自分の主観でいえば、知識とは、ただそこに積み重ねられた情報の山のようなものだ。質問されれば答えられる、クイズ番組でボタンを早押しできる、そういう意味での強さはある。だが、それは「答えがもう用意されている世界」の中でしか輝かない。一方、知恵とは、与えられた情報が、ある種の地図の上で組み替えられていくイメージに近い。背景や前提、文脈、利害関係、価値の対立といったものを踏まえながら、「この状況では、どの道を選ぶことが妥当なのか」を考えるための力だ。
本書は、法律の世界においても、この両者の差は決定的なのだと、静かに、しかし容赦なく突きつけてくる。条文を知っているだけでは、それは単に「クイズ王」でしかない、と。クイズ王はたしかにすごい。だが、答えのない問題に向き合う場、つまり現実の生活や仕事、紛争や葛藤の現場において、単純な知識の量はあまり役に立たない。出題者の用意した「正解」をいかに早く取り出すか、というゲームと、そもそも正解が一つに定まらない状況で筋の通った解決策を構築することとは、まったく別物だからだ。
この本の面白さは、法律を「暗記の対象」から「問題解決の道具」へと引きずり出してくれるところにある。たとえば、自由、平等、公正、信義則、権力濫用、公序良俗といったキーワードが次々に登場するのだが、それらは単なる用語集ではなく、「物事をどう捉えるか」という視点のセットとして提示される。自由という言葉一つ取っても、誰の自由なのか、どこまでの自由なのか、その自由は他者の権利や安全とどう調整されるべきなのか――こうした問いを抜きにして「自由は大事だ」と唱えても、空々しいスローガンにしかならない。そのことを、本書は丁寧な事例を通じて思い出させてくれる。
読んでいて、とくに心に残ったのは、「背景を知らないまま学ぶこと」と「背景を知ってから学ぶこと」の差についての感覚が、じわじわと自分の中で立体化していったことだ。背景を知らずに学ぶ知識は、たしかにテストの点数にはつながる。だが、それは「教科書と模試の世界」という、ごく限定された球場でしかスイングできないバッターに似ている。ど真ん中にストレートを投げてもらえれば軽快に打てるが、少しでも変化球を投げられると、途端にバットが空を切る。
これに対して、背景を知ってから学ぶ知識は、そもそも「どういう試合が行われているのか」「どんな投手がいて、どんな作戦がありうるのか」といった、ゲーム全体の構造から把握しようとする。そうやって身についた知識は、カーブが来ようがシンカーが来ようが、とりあえずボールの軌道を見極めようとする目を鍛えてくれる。ときには、たまたま変化球にうまくバットが当たって、思いがけないホームランが飛び出すこともあるだろう。そういう「試合全体と結びついた学び」を、本書から少し分けてもらったような感覚がある。
法律の勉強というと、「六法全書を抱えて条文を暗記する」というイメージが先に立つが、本書が描き出すのはむしろ逆だ。先にあるのは、現実の「もめごと」や「困りごと」であり、その状況のどこに自由や平等、公正、信義則、公序良俗といった尺度が絡んでいるのかを見極める作業である。条文はそのあとで、「じゃあ、この価値の対立を調整する枠組みとして、法はどんな答えを用意したのか」を確認するために参照される。法律が問題解決のツールだというのは、まさにそういう意味なのだろう。
この構造は、ここしばらく自分が考え続けている「可逆性功利主義」の話ともどこかで響き合っている。知識を集めることだけに満足してしまうのは、どこかで「不可逆性」に安住してしまうことでもある。「自分はこれだけ知っている」という事実は、ある種の自己完結した快感を与えてくれるが、その知識を使って現実の不均衡や非対称性に介入する覚悟とは、必ずしも結びつかない。クイズ王的な知識のあり方は、安全なスタジオの中でだけ完結する。
しかし現実の紛争やトラブルは、スタジオの外で起きる。結婚相談所との契約トラブルにしても、サブスクの解約をめぐるやり取りにしても、そこでは「答えの載っていない問題」に対して、自分なりに筋の通った主張を構成しなければならない。そしてそのとき、ただの知識として覚えた条文は、たちまち心もとないものになる。むしろ、「この制度は、誰にとってどんな不可逆性をもたらしているのか」「ここに可逆性を少しでも埋め込むとしたら、どこから手をつけるべきか」といった問いを立てるための視点こそが、決定的に重要になってくる。
本書を読みながら、自分がまさにその入口に立っているのだと感じた。自由や平等といった概念も、信義則や公序良俗といった言葉も、これまではどこか「遠くの法律用語」として眺めていたところがあった。だが、役務提供をめぐるトラブルや、インフルエンサーと非インフルエンサーの非対称性に目を向けてみると、それらの概念は急に身近な尺度として立ち上がってくる。「この契約は、一見自由な合意に見えるけれど、情報量の非対称性や選択肢の少なさを踏まえても、なお『自由な自己決定』と言えるのか?」――こうした問い方は、もはや抽象的な哲学の話ではない。
知識として法律を知ることはたやすい。ネットを検索すれば、条文も解説も、いくらでも出てくる。だが、「問題解決ツールとしての法的思考」とは、その情報の海の中から、いま自分が立っている場所にとって本当に意味のある問いを組み立てることなのだろう。どの条文を持ち出すかは、その問いの結果として決まる。条文そのものが先にあるのではなく、「どんな価値の衝突がここにあるのか」「誰のどの利益が危うくなっているのか」を見極めることが先なのだ。
そう考えると、この本を読んで感じた「知識と知恵の違い」は、単なる感想ではなく、自分自身の学び方そのものに対する問いかけでもある。これまで自分は、どれだけ「背景を知らないまま学ぶ」側に偏っていたのだろうか。どこかで、テストで点数が取れたり、知識を披露できたりすれば、それで十分だと安易に安心してこなかったか。変化球が来るたびに空振りして、そのたびに「こんな球を投げる方が悪い」と心のどこかで言い訳してこなかったか。
本書は、そうした自分の癖を静かになぞりながら、「背景から学ぶ」方向へと、少しだけ舵を切らせてくれたように思う。法律の勉強をするにしても、まずは「この制度は誰のためのものなのか」「どのような歴史的経緯でこのルールができたのか」「今の社会でどんな機能を果たしているのか」といった問いから入ってみる。そのうえで初めて、条文の一つひとつが、単なる文字列ではなく、生きた選択の跡として読めるようになるのかもしれない。
同じタイミングで読み進めているトルストイ『復活 下』の方は、物語がゆっくりと進行している。こちらは、法の世界とは別のかたちで、「背景を知らずに裁くこと」と「背景を知ってから判断すること」の差を描き出しているようにも思える。人間の過去や環境、貧しさや孤独、といったものを知らないまま、「この行為は悪だ」と断罪することは、たやすい。だが、その安易な断罪は、しばしば取り返しのつかない不可逆性をもたらす。トルストイの筆は、その一点を何度も繰り返し照らし出しているように見える。
法学書とロシア文学という、一見まったく別のジャンルの本を並行して読むことで、「判断する」という行為の重さが、自分の中で少しずつ重なり合ってきた。法律は、判断のための枠組みや道具を整理する。一方で文学は、判断される側の具体的な息づかいや、制度の網からこぼれ落ちてしまう感情を描く。どちらか片方だけでは、世界の輪郭はどうしても歪んでしまう。その両方を行き来しながら、自分なりの「知恵」のかたちを探していきたいという気持ちが強まっている。
『問題解決ツールとしての法的思考力』を読み終えた今、自分が手にしたのは、六法全書のどこかの条文を暗唱できるようになった、という種類の満足ではない。むしろ、「条文を引く前に、自分は何を問おうとしているのか」「この問題のどこに、自由や平等や公正や信義則の争点が隠れているのか」を考えるための、ほんの小さな足場である。その足場はまだ心もとないが、それでも、何もない空中に立っていた頃に比べれば、だいぶマシだ。
これからも、婚活ビジネスの不可逆性であれ、サブスクの解約導線であれ、インフルエンサーと市民の非対称性であれ、さまざまな場面で「それって不可逆性ですよね?」と問いかけながら、自分なりに可逆性功利主義の限界と可能性を探っていくことになるだろう。そのとき、本書から学んだ法的思考力が、どこまで役に立ってくれるのか。あるいは、どこでまったく通用しなくなるのか。その両方を、これからの読書と実践の中で、少しずつ確かめていきたいと思う。そうやって、自分の中の知識は、いつか本当に知恵と呼べるものに変わるのだろうか。