新・読書日記1(読書日記1341)
「ラボ読書梟」では読書日記を書いたり小説を書いたりChatGPTと話したりと、日々「書くことの可能性」を模索しつつ、「読むことの可能性」そして「読書の可能性」を研究しております。普段は就労支援員を行っております。今まで様々な分野の本を読んできました。(生態心理学、社会学、文学、文化人類学、法哲学、法思想史、進化倫理学、進化心理学、政治哲学、政治学、経済学、数学、、、あげたらキリがありません)ここにその結晶を残してまいります。
★ブログ運営者お気に入りの本10選★
・・・・
(はてなブログ大学文学部との読書日記と区別するため、こちらのブログでは「新・読書日記」とします)
3月、4月といろいろな新刊が出たが、今日はこの一冊について書いてみたい。
「疲労社会」
私たちは以前よりも疲れるようになったのか?自分はそう思えない。明らかにデスクワークは昔よりも増えたであろうし、電車も寝ていれば最寄り駅に着く。エスカレーター、エレベーターと、昔に比べれば身体的な負荷は少ないはずだ。
この本は精神的な面での「疲労」について語りたいのだと自分は感じた。
読んでいくうちにおよそ見当はついた。
移動が速くなればなるほど、余分に時間があまるのは当然で、1日あたりの仕事量は変わらない。それはいい。身体的にはむしろ軽減されているであろうから。
問題は休日である。
移動が早くなればなるほど、人は「暇」になる。かといって、じっとしていられない。
「成長せよ」「人以上に努力せよ」「時間を無駄にするな」
この至上命令によって、休日の時間が容赦なくなにかに埋められていくのである。
また、情報過多の時代によって、ついついスマホに手を出したくなる。
「暇な時間」は「落着きのない時間」にシフトしたのである。
本書によれば、ニーチェは、刺激に簡単に反応する人間を非難していたとされる。
スマホも軽度とはいえそういった刺激の一つに入るであろう。
注意散漫とは刺激に対する抵抗力のなさなのである。
そういうことを本書では、多角的に論じられている。
薄くて軽い本なので、休日の電車で読むにはぴったりだ。


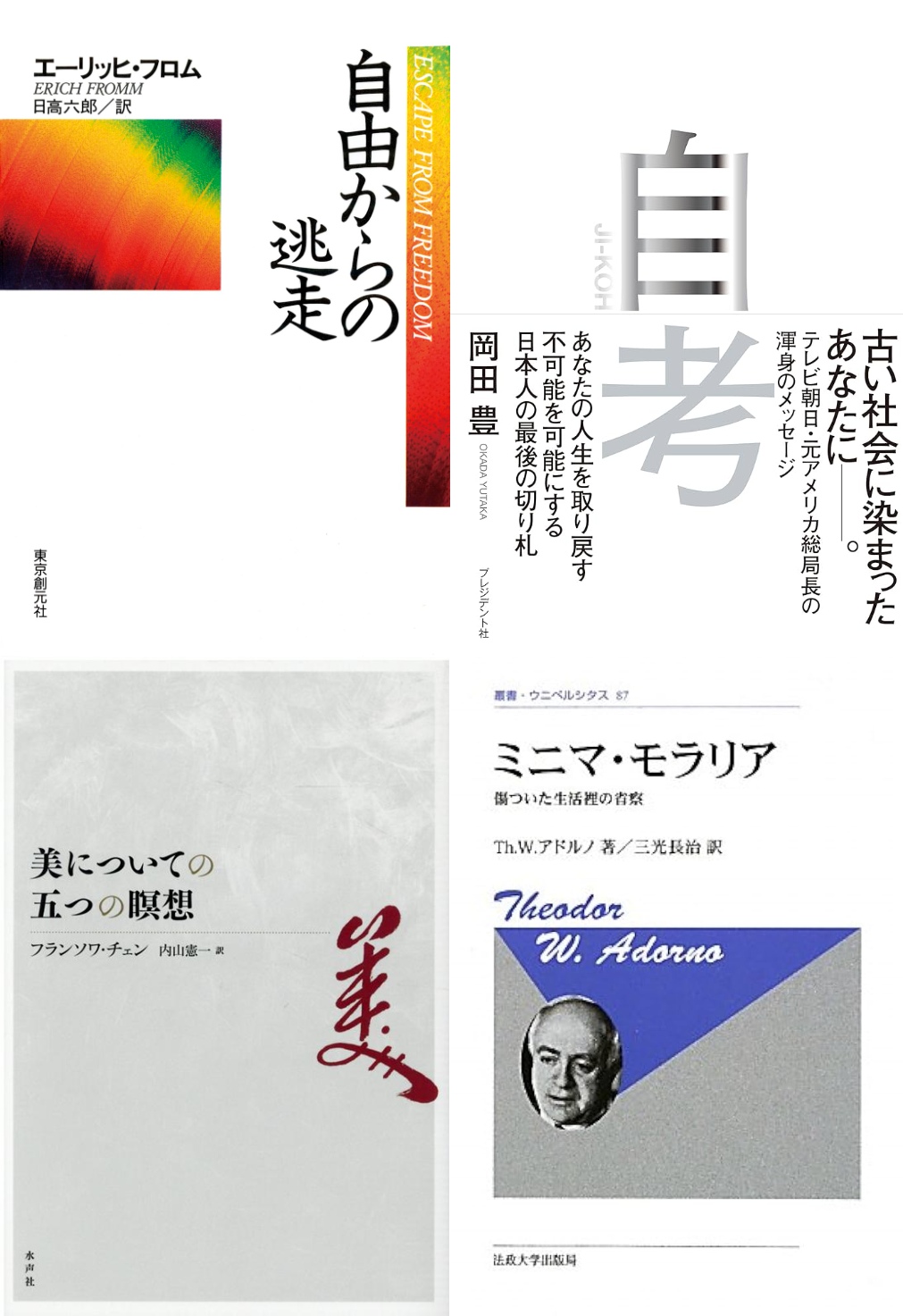
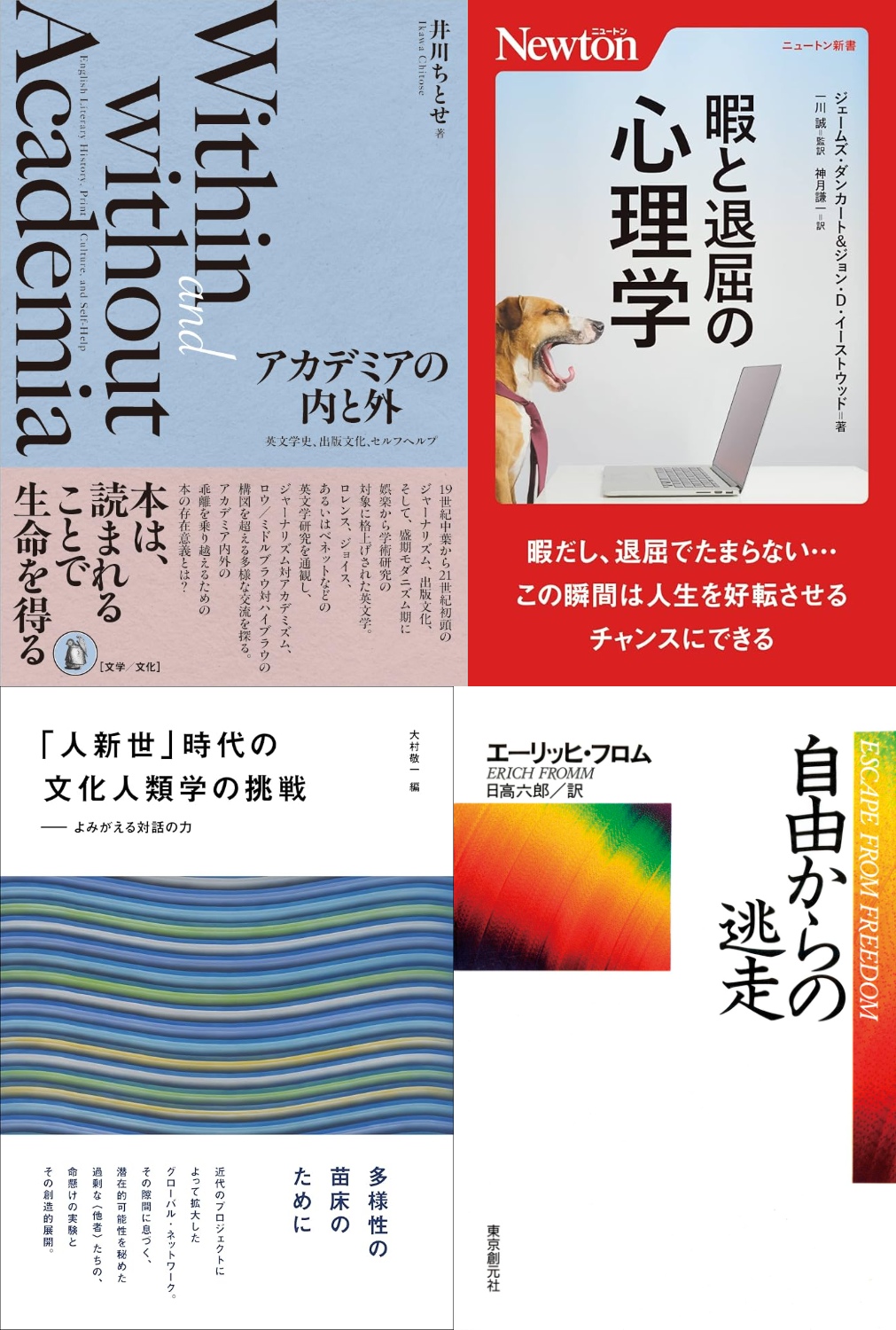
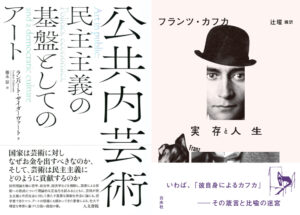

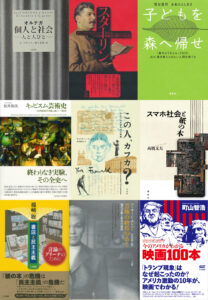
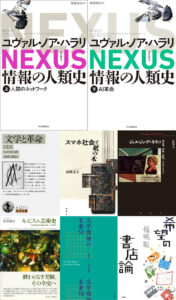
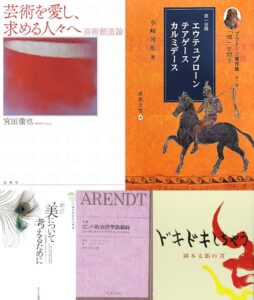
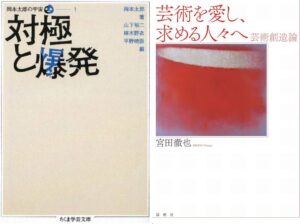
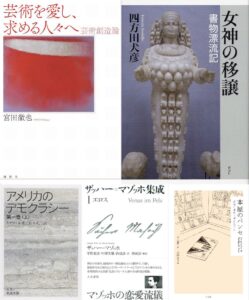

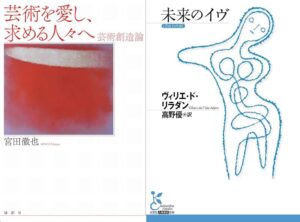

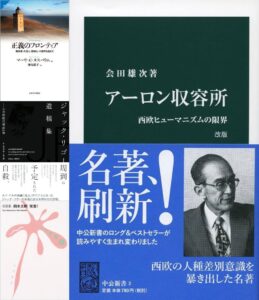
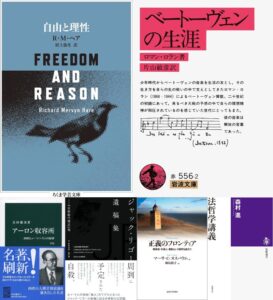

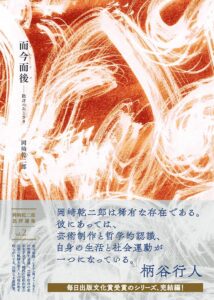
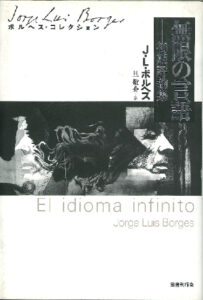
コメントを送信