佐々木俊尚『この国を蝕む「神話」解体 市民目線・テクノロジー否定・テロリストの物語化・反権力』徳間書店(2023)読了
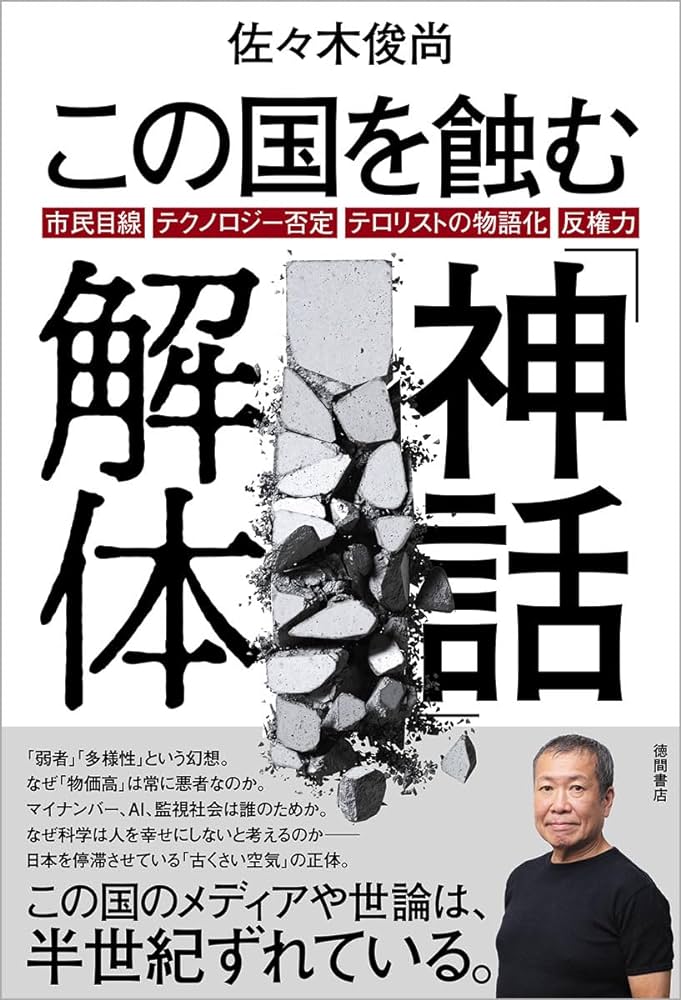
■株式会社徳間書店
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/tokumashoten_pr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
AbemaTVでよく見かけるこの方は、ラディカルでアクチュアルで、切れ味のあるコメントが印象的であった。
本書も期待から外れることなく、読み終えたころは自分を謙虚にさせ、「物事を表面的なところで判断しないようにせよ」と、メッセージを受け取った気分になった。
帯には「この国のメディアや世論は、半世紀ずれている。」と書いてあるが、その意味も理解できた。
例えばウクライナ戦争以降、物価上昇に関するニュースを頻繁に見かけるようになったが、ハンバーガーに関しては1980年代のほうが今より高いという著者の指摘があった。
ジョージ・オーウェル『1984』が日本で出版されると、1980年代は一時話題をさらったようだが、約半世紀後の2020年代もAIに関するネガティブな側面を全面押し出すようなニュースを見かける。
前者は物価に対する認識がずれているという指摘で(ずれているというよりかは、誤っている)、後者はテクノロジーがいかに利便性をもたらしたのかを見事に忘却した世論の認識は、やっぱりずれいているという意味であった。
本書は広い範囲(話題)にわたって様々なことに言及されるが、ひとつひとつ鋭い指摘がなされ、自分も誤謬をおかしていたなと、内省させられる内容となっていた。100ページくらいを読み終えたころは、この本は優れた良書だと実感した。なので時間を置きながら、ちまちまと読み進め、あとはいっきに最後まで頑張って読み通した。
社会正義に関する評論はうまいところを突いていると感じた。
ポリティカル・コレクトネスは否定しようがないので、あれもこれもと持ち出されると混乱する。
LGBTQなどがその最たる例である。
「失われた30年」という言葉が出て以降、一億総中流から一億総「弱者」化した印象を世論は醸し出すわけであるが、あちらもこちらも「弱者」になり、「かわいそうランキング」の様相を呈し、誰を優先に救済すべきかという状況になっている。
年金の少ない高齢者なのか、シングルマザーあるいはシングルファーザーなのか、貧困家庭なのか、障害を抱えたひとなのか、マイノリティの人なのか、クイアな人なのか、トランス女性なのか、シスの女性なのか。
新型コロナは経済と健康を両立することが困難であることを証明した。
つまり、場合によっては「正しさ」の「トレードオフ(=あちらが立てばこちらが立たぬ)」が発生するということである。
そして世の中はエネルギー問題をはじめとし、様々な両立不可能なトレードオフが存在する。
ここで「分断」している場合ではない。
正しさ同士がぶつかり合いをしていては、どちらかが倒れておしまいである。
そうではなく、理念同士の対決でなければならないと著者は語る。
理想は政治哲学のような構造だと著者は語る。つまり、理念同士がぶつかり合うことでお互いに知見がもたらされ、建設的な議論ができるのである。
これは激しく同意する。
理念なき対立はただの喧嘩に過ぎない。
理念さえあれば理性的な議論を行うことができる。
どちらが正しいか?という問いは意味をなさない。なぜならば、さきほど書いたように、今日ではポリティカル・コレクトネスが乱立しているからである。
ヴォルテールは、意見が違う相手であっても「それを主張する権利は絶対守る」といった言葉を残したそうである。
人格否定するのではなく、意見と人格を分離させ、意見は意見で受け止める。簡単なことが実は意外とできないのは、もしかすれば日本の教育が全体的に受け身の形式だからかもしれない。
本書からはいろいろなことを考えさせられ、いろいろなことを引き出せることができた。
なかなかみない良書である。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関連図書
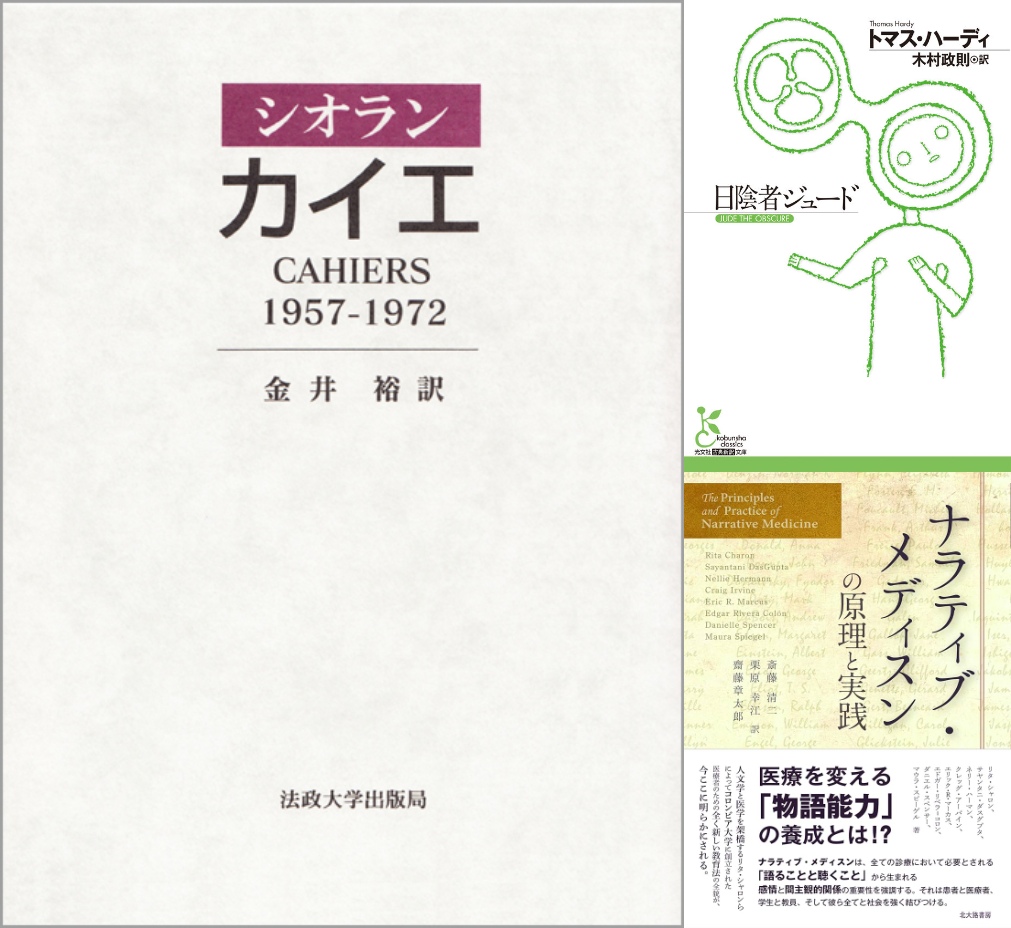
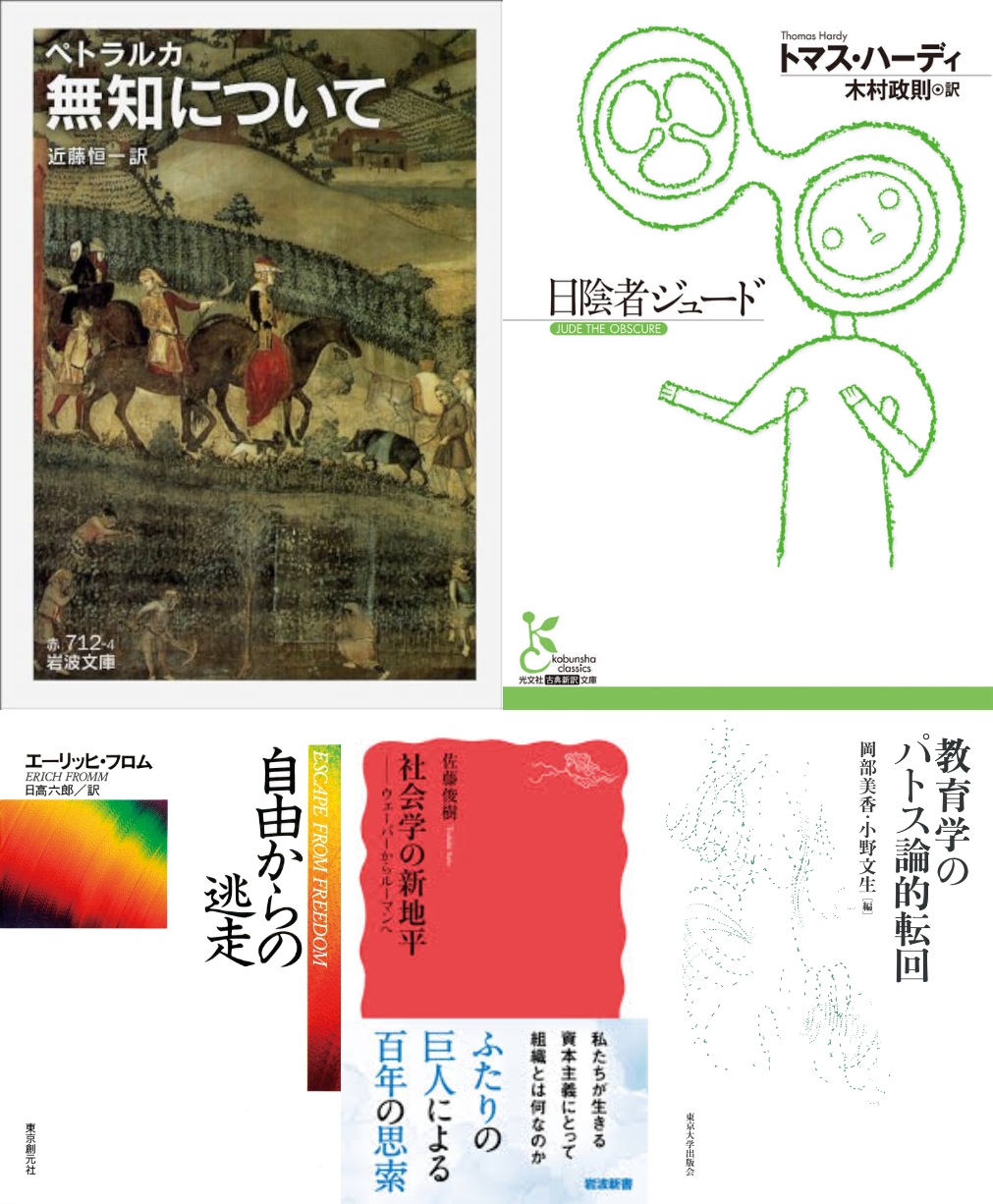
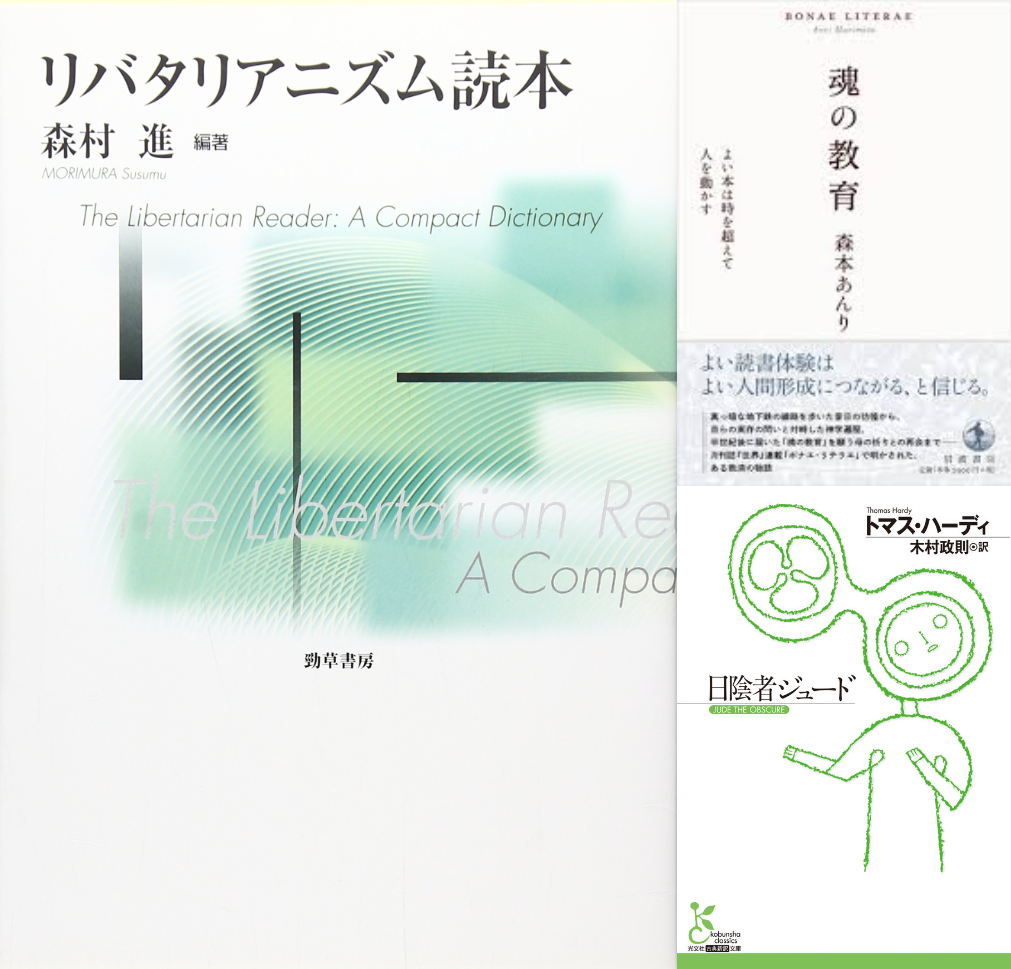
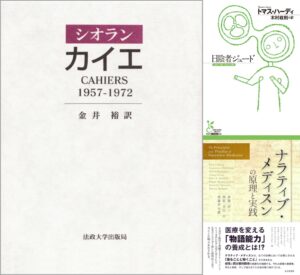

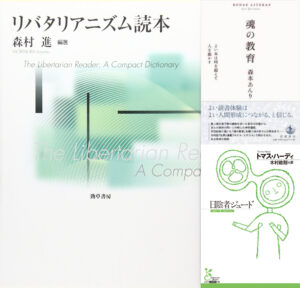
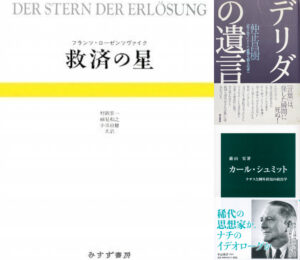
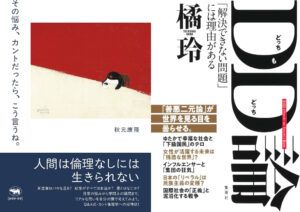

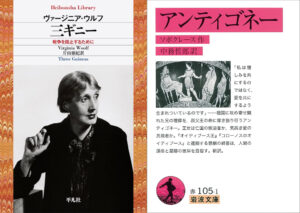
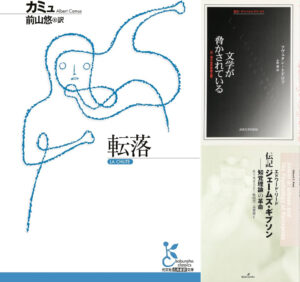
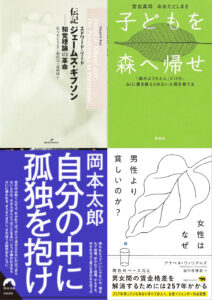
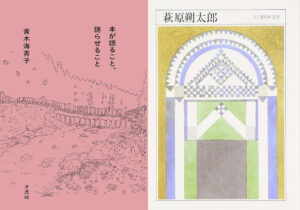
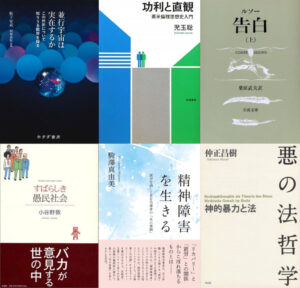
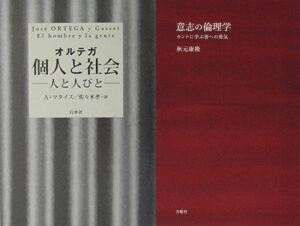
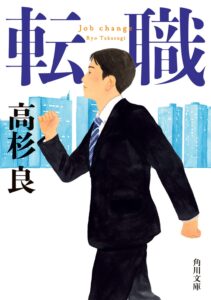
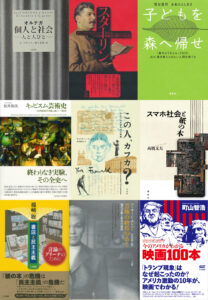
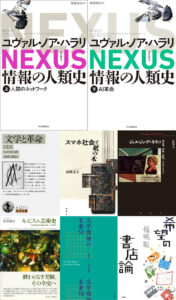
コメントを送信