読書日記778
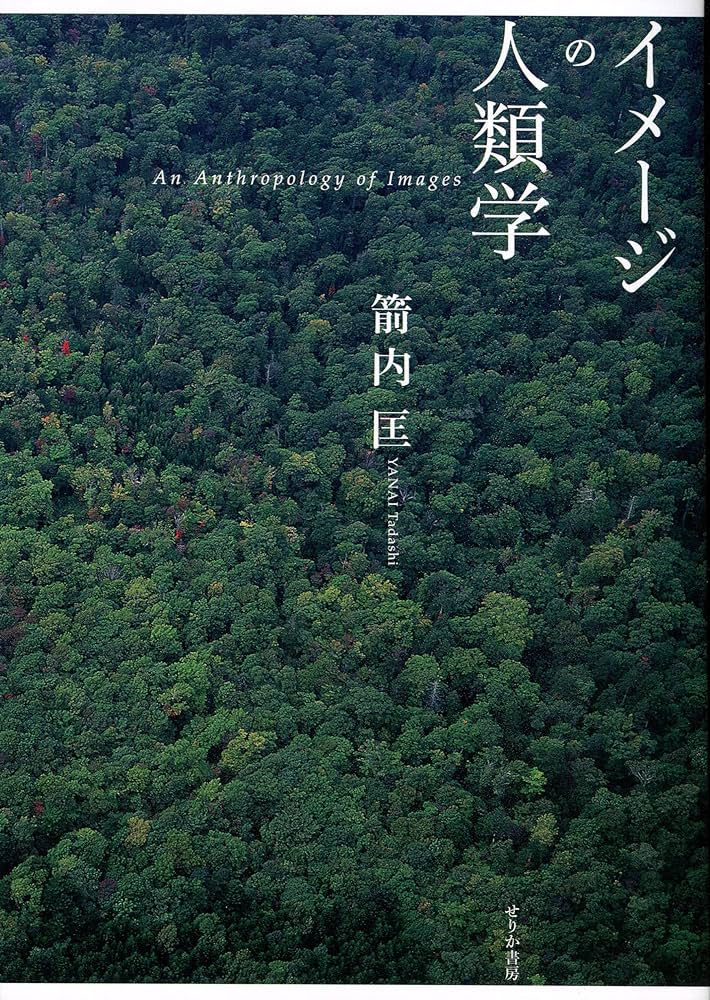
株式会社せりか書房
公式X(旧 Twitter ):不明
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
つづきをよみすすめた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー日記
最終章(9章)の手前まで読み終えた。
結論から書くと、未開社会と呼ばれる社会のシステムと先進国における社会システムも人類学的に見れば根本において同じような原理が働いているというものであった。
(前回、前々回の記事の内容に従えば、両方の社会にディナミズムが作用している。)
・・・
出版、統計、技術などが相互作用的に発達していく近代のなかでベイトソンのいう「参加する意識」が「参加しない意識」へとどのように変容していったのか。
それを説明する過程はこの八章において示唆されたように思うが、二時間程度一読しただけでは到底整理しきれるものではかったところが悔やまれる。
著者はフーコー、イアン・ハッキング、ベネディクト・アンダーソンらの仕事を紹介しながらハイデガーの提唱した「駆り立て体制」へと繋げていき、その後内容はガブリエル・タルド『模倣の法則』、『世論と群衆』へとシフトしていく。
・・・
内容が内容だけに、これを短時間で咀嚼し、整理しきることは端的に現時点の自分の力では不可能であると感じた。
まず、結論の解釈について書き、個人の解釈を添えることで本書の読書記録とする。
・・・
ベイトソンの二重理論(メッセージとメタメッセージが混在し、矛盾した状況であること)が、現代におけるサッカー観戦において見受けられること、そしてこのことが「儀礼」と相似関係にあるということが語られた。
本書によれば、ベイトソンは儀礼と遊びはほぼ同じものと考えた。
ある民族では男性が女性を、女性が男性を演じるという儀礼が存在している。
これはある側面では「非現実≒遊び」とも言える。
演じるというのは、つまり儀礼とは一過性、一時的なもので、この事例においては男性と女性の役割を「本当に」交換するものではない。
それでも彼らは伝統に沿って「真剣に」行う。
この伝統の存在自体は「現実的」なものである。
サッカー観戦も似たようなことが起きている。
現代人は無神論者が多いが、ワールドカップなどの行事(≒儀礼)において、勝利を「祈る」者が少なくない。
普段から習慣として祈ることはないが、行事で祈ることはある。
日本においても黙祷という儀礼行為が存在しているように、対極的にみれば現代文明においても神秘性、自然の「力≒ディナミズム」の作用が見受けられるということであった。
この原理は「アナロジスム」として地球上のあらゆる社会に機能している。
しかしながら、読解不足とはいえ総合的にみれば批判できる点はあると感じている。
最後まで読みきってからそのことについては指摘したいと思う。
公開日2022/10/24
関連図書
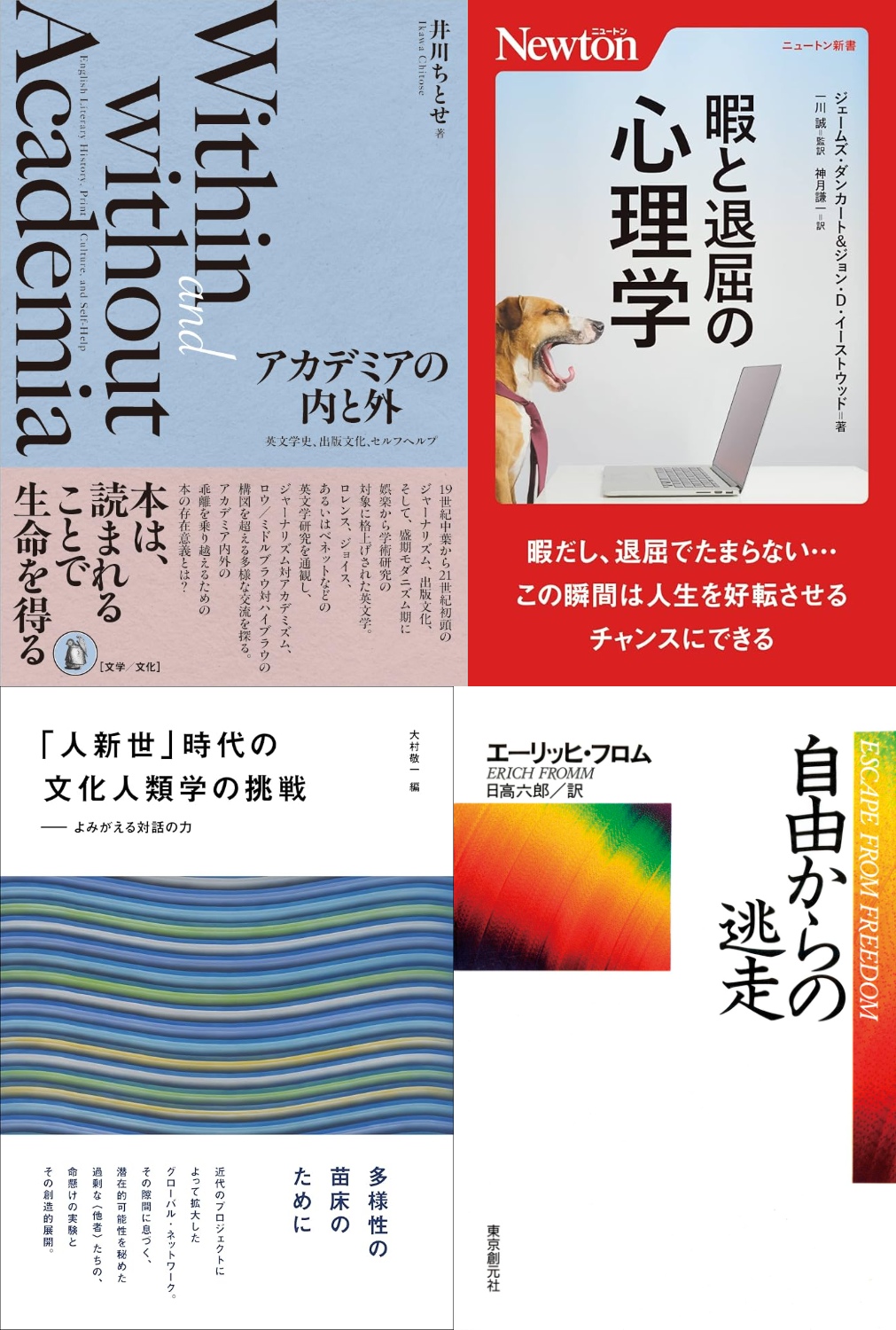
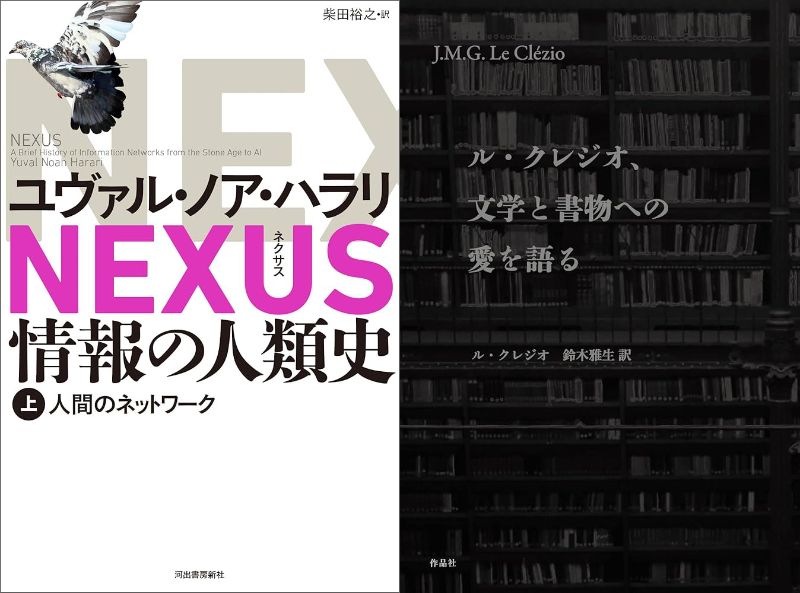

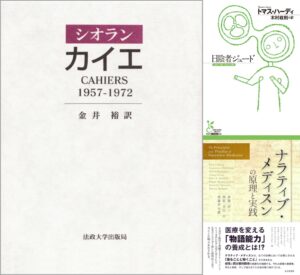

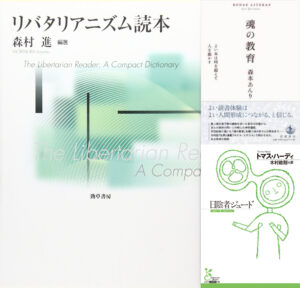
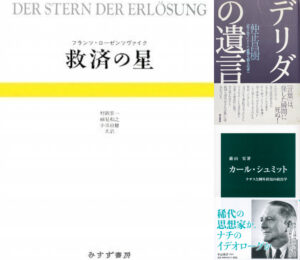
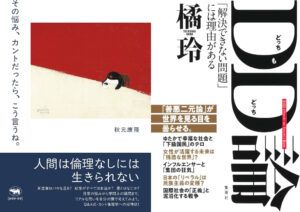

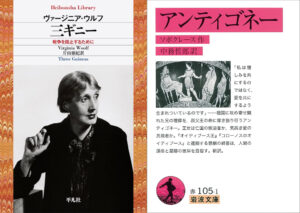
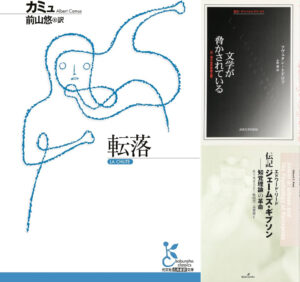
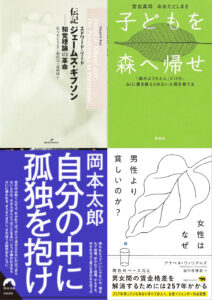
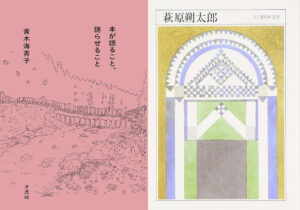
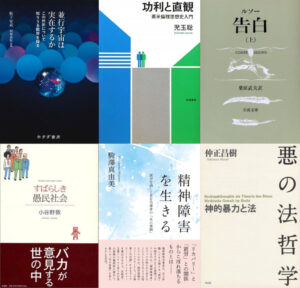
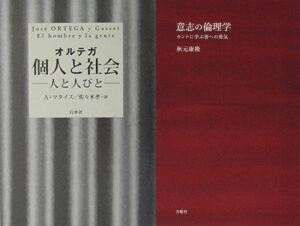
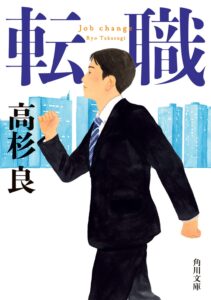
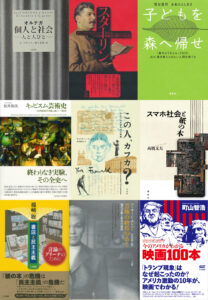
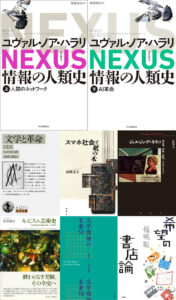
コメントを送信