新・読書日記98
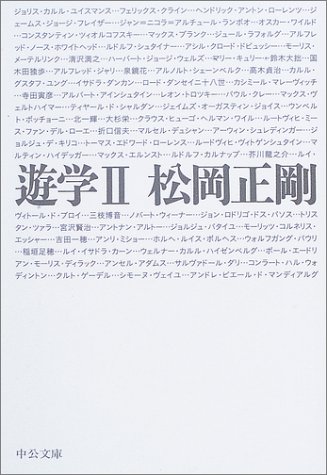
画像引用元:楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/kaitoriouji/txt-4122042615-240508rm410267
■株式会社中央公論新社
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
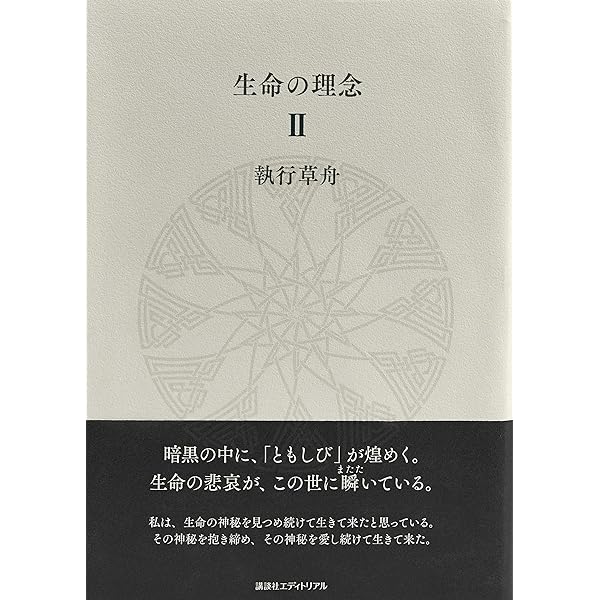
■株式会社講談社
公式HP:https://www.kodansha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
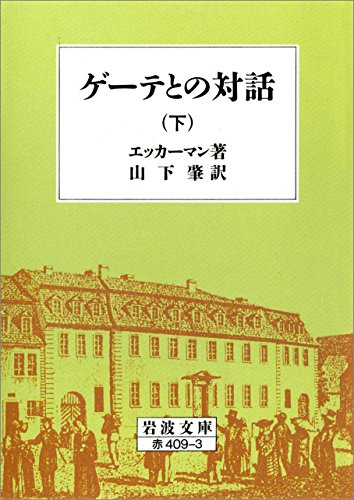
■株式会社岩波書店
公式HP:https://www.iwanami.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
メモ
『遊学Ⅱ』
ボルヘスについて語る松岡正剛
“しかし、ボルヘスがどうして超数学や新数学の文学的体現者でありえよう!私は書いた。「文学のジレンマは”言葉の使用”に起因するものではなく、したがって、その使用法および構造の円環化をはかったところで、ジレンマから脱出できるわけではありません。一方、数学のジレンマはそもそも、”数学の使用”に起因するものであり、したがって、その使用法および構造(数式、方程式)の円環化をはかることにより、数学は数学を解消し、これをあつかった存在のみが円環の廃墟を眺望することが可能になります。」” P310
カルナップについて語る松岡正剛
“カルナップが試みたことは、まず「命題の意味はその検証の方法である」ということだった。” P245
・・・
『ゲーテとの対話 下』
”「同類のものは、われわれを安心させる。しかし、反対のものは、われわれを創造的にしてくれるよ。」” P134
ソポクレスについて語るゲーテ
“詩人が、ソポクレスのように高度な精神内容をもっているなら、好きなように書いたところで、その効果はつねに道徳的なものになるだろう。” P142
政治について語るゲーテ
“「しかし、時代はたえず進歩しつつある。人間のやることなどは、五十年ごとに違った形態をとるのだから、一八〇〇年には完全であった制度も、一八五〇年にはもう欠陥となってしまうだろう。」「その上さらに、ある国民にとっては、他国民の真似ではなく、その国民自身の本質から、その国民自身の共通の要求から生じてきたものだけが、これは善であるといえるのだよ。(・・・)だから、ある外国の改革を導入しようとする試みは、自国民の本質に深く根ざした要求でないかぎり、すべて愚かなことだ。” P58
・・・
『生命の理念Ⅱ』
教育について語る執行草舟
“(・・・)どころが、戦後に電化製品がどの家庭にも普及したことで、子供が家事を手伝う余地がなくなってしまいました。このことが、戦後になって子供の情操教育を出来なくしている一因なのです。” P163
気品について語る執行草舟
“「走る」というのは、基本的に人間が慌てている時の行為です。そして、この慌てる人間には、その発動の原因としてその人の弱さが必ずあるのです。この弱さがあると、気品が無いことになります。” P179
“安楽と安定が、人間の心から気品を奪ってしまうことは歴史が証明しています。人間は戦うことを常に心に抱いていなければ、気品というものを見失ってしまうのです。” P186
“(・・・)昔の酒は現代のアルコール添加の酒と違って、ほとんどが菌食効果だったのです。” P194
“菌食によって解毒される毒とは、食物の中にある有害な自然物や、人工的な食品添加物などが挙げられます。” P197
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日記
執行草舟氏と直接話をして頂いてから1年半が経とうとしている。
ようやく、菌食に関する理解が深まってきた。
また、菌に関する知見を基盤とした文明史観は多くの考察材料を提供してくれている。
・腸自体は大して分解能力を持たない
・1000兆個ある腸内細菌が無くなると何を食べても餓死する
人体は宇宙とよく表現されるが、細菌が住みやすいように人体が設計されているかもしれないという仮説は非常に面白い。
実際、一般的に知られている進化論の多くは勘違いであることを自分は様々な本を漁って学んできた。
(人類は徐々に進化してたという説など)
なぜ健康食品ではなく菌食なのか。少しずつ自分のなかで腹落ちしてきた。
栄養学に対する批判的精神、対処療法に対する批判精神が養われた感覚を持つことができた。
・・・
腸と脳が密接にかかわっていることが近年ようやく理解されつつある。
つまり、思考に関係する脳は細菌と間接的にリンクしている。
武士道と騎士道を菌のレヴェルから考察するとまた深みが増してくる。
日本の教育と日本語能力に関する話も視点が斬新であり、深みを感じた。
ひとことで言うと、やはり本書は多くの考察材料を与えてくれる。
書いてみたいことはいくらでもある。
読み終わったら長めの感想文を書いてみたい。
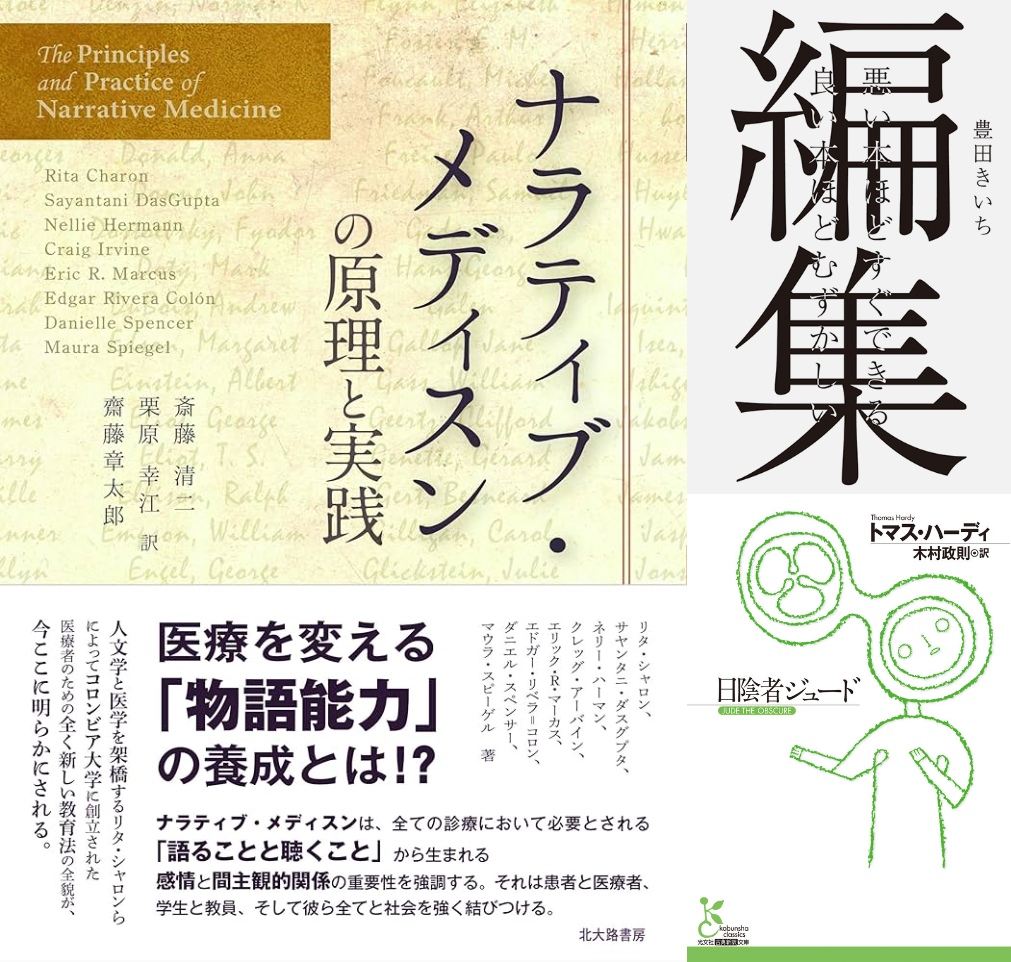
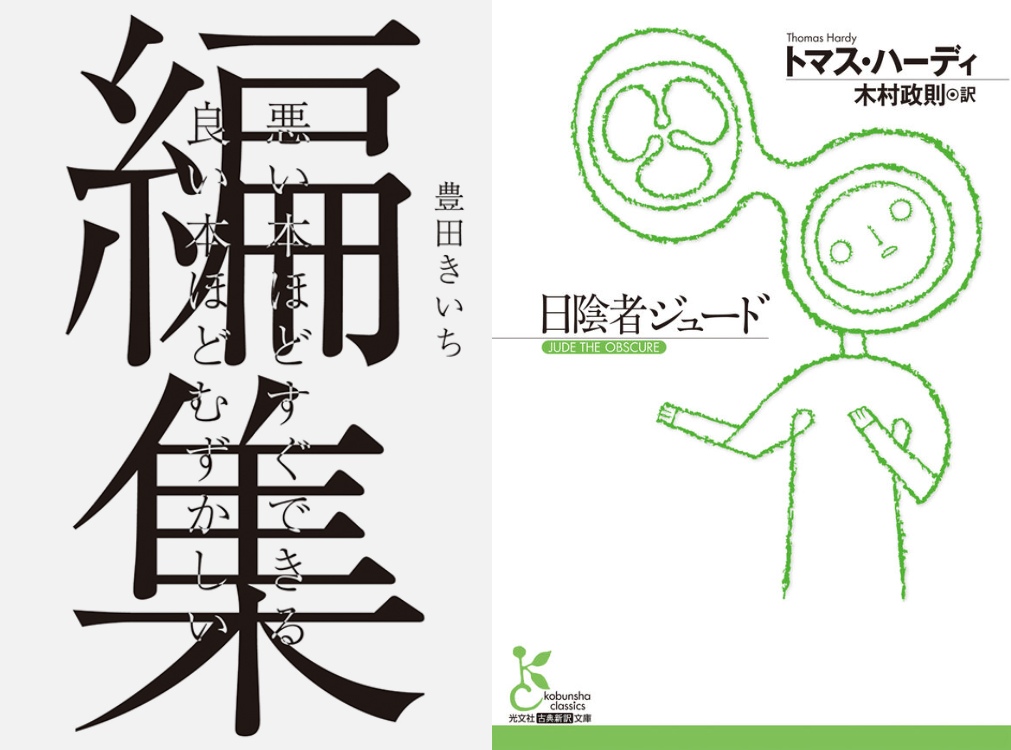

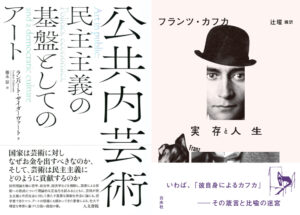

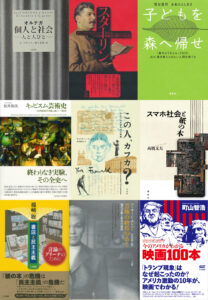
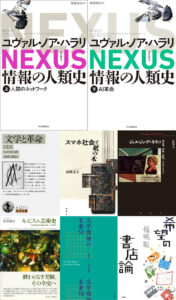
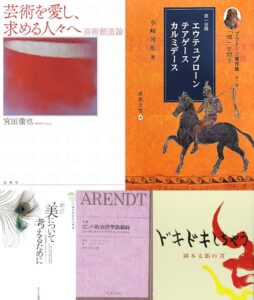
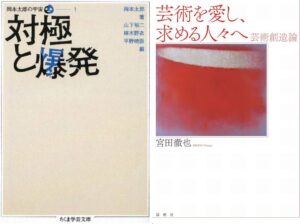
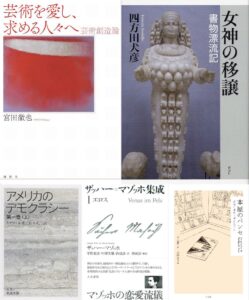

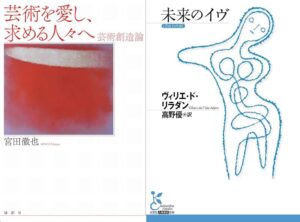

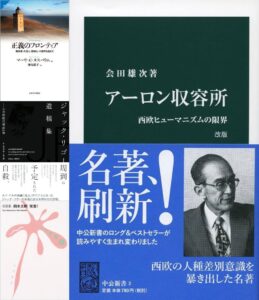
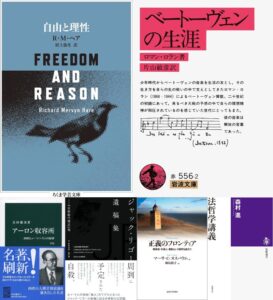

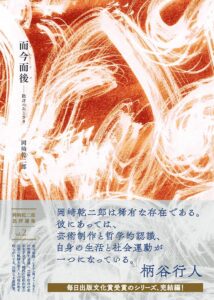
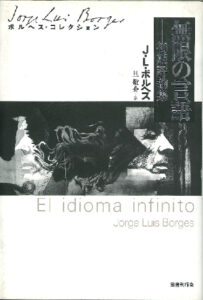
コメントを送信