読書日記954
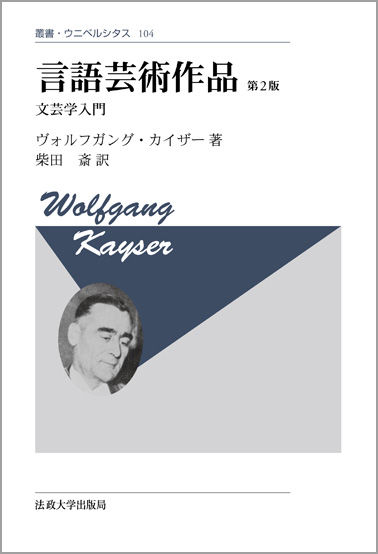
■一般財団法人 法政大学出版局
公式HP:https://www.h-up.com
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
カントの『判断力批判』の分析のなかで、認識の客観性や趣味判断の主観的側面について基礎的なことは理解したつもりだったが、それが倫理とどう繋がっていくか、次にそれを学んでいきたいと思ったが今日はもう気力がなかった。
こちらも興味を持っていた本で、文学の役割というものを学術的な観点から引き出せそうであるところ、そして文学の社会的意義に関する知見が得られそうであった点も気に入り少しだけ読んだ。
文学は教訓めいてもいるが、喜びも与えてくれる。
パッと思い付いたことがあった。
「何のために文学があるのか」という問いと「何のために教育があるのか」という問いが、「自然治癒力」の点で両者ともに似ていることをおもいついた。
傷口を治すのは薬ではなく自然治癒力である。
薬はあくまで「お手伝い」である。
教育も似ている。先生は生徒の学習を「お手伝い」することが限界であり、「分かる」という経験まで教えることは不可能である。
結局のところ生徒の「自然治癒力」を信じるしかない。
それと同じで、文学も「お手伝い」が限界なのかもしれない。
先生は授業を魅力的なものとし、勉強の喜びを生徒与えることはできる。
それと同じで、文学も魅力的なものとし、読者に喜びを与えることができる。
そこから副次的な何かの効果が生まれることはやはり読者の力を信じるしかない。
そう思いながら本書をちびちび読んでいた。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
カントの『判断力批判』の分析のなかで、認識の客観性や趣味判断の主観的側面について基礎的なことは理解したつもりだったが、それが倫理とどう繋がっていくか、次にそれを学んでいきたいと思ったが今日はもう気力がなかった。
こちらも興味を持っていた本で、文学の役割というものを学術的な観点から引き出せそうであるところ、そして文学の社会的意義に関する知見が得られそうであった点も気に入り少しだけ読んだ。
文学は教訓めいてもいるが、喜びも与えてくれる。
パッと思い付いたことがあった。
「何のために文学があるのか」という問いと「何のために教育があるのか」という問いが、「自然治癒力」の点で両者ともに似ていることをおもいついた。
傷口を治すのは薬ではなく自然治癒力である。
薬はあくまで「お手伝い」である。
教育も似ている。先生は生徒の学習を「お手伝い」することが限界であり、「分かる」という経験まで教えることは不可能である。
結局のところ生徒の「自然治癒力」を信じるしかない。
それと同じで、文学も「お手伝い」が限界なのかもしれない。
先生は授業を魅力的なものとし、勉強の喜びを生徒与えることはできる。
それと同じで、文学も魅力的なものとし、読者に喜びを与えることができる。
そこから副次的な何かの効果が生まれることはやはり読者の力を信じるしかない。
公開日2023/3/6
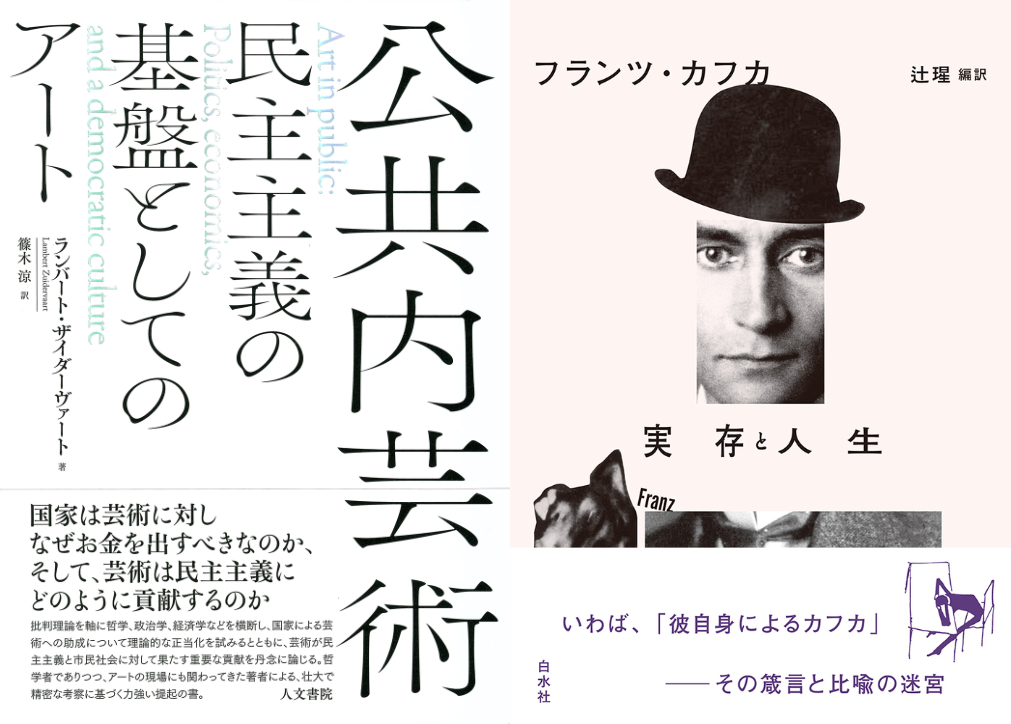
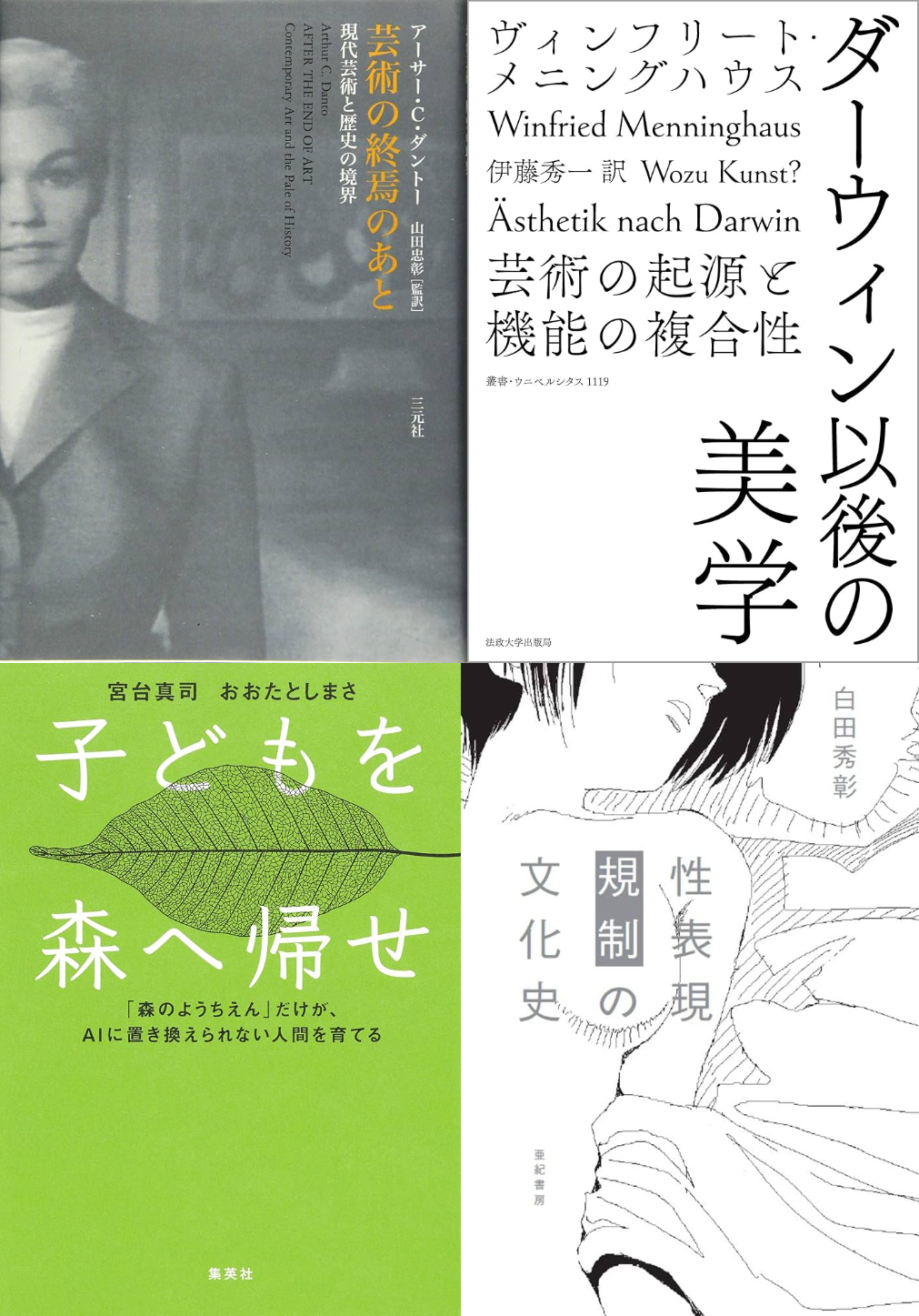
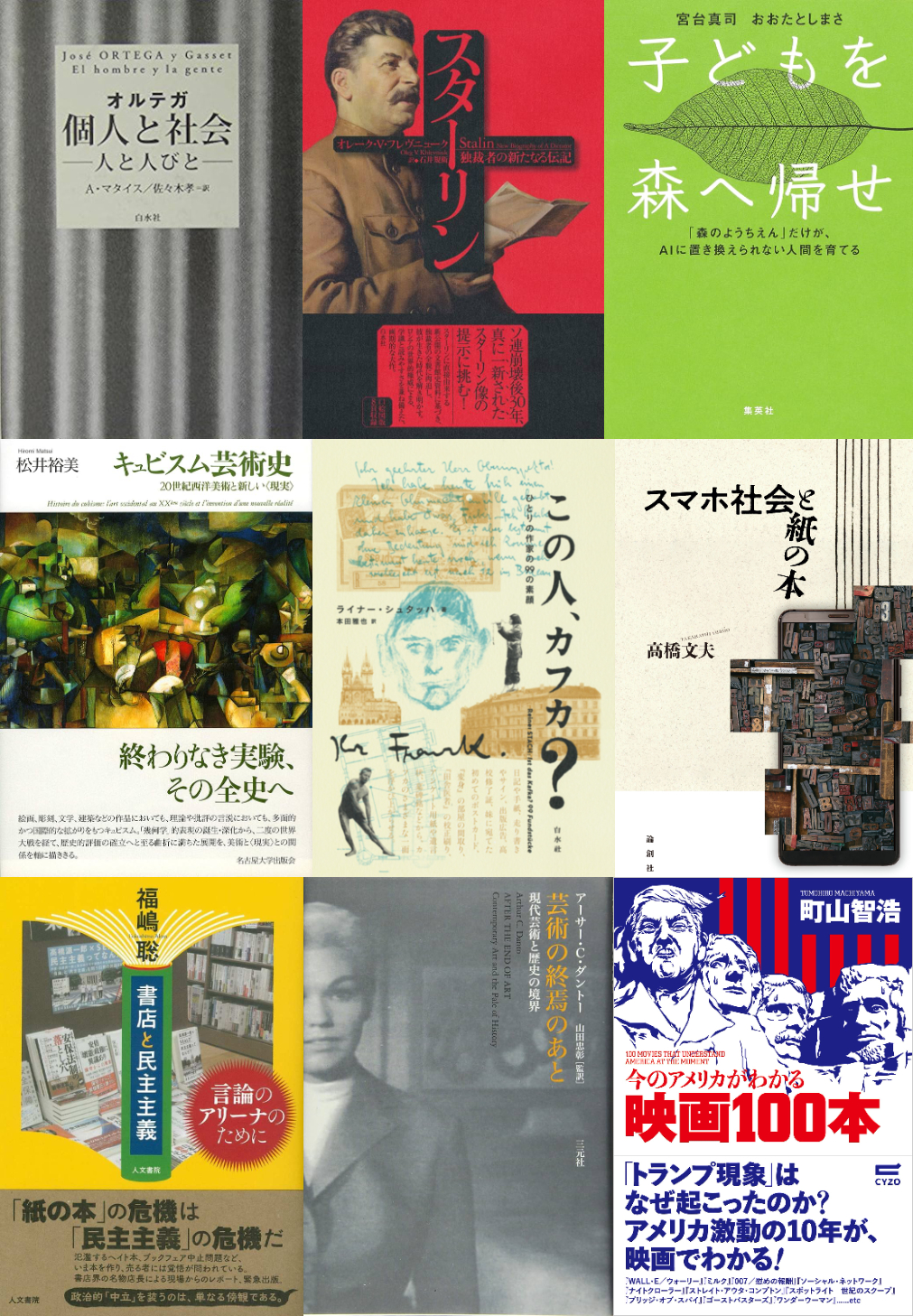
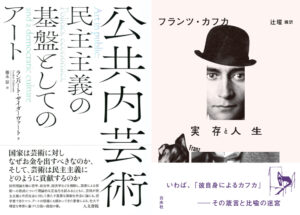

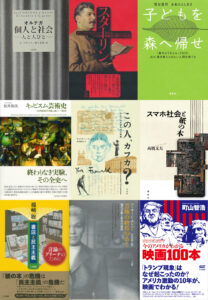
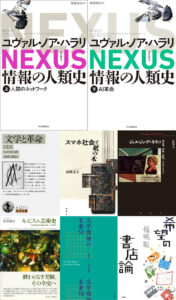
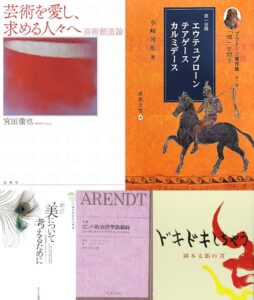
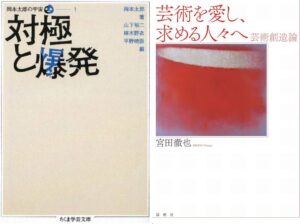
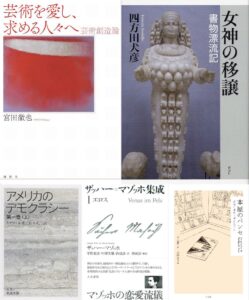

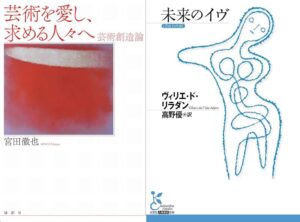

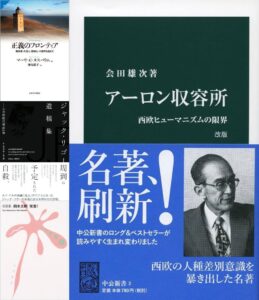
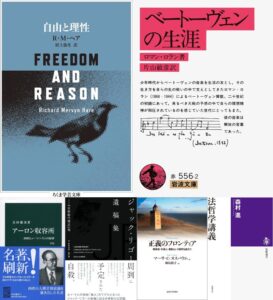

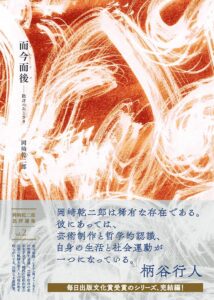
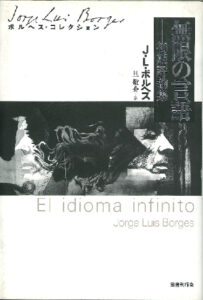
コメントを送信