読書日記962

■株式会社白水社
公式HP:https://www.hakusuisha.co.jp/
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hakusuisha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
その他数冊
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
仕事で一日の集中力を約7割ほど使い果たしたあとに、また読書で精神集中ということは難しい。
2回ほど読書中に眠ってしまった。
今日は本屋に入っても面白そうだと思える本もなく、収穫に欠ける一日であった。
古典には手が出ず、かといって現代文学にもいまいち手がでない。
哲学書のコーナーもさすがに見飽きた。
いよいよ自分で物語を書いてそこに楽しみを見出す時が来たのかもしれないとも思えた。
・・・
ロベルト・ボラーニョの本は読んでいて、これは面白くなりそうだなという予感はしたが本が重く20ページほどしか読めなかった。
『美学』はデリダによるカント批判が解説された。
しかしデリダという人物のあら探し的な研究方法に若干の嫌気がさし池田晶子の本を読むことにした。
池田晶子は生きることと考えることが完全に一致していなければ学問ではないと語る。
食べるために生きる、だから生きる手段として学問をしている、という常套句にはうんざりだ。
食べるために生きるのであればそれは動物と変わりがない。
カントが述べたように、人間は機械論的世界観に唯一抗い、意味を生に付与することのできる存在だ。
しかし意味を求めすぎると行き詰まりをむかえ虚無になる。
だから意味を求めない方が逆説的には意味のある生となるのであるが、それが機械論的な生き方になってしまうのではおろかではないか。
改めて思うのは、「善く生きる」とは機械論を越える合目的的な生き方であって、機械論的な制約(≒ニヒリズム)に抗いきれないからこそ問いつづけることが大事だということである。
文学はその指標とならなければならない。
公開日2023/3/15
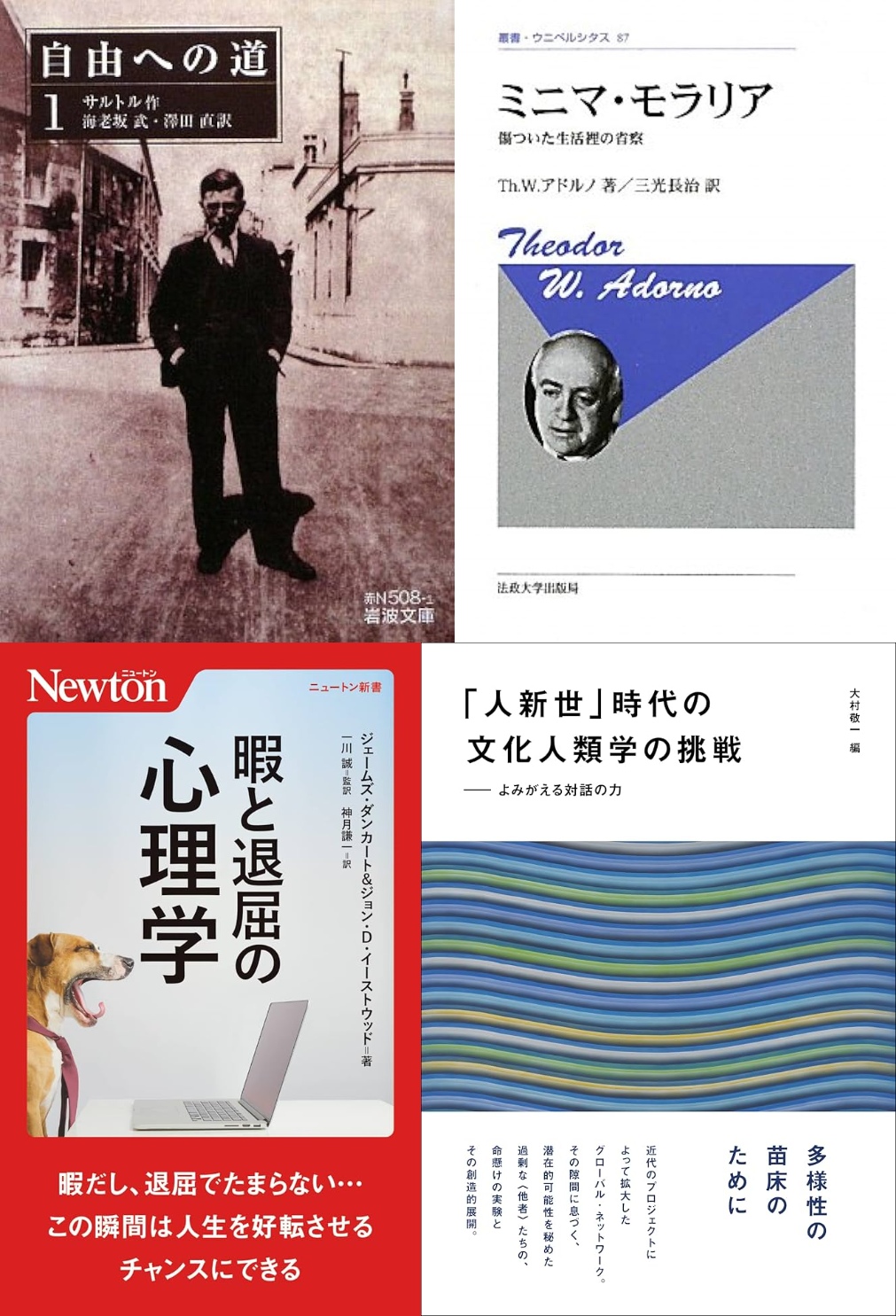
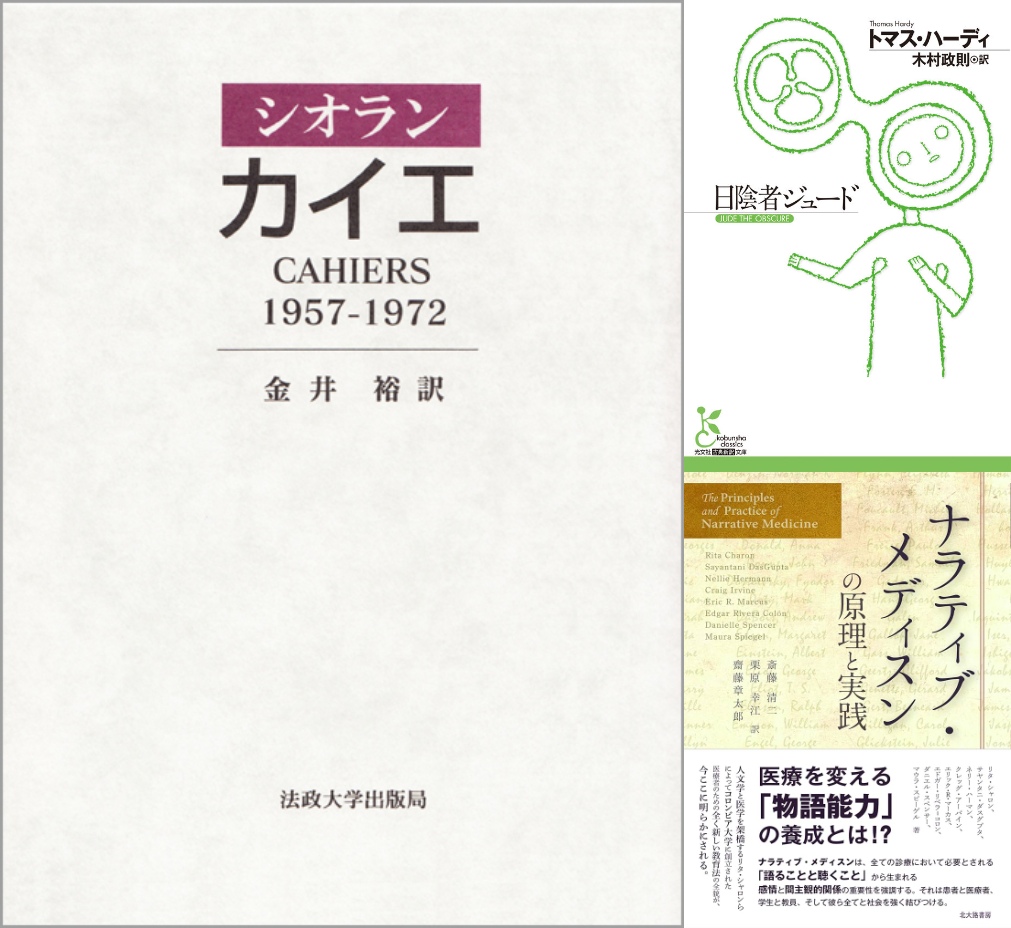
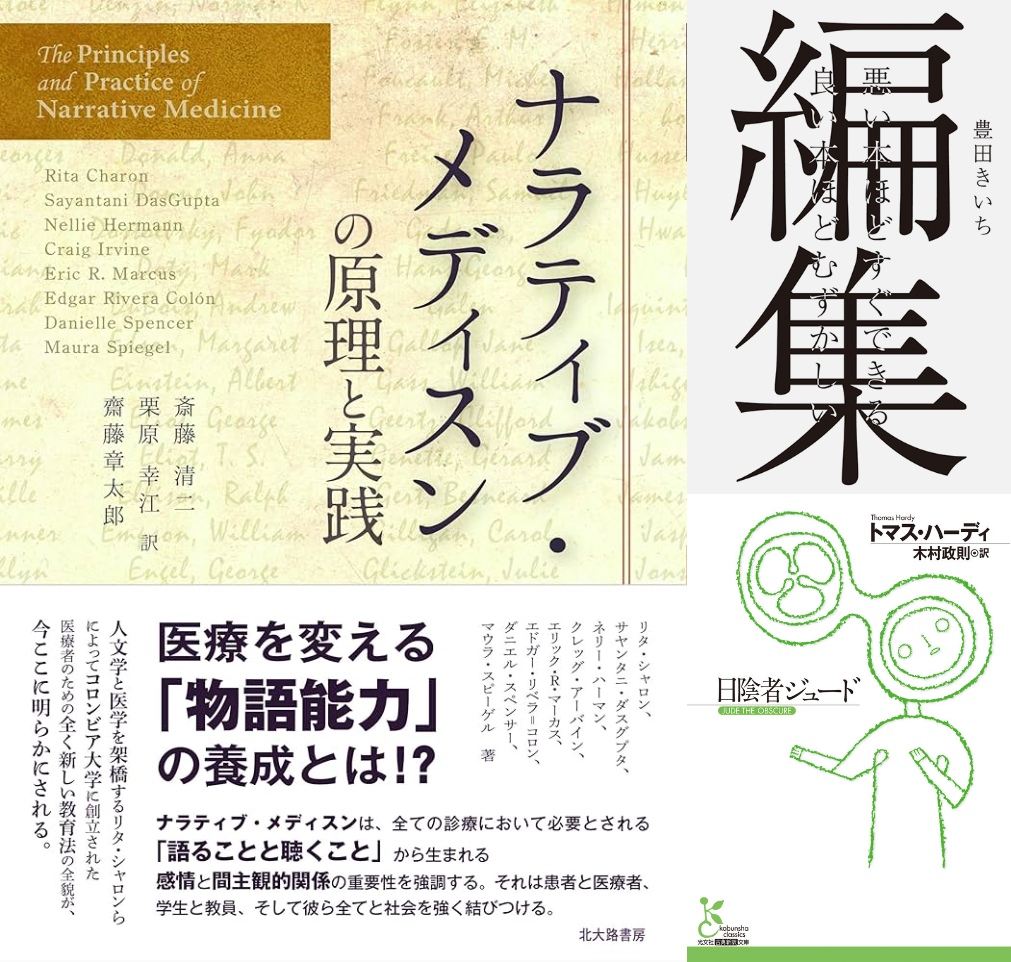
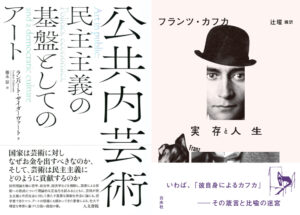

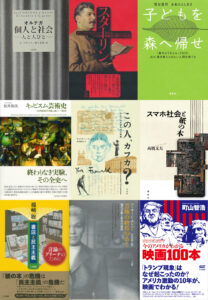
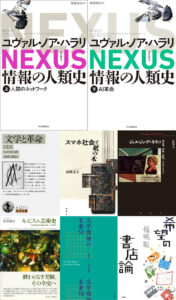
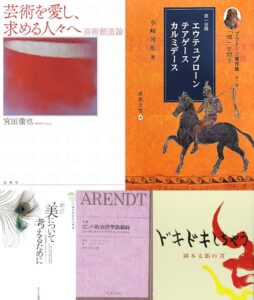
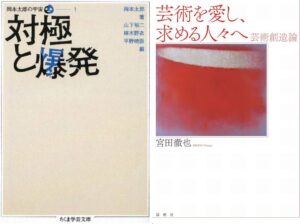
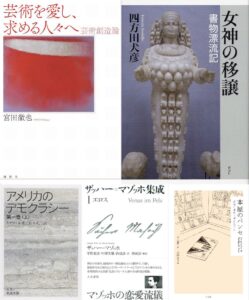

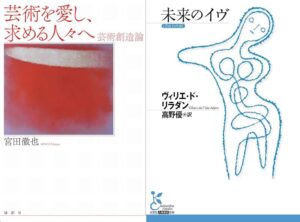

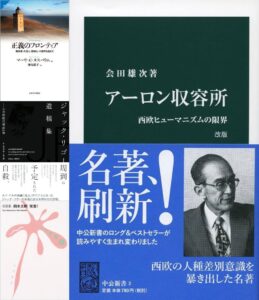
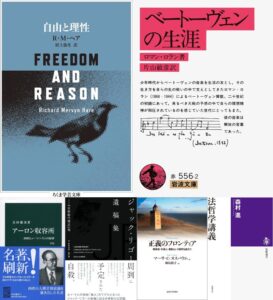

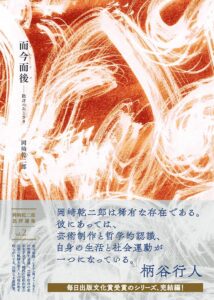
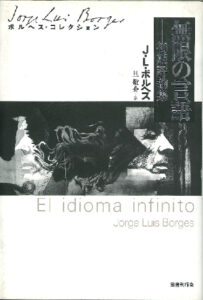
コメントを送信