読書日記967

■毎日新聞出版株式会社
公式HP:https://mainichibooks.com/index.html
公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/mai_shuppan
その他数冊
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
池田晶子はエッセイについて語る。
文筆家は毎回毎回、何について書くのか、ネタ探しは大変じゃないですかという主旨のことを池田晶子は問われ、全く困ったことがないと述べる。
“逆に、文章を書くには「ネタ」が必要なはずだという考えに改めて私は驚く。なぜ文章を書くに際して、言葉以外の材料が必要なのだろうか。(・・・)本来の「エッセイ」とは言うまでもなく十六世紀モンテーニュの『エセー』であり、その意は字義通り「試み」もしくは「試論」である。思考が自身を試みるために書かれる文章、それが本来の「エッセイ」である。” P335 (『考える日々』)
ブログを書くためネタ探しに必死になっている人がいる。
文章を書くという行為はいかなる意味を持つのか。
言葉を使ってなにかをするということは、それは本質的にいかなる行為を指すのか。
池田晶子の言葉はどこまでもストレートであった。
また、池田晶子は学術用語に注意、ということを語る。
「心的外傷」「トラウマ」「アダルトチルドレン」といった心理学用語をあげ、これらはフロイトやユングらが生涯をかけて心を理解しようとために「便宜的に」用いられた言葉だと語った。
実際は彼らも本当のところまでは分かっていないが現代人はなぜか「理解している」つもりになっている。ここにあべこべが見られると池田晶子は語った。
これにはいろいろと考えさせられた。
・・・
『美学イデオロギー』からひとつのヒントを得ることができた。
味覚と共通感覚を道徳法則に何故つなげ得ることができると彼ら(ヒュームを含めた18世紀イギリスの思想家たち)は考えたのか。
人は「甘い」という言葉を様々な文脈で使う。
「あの課長の評価は甘い」
「将来に対する考えが甘い」
「甘い香りのする美しい女性」
甘いという言葉は形容詞としてだけでなく、五感として知覚されもする。
ケーキの甘さと人生に対する考えの甘さ。
なぜ複数の異なる文脈において「甘い」という言葉が使用されるのか。
ここにはひとつの驚きがある。
これの共通理解が経験的に、かつ当たり前のように万人にインプットされているという事実である。
でなければそもそも言葉として通用しない。
「甘い」の意味が複数あるにせよ、文脈によって意味がコロコロ変わり、その度にいちいち意味の確認を取らなければならないという事態には陥ることはない。
しかもこれが特に勉強によって教えられることもなく、ただただ経験的にいつの間にか脳みそにインプットされるのである。
もはや個人的な理解として、構造主義的な言語観には賛同できない。
構造主義は犬や狼の特徴の違いによって、意味が「相対的」に規定されると考える20世紀の考え方であった。
この考え方で突き詰めていけば先程の「甘い」が様々な文脈で意味が変わるにも関わらず万人が当たり前のように理解できることをどう説明できるというのだろうか、という考えになっていく。
100人がケーキを食べて5,6人が「辛い」と言うなんてあり得るだろうか。
どちらがより甘いか、その比較はできるにせよ、「甘い」という言葉までは変わらない。
この絶対性を鑑みれば構造主義の基盤の弱さが露呈するはずである。
ヒュームらは情念、情動、情緒など心的な言葉を厳密に分け、動機付けと道徳を
結びつけて考えていた。
このあたりを読んで私はヒント得た。
「甘い評価」というものは、人にもよるが「悪くはない」と感じるはずである。
卒業間近で単位が足りない人が「甘い」評価によって良い成績を得たとしたらそれは「快」であるはずだ。
この「快」という心情は「甘い」と使用される文脈に共通して各々の心理に内在していると私には思われた。
「甘いマスク」「甘い香り」これはまず当てはまる。
「人生に対する甘い考え」これは個人のなかに内在している心理を推察すれば分かるはずだ。
そこには「楽をしている」という状態があるはずだ。
「楽」と「快楽」はほぼ等価だ。
かくして味覚と意味の複数性が説明可能になっていくはずである。
・・・
また、言葉の意味は「社会によって決められる」という主張に対しても思うところがある。
これはプラトンのイデア論を読んでいけばこの主張の欺瞞に気がつくはずである。
まず存在しないものは名付けることができないという当たり前の論理がある。
裏を返せば、存在するものには必ず名前が与えられる。
普通に考えれば分かることである。
人は水、土、木、火などを言葉で便宜的に区別しなければサバイバルに負けてしまう原始の時代があった。
そんなときに誰が水のことを火と言うだろうか。
これが歴史の連続性によって名前が固定されていき、長い時間をかけて様々な言葉が定義付けられていったと考えるのが妥当である。
さきに社会が規定するのではなく、さきに「存在」が言葉とその意味を規定する。
従って社会が言葉の意味を決めると考えるのはナンセンスであり愚行である。
・・・
えんぴつアートの問題をもう少し考えてみた。
人は人間離れした行為に「神業」という名で称賛を与える。
しかし今日はどうだろうか。
「神曲」「あれは神」と、なにか言葉が見つからないくらいに驚異的なものを目のあたりにしたときに日本人はそのように表現することがしばしばある。
まず一点には、神なき時代に安易に人間に「神」という形容を与えるところが現代ヒューマニズムの特徴が現れているように思われた。
もう一点としては、人間の関心が [ 技術>自然 ] になりつつあるのではないかと思われた。
何気ない風景をえんぴつで完璧に再現することによって初めて「すごい」と感心する。
それは厳密には技術に対する「すごい」なのであるが、もともとはその模倣の対象である自然のほうが明らかに完全性を持っているわけであって、やはり人間が自然をこえる存在として、神に代わる存在として世の中には認識されつつあるのではないか、執行草舟氏の『脱人間論』を読むことで一段とそのように強く思われたのであった。
執行草舟氏の本には何十回と繰り返し「人間は自分が神になったと思っている」と語られるが、宗教を忌み嫌う日本人の体質、また無神論的な価値観、そして神という言葉が形容詞として安易に使われる現代社会を思えばこの主張が的外れだとは到底思えないのであった。
公開日2023/3/20

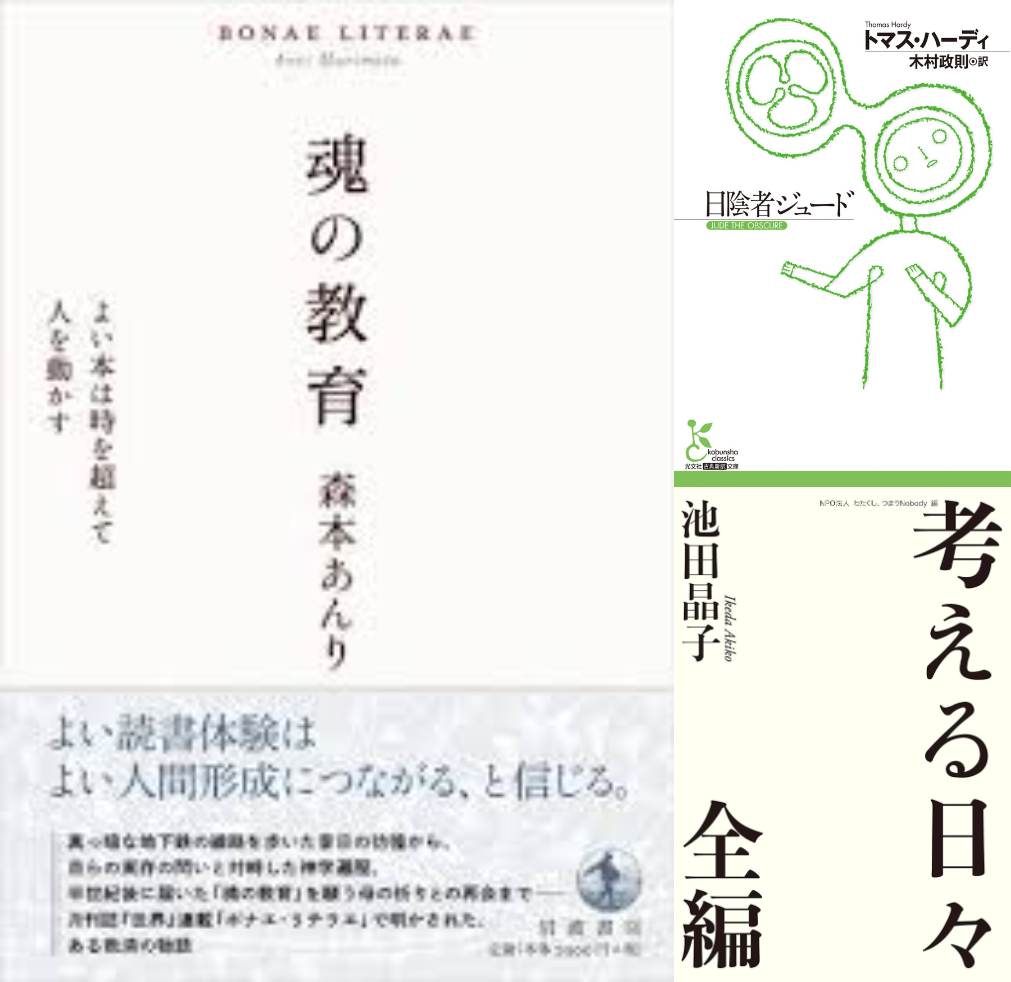






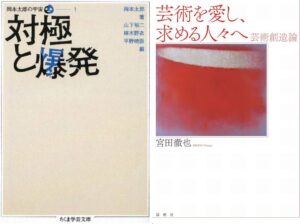









コメントを送信